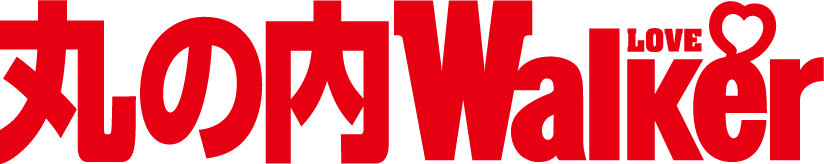三溪園のシンボル「旧燈明寺三重塔」の保存プロジェクトが始動! 500年の歴史を未来へつなぐ再生の物語
2025年11月14日 12時00分更新
横浜の自然と歴史的建造物が調和する国指定名勝の日本庭園「三溪園(さんけいえん)」。その小高い丘に静かにたたずみ、庭園のシンボルとなっているのが、重要文化財「旧燈明寺三重塔(きゅうとうみょうじさんじゅうのとう)」だ。2025年7月、この塔を次世代に継承していくため、5年をかけた壮大な保存プロジェクトが始動した。
京都から移築された三重塔の大規模修繕は約70年ぶり!
「『旧燈明寺三重塔』(以下、三重塔)は、室町時代の1457(康正3)年に建てられたもので、関東地方にある木造の塔では最古の重要文化財です。もともと京都府木津川市の燈明寺に建っていましたが、三溪園の創設者である実業家・原 三溪によって1914(大正3)年にこの地に移築されました」と、三溪園の学芸員・原 未織さん。
園内の建造物の中で最も古いこの建物の移築は、その後の庭園を造成する上で大きな鍵となったという。園内の建造物や庭の造りの配置は、さまざまな場所からこの塔を含めた風景を眺められるように工夫されており、まるで絵画のような美しい景色が見る者を楽しませてくれる。
移築から100年以上の時が流れ、塔は今、大きな節目を迎えている。通常、三溪園では園内にある10棟の重要文化財の屋根修繕を約30年ごとに行っている。建造物の多くは木造で、雨風や紫外線、湿度など自然環境の影響を受けやすく、損傷や劣化が進む前に修繕を行うことが必要だからだ。
「檜皮葺屋根の『臨春閣(りんしゅんかく)』などがそれにあたりますが、三重塔は瓦屋根のため、最後に大規模修繕が行われたのは1954(昭和29)~1955(昭和30)年。約70年を過ぎた現在、昨今の文化財修繕の指針に基づいて、屋根の修繕に合わせて耐震診断・補強も実施することになりました」と、原さんは話す。
修繕工事は2018(平成30)年に始まった第1期を皮切りに、「臨春閣」など他の重要文化財から順次開始しており、今回の三重塔の修繕はそれに続く事業。2025(令和7)年度から約5年にわたるプロジェクトとなる予定だ。
日本の歴史や技術、文化を継承していくことも重視したプロジェクト
この保存プロジェクトは、単に「歴史的建造物を修繕・保存する」というものではなく、「『歴史の鼓動を次世代につなぐ再生の物語』なんです」と、原さんは話す。
「塔が建設された室町時代の技術や美意識に敬意を払いながら、一つ一つの工程を丁寧に進めていくことはもちろん、横浜の街や来園者の方々、そして、プロジェクトにかかわる職人さんにも、その歴史をつないでいくことが大きな使命だと考えています」
例えば、修繕には全国から集まる熟練の職人たちが作業にあたるが、若い世代への伝統技術の継承という重要な役割も、このプロジェクトは担っている。
「三重塔だけでなく、他の建造物の屋根などの修繕は約30年ごとに行われますから、今やっていることがまた30年後にも実施されるわけです。今回は若手として頑張ってくださる職人さんが30年後には立派なベテランになり、次はリーダーとして若手の職人さんを連れてきてくれるかもしれません。私たちが建造物を維持し続けることと同時に、無形の技術を継承していく機会を彼らと一緒につくり上げていくことが、文化財修繕の大事な役割だと考えています」。
重要文化財の修繕というと仰々しいイメージもあるかもしれないが、実際には大工や瓦師、畳職人などがかかわり、身近な日本の伝統や文化が活性化していくことにもつながるのだという。
三重塔の知られざるエピソードとは!? 修繕の様子はSNSなどでも発信予定
三重塔は、園内の風景と合わせて遠くから眺める姿も美しいが、ぜひ丘の上まで登って近くで見るのがおすすめだ。塔の全高は約24メートル。細部は和様でまとめられ、端正に組み合わされた斗栱(ときょう)や、整然と並ぶ垂木(たるき)などが長く突き出た軒を支えている様子などが見られ、500年以上の時を超えてきた歴史の重みを間近で感じることができる。
交通網や重機が今ほど発達していない大正時代に京都から移築するのはさぞ大変だったことがうかがえるが、それにまつわるエピソードも。
「京都から移築するとき、塔の中心を貫く長い心柱(しんばしら)が輸送中に道のカーブを曲がりきれなかったため、いったん切断し、移築再建時に三溪園でつなぎ直したという記録が残っています。三重塔の心柱は建物を支える柱ではないので、そんな大胆なことができたのではないでしょうか」。
また、塔が立つ向きにも面白い逸話が残っている。移築当初は現在の向きから90度南側に正面があったが、戦後の修繕工事の際、文化財の専門家によって本来の向きが判明したため、現在の向きに変更されたのだという。
今回の保存プロジェクトでは、斗栱や垂木、屋根の瓦なども全て調査し、解体しながら進められる。木部の傷みを含め、実際に始まってみないとその修繕内容は明らかにならないが、その過程で建物の内部から年代の根拠となる痕跡や昔の彩色などが見つかる場合があるのも、修繕の醍醐味だ。
「三重塔の本来の塗装は、全体が赤(丹)、垂木の小口が黄土色、連子窓が緑青色という彩色だった可能性が、戦後の修繕の記録から判明しています」と、原さん。
この原色を塔に復原するかどうかはまだわからないが、三重塔が将来に向けて再生するのは事実。その過程は、三溪園の公式HPやSNSなどでも随時発信される予定なので、ぜひチェックを。
ふるさと納税で応援!数百年後も遺したい横浜の風景を次世代へと守り継ぐ取り組み
三溪園の三重塔は、園内からだけでなく、湾岸沿いの高速道路や本牧山頂公園などからも望むことができ、横浜のシンボルとしても愛されている。
今回の保存プロジェクト始動に伴い、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」でこのプロジェクトを横浜市の寄附の活用先として選べるようになったのも、話題の一つだ。寄附金は三重塔の耐震診断のほか、調査・設計・修繕工事などに活用され、返礼品として園内での食事会やお茶会、建築物を巡るプレミアムツアーなど、三溪園ならではの体験型リターンが用意される予定。歴史ある塔に新たな命を吹き込み、次世代へとつなぐ取り組みを応援できる、またとない機会だ。
「修繕期間中は塔が足場などで覆われるため、見られなくなる期間もありますが、いずれ本来の美しい姿に戻った状態でお目見えします。そこから先も変わらず存在するようにしていくのが、今回のプロジェクトの大きな目標です。『三重塔が見えるな、あぁ、横浜だな』と安心していただける風景を守り継いでいきますので、ぜひ見守っていただければと思います」と、原さんは話す。
加えて、「昔の三重塔の写真を見て『こどものころ見た風景と全く変わらない』と喜んでくださる方がとても多い」とも。
「それこそが、三溪園の価値だと思うんですね。室町時代の三重塔が500年経った今、ここに建っていますが、同じように数百年後も変わらぬ美しい風景として遺り、後世の人々にも同じような思いを持っていただけたらいいですね」
季節ごとの美しい景観も必見。足を運ぶたびに新しい日本文化を発見
三溪園は、約17万5,000平方メートルもの敷地を持つ広大な日本庭園。1906(明治39)年から一般公開された外苑と、園の創設者である原 三溪のプライベート空間だった内苑の2つの庭園から成り、歴史的建造物と四季折々の自然が美しく調和した景観が見どころだ。
京都や鎌倉などから移築された17棟の歴史的建造物のうち、原さんがぜひ見てほしいとおすすめするのが、内苑に立つ檜皮葺屋根の「臨春閣(りんしゅんかく)」。紀州徳川家の初代藩主の頼宣が和歌山県・紀ノ川沿いに建てたといわれる数寄屋風書院造りの別荘建築で、このあたりから望む三重塔の美しさもまた格別だ。
もともと三重塔と同じく燈明寺にあった「旧燈明寺本堂」は、台風被害により解体された後、同じ場所での再建が叶わず、1987(昭和62)年に三溪園に寄贈・移築された建造物。三重塔と向かい合う形で配置されており、併せて見ると、かつての寺の配置が思い浮かぶような工夫が凝らされている。
織田有楽斎(信長の弟)ゆかりの茶室「春草盧(しゅんそうろ)」、豊臣秀吉ゆかりの「旧天瑞寺寿塔覆堂(きゅうてんずいじじゅとうおおいどう)」、徳川家光ゆかりの楼閣「聴秋閣(ちょうしゅうかく)」などが点在し、「3人の武将にまつわる建造物が一堂に会するのも、三溪園ならではなんですよ!」と、原さん。
ほかにも、初春の梅、春の桜、夏の蓮、中秋の名月や秋の紅葉といった四季折々の美しい景観や、期間限定のライトアップなど、散策の楽しみは尽きない。
横浜の中心地にいながら、古都のような日本文化に触れられるのが三溪園の最大の魅力。「三重塔の保存プロジェクトを通じて、三溪園の魅力をより多くの方に知っていただき、『一度行ってみたい』『また行ってみたい』と思っていただけるきっかけになれば、うれしいです」
国指定名勝 三溪園
住所:神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1
電話:045-621-0634
開園時間:9時~17時(最終入園16時30分) ※イベントなどにより変更の場合あり
休園日:12月26日~31日
入園料:大人(高校生以上)900円、小・中学生200円、横浜市内在住65歳以上700円
交通:JRほか横浜駅からバスで約40分、JR・横浜市営地下鉄桜木町駅からバスで約30分、三溪園入口下車徒歩5分。JR根岸駅からバスで約10分、本牧下車徒歩10分、三溪園南門入口下車徒歩7分
駐車場:入場から2時間まで1,000円、2時間以上は200円/30分
HP:国指定名勝 三溪園
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」
HP:ふるさとチョイス
横浜LOVE WALKERの最新情報を購読しよう