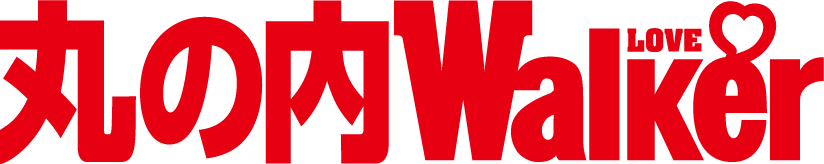「東京駅丸の内駅舎」に使われてるレンガ、何個か知ってますか? 職人延べ75万人で作り上げた世界最先端のレトロモダン建築の歴史に迫る!!
2025年01月31日 12時00分更新
太平洋戦争での焼失と戦後復興
1914年に東京駅が開業した後、丸の内の中心が馬場先通りから行幸通りに移り、鉄筋コンクリート造のアメリカ式オフィスビルが次々と建設されます。1923年には初代・丸ノ内ビルヂングが竣工、1933年には東京中央郵便局が竣工するなど、1920~1930年代には一丁紐育(いっちょうニューヨーク)とよばれる日本最大のビジネス街が形成されました。そして、東京駅開業当初は東海道本線と横須賀線合わせて上下80本だった発着本数が、1935年には上下202本、山手線・京浜線も最大8両編成が1分40秒間隔で運行されるようになり、駅利用者も12倍程度に激増、東京駅は限界を迎えます。そのため、八重洲側の車両基地移転でのホームの増設や線路数増加などが行われました。改良工事の進む東京駅でしたが、第二次世界大戦に突入し、次第に戦況が悪化するにつれて空襲も激しくなり、遂に1945年5月25日の空襲で東京駅丸の内駅舎北口付近に焼夷弾が着弾、炎上してしまいます。火の勢いが凄まじく、駅舎は全焼してしまい、鉄骨造だった屋根は焼け落ち、そして内装も焼失、見るも無残な状況に変わり果ててしまいますが、耐火性能が優れていた煉瓦造だった3階までの外壁は幸いにも残っていました。駅機能の復旧がすぐ行われ、2日後の5月27日には列車の運行が再開されていたことは驚愕ですが、駅舎に関しては終戦の8月15日時点でも屋根は焼失し、焼け落ちて垂れ下がった鉄骨もそのまま、床も穴だらけ、しまいには1階の片隅に死体も転がっているという悲惨な状態で使われ続けました。
戦後の1945年10月に入り、ようやく戦災復旧工事に着手し、その際に構造的な負担を軽減することを目的として3階部分を撤去することとなり、物資不足の中、堅牢に作られた3階外壁を苦労して切断・撤去したのち、ドーム屋根は木造トラスによる台形の屋根に掛け替えられました。当初は建て直しまでの4~5年程度、長くても10年程度持たせる計画で突貫工事を行ったとのことでしたが、1947年3月15日の完成から約60年使われ続けることとなります。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう