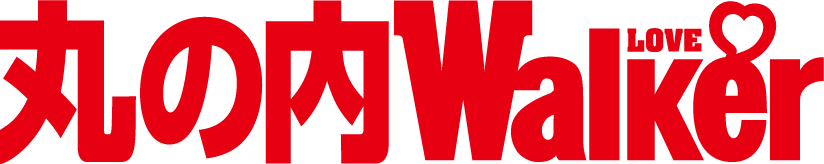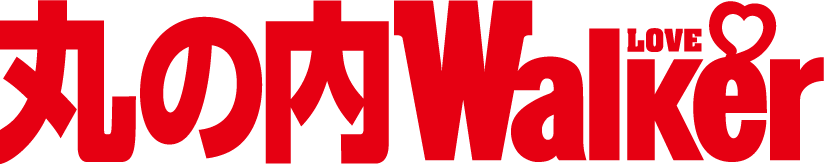「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025」のテーマ“音楽の時空旅行”とはいったい何だったのか!?
2025年05月07日 07時00分更新

「時空旅行ってなんですか」と聞かれて答えられますか?
1995年にフランス・ナントで始まった「ラ・フォル・ジュルネ(熱狂の日)」は、クラシック音楽をより多くの人々に届けることを目的とした音楽祭。東京では2005年から『ラ・フォル・ジュルネ TOKYO』(以下、LFJ)が開催され、毎年異なるテーマのもと、多彩なプログラムが展開されています。
今年、5月3日(土・祝)から5日(月・祝)までの3日間で開催されたLFJのテーマは、「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」でした。音楽の発展に多大な貢献をした都市とその時代にスポットライトを当てるというものです。
……と、さらっと触れましたが、“音楽の時空旅行”と言われてピンとくるでしょうか。正直なところ、時空旅行とは一体どういう体験なのか。
筆者は5月5日に取材に行ったのですが(取材記事はこちら:クラシック音楽の聴き方、楽しみ方ってどうすればいいの? 「ラ・フォル・ジュルネ」で考えた)、取材前の打ち合わせで編集部の人に「音楽の時空旅行ってなんですか?」と聞かれましたからね。確かに、音楽祭が提示するには、ちょっと抽象的なテーマに思えます。
たとえば「今年のテーマはバッハです!」なら、バッハを中心に、同時代の作曲家や影響を受けた後の音楽が紹介されるんだろうな……と思うでしょう。あるいは「今年のテーマはイタリアです!」なら、バロック時代の音楽家(ヴィヴァルディなど)からイタリア・オペラの傑作(ヴェルディやプッチーニなど)を紹介するのだろう……と考えるはず。
しかし、今年は「Mémoires(メモワール)」。そう言われても……。お、音楽の時空旅行……?
音楽で時空を旅する。言葉としてはロマンがありますが、想像してみるとどうでしょうか。そもそも人間は(現在、筆者の知る限りですが)異なる時空を移動することはできません。
本記事では、そのあたりを解説しながら、今年のテーマの魅力にせまってみたいと思います。
Q:なぜ「時空」なのか?
A:歴史がめちゃくちゃ長いから
そもそも、クラシックで「時空」というワードが出てくるのはなぜなのでしょうか。これは、「“クラシック音楽”の歴史はめちゃくちゃ長いから」と考えるとわかりやすい。
バッハの時代には、まだピアノは普及していませんでした。ブラームスは50代の頃に蓄音機にピアノ演奏を録音しましたが、これは“史上初の録音”とまで言われるほど歴史的なもの。一方、アメリカのガーシュウィンやロシアのショスタコーヴィチは、映画音楽を多数手がけていました。つまりこの時代には映画が普及してきたわけです。
これらの作曲家の作品がすべて「クラシック」として一括りになるのですから、クラシックという音楽の「時空」はなんと広大なことか。

バロック音楽の時代には、まだ「ピアノ」はありませんでした。鍵盤楽器といえばこちらのチェンバロ、あるいはオルガンなどのために書かれていました
今年のLFJのコンサートで演奏された曲を2つ挙げます。ヴィヴァルディの「四季」。1720年代前半に作曲されていたそうです。アメリカの作曲家、ガーシュウィンの「ピアノ協奏曲」。こちらは1925年に作曲されています。
この2曲の間には、なんと、およそ200年もの時が流れているのです。日本で200年前といったら、「異国船打払令」(日本の沿岸に接近する外国船は見つけ次第に砲撃し、追い返すよう定めた追放令)が出ている時代ですからね。
一口に「クラシック」といっても、実に長い、なが〜い歴史があるわけです。よって、期間中に実にさまざまなコンサートが実施されるLFJであれば、コンサートをいくつか聴くだけでも“異なる時代”の文化に触れることができると考えられます。わざわざ「“時空”旅行」とテーマに掲げる理由は、そのあたりにあるのではないでしょうか。
Q:なぜ「旅行」なのか?
A:都市の歴史や文化とクラシックは影響し合っているから
今年のLFJは、時代だけではなく、「音楽の発展に多大な貢献をした都市」にもスポットライトを当てています。それはなぜか。
クラシックは、「都市」と結びついた音楽ともいえます。その都市の歴史や文化に作曲家は影響され、彼らが生み出した作品がその都市の名物ともなりました。
たとえば、ウィーン。モーツァルトやベートーヴェンをはじめ、数多くの作曲家が活躍して「音楽の都」と呼ばれています。19世紀のウィーンで流行した「ウィンナ・ワルツ」は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるニューイヤーコンサートの名物。
ウィーンでハプスブルク家が築いた壮麗な宮廷文化は、政治・芸術・学問の中心としてヨーロッパをリードし、その中でクラシック音楽は王室の権威と結びつきながらも、市民社会へと溶け込んでいきました。

「ウィンナ・コーヒー」はウィーン発祥とされていますが、「ウィンナ・ワルツ」のように都市名が付くクラシック音楽のサブジャンルはめずらしいものです
あるいは、ドイツのライプツィヒ。「トーマス教会少年合唱団」という古い音楽団体があり、かつてこの教会の音楽監督に就いたことがあるのがバッハ。世界初の民間オーケストラ、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団もこの都市に本拠地を置いています。
そういった歴史から、メンデルスゾーン、ヴァーグナーなどもこの街で活躍し、市街各地に音楽ゆかりの場所があるのですね。
フランスのパリは、19〜20世紀の転換期にクラシック音楽史の主要な舞台となります。パリ万国博覧会が開かれた際には、ドビュッシーがガムランに触れる、マーラーのような当時の音楽界の有名人が会場を訪れるなど、クラシック音楽にとっても大きな影響を与えました。
当時のドイツの「ロマン派」たちとは異なる、情緒や物語性の描写よりも、雰囲気の表現に比重を置いたようなパリの作曲家たちの音楽。同時期に絵画界を席巻した印象派の絵画と共鳴するような彼らのスタイルは、鉄道の発展、セーヌ川、カフェ文化のざわめきと共に、パリの都市そのものを音で描き出したとも言えるでしょう。

フランスのエッフェル塔のデザインは当時のパリっ子たちの間でも賛否両論。クラシック音楽界の反応でいうと、「アヴェ・マリア」で知られる作曲家、グノーは反対の抗議声明に署名しています
言葉や文化の異なる都市で、さまざまな作曲家が育ち、活躍してきました。その都市に憧れて作曲家がやってくることもあれば、作曲家の名が高まることで都市自体が注目されることもあります。
ヨーロッパの主要な都市においては、その都市の歴史とクラシック音楽がただ共存しているのではなく、深く絡み合い、影響し合っているわけですね。
なので、クラシックの催しで「都市」をテーマにしたコンサートを並べることには必然性がありますし、それらの演目を楽しむことで都市の魅力が浮き彫りになるのは、いってみれば“旅行”のような魅力がある、ということなのでしょう。
「音楽の時空旅行」を感じさせるプログラム
長々と解説してきましたが、「音楽の時空旅行」というテーマを掲げていても、それを感じさせる内容でなければ意味がありません。
もちろん、そのテーマを念頭に置いたプログラムがいくつもありました。たとえば、5月5日の有料コンサートの一つ、「四季世界一周」です。
公演番号:323「四季世界一周」
(曲目)
《ヴェネツィアの春》
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 抜粋
《パリの夏》
フォーレ:夢のあとに
サン=サーンス:死の舞踏
《ブダペストの秋》
ブラームス:ハンガリー舞曲第17番
セルキン:あなたの愛に
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
《ニューヨークの冬》
ガーシュウィン:「パリのアメリカ人」から ブルース
パーキンソン:ルイジアナ・ブルース・ストラット
バーンスタイン:ウエストサイド・ストーリー(メドレー)
バロック音楽の中心地だったイタリアの作曲家、ヴィヴァルディの「四季」からスタート。そこから、19世紀後半から数多くの作曲家を輩出したフランスの楽曲でパリを表現。ブラームスにインスピレーションを与え、ほぼ同時代のバルトークを輩出したハンガリー(ブダペスト)が舞台となった音楽につなぎ、最後は20世紀のクラシック音楽で大きな存在感を発揮したアメリカのニューヨークへ。

会場ではコンサートごとにプログラムも配られているため、理解の手助けになります
異なる時代の楽曲を、都市と“四季”というコンセプトでパッケージ。18世紀から20世紀まで、イタリア→フランス→ハンガリー→ニューヨークと、時代の移り変わり、作曲家の故郷、文化の隆盛までもが描かれていました。
このように、異なる時代や都市にスポットライトを当てることを意識したコンサートを並べることで、クラシックという広大な歴史を持つ音楽の魅力をわかりやすく伝える……。それが、今年のLFJの狙いだったように思います。
「音楽の時空旅行」と聞くと、なにやらSFのような大仰な響きに思えるかもしれません。しかし、音楽の発展に多大な貢献をした都市とその時代にスポットライトを当てることは、長い歴史を持つクラシックに触れて楽しむにあたって、とてもわかりやすい切り口だったのではないでしょうか。
LFJの場合、有料公演はおよそ45分と短めで、チケット価格も2000円台〜とリーズナブル。朝から晩まで複数の公演をハシゴすることも可能でした。いろいろな時代の音楽、さまざまな都市で生まれた音楽に気軽に触れられるのがLFJの魅力。
クラシックをもっと身近に感じられる貴重な機会、それがLFJです。2026年も、「クラシック音楽の時空旅行」を楽しめるLFJの開催に期待しましょう!
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう