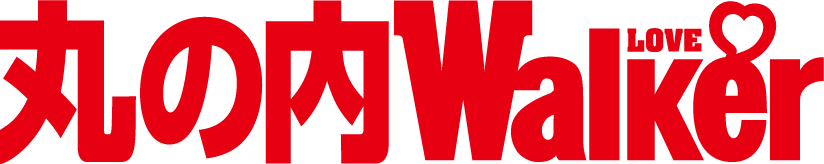丸の内を彩る花はただの飾りじゃなかった! 養蜂で人、街、自然を結ぶ丸の内びと―― 伊藤月乃さん
2025年07月24日 12時00分更新
丸の内LOVEWalker総編集長の玉置泰紀が、丸の内エリアのキーパーソンに会いに行き、現在のプロジェクトや取り組みなどのエピソードを聞いていく本連載。第25回は大手町ビルで養蜂活動を行っている「丸の内ハニープロジェクト」の伊藤月乃さんにお話を伺った。
「都心で養蜂する」ことのメリットとは
丸の内エリアのビル屋上で養蜂活動が行われている。その名も「丸の内ハニープロジェクト」。後述するが拠点を何度か変えながら活動を継続し、今年は大手町ビルの屋上で養蜂活動が行われている。
――「丸の内ハニープロジェクト」はどんなきっかけでスタートしたんでしょうか?
伊藤「大丸有エリアのコミュニティ形成の場として、エリアの企業やまちづくり団体を中心に、2016年7月より『丸の内ハニープロジェクト実行委員会』が組成されました。
週に一度の採蜜では、養蜂のプロとして銀座ミツバチプロジェクトさんにご指導いただきながら、一般の方にもご参加いただいています。参加してくださる方は初めての方が多いのですが、参加前には“蜂は怖い”という印象を持たれている方がほとんどの中、実際に触れてみると『怖くないんだ』『こんなに環境に貢献している生き物なんだ』という感想を持ってくださってうれしいですね。
こうして活動してみると、都心で養蜂を行うこと自体がまちづくり活動としてかなり有効なものだと思うようになりました。採蜜の場が人と人をつなぐ場になりますし、数少ない丸の内産の食品を作ることができるのが魅力だなと思いました」
――プロジェクトは2016年から始まっていますよね。最初はどこのビルから養蜂を始めたんですか?
伊藤「丸ビルから始まりました。風などの関係で、巣箱の設置はあまり高い場所では難しいですがビルの9階、10階ぐらいまでの高さだと問題なく実施できます。ビルの屋上工事が行われる期間は養蜂ができないので、これまでに日本工業倶楽部、新東京ビル、新有楽町ビル、大手町ビル、と何度か場所を変えながら養蜂しています」
高い位置に巣箱を置いても、風が強くて作業が難しい環境では養蜂はできない。巣箱が設置できる高さ、一般の人があまり集まらない場所など、さまざまな条件の下、丸の内で養蜂をしているというわけだ。
ミツバチは怖くない!
伊藤さんが養蜂に携わるようになって1年3ヵ月。最初はミツバチの生態にも詳しくなく、そもそも「都会で本当にハチミツが採れるんだろうか」と思っていたのだという。
伊藤「『ミツバチって刺すんでしょ?』とイメージしている方が多いので、巣箱を設置してからの周りの方の理解が必要だなと思っています。人間が攻撃しなければミツバチは刺したりしてこないんですよね。なので、巣箱を設置した際に周りへちゃんと説明して理解していただくということが必要だなと思っています」
実際に大手町ビル屋上にある巣箱を拝見させてもらったが、伊藤さんの話の通り、こちらから大きく動かなければ蜂も静かなもので実に平和。都心のオフィスビルに囲まれた空間が全く違う世界に感じられて、感動的だった。
――採蜜は週に一度とのことですが、思っていたよりも頻度が高くて驚きました。先ほど“一般の方と一緒に採蜜している”というお話がありましたが、参加された方の反応はいかがですか?
伊藤「今年は巣箱を増やしたこともあって、春は1週間に一度、夏は2週間に一度くらいのペースで行っています。丸の内エリアの養蜂は春から夏の間だけなんです。3月に巣箱を設置して、8月末頃に撤収するというサイクルで、その後は銀座に巣箱を移動して越冬し、また3月になると丸の内に戻ってきます。
採蜜活動では、主に丸の内エリアに勤めている方が参加されていますね。まず『こんな都心でハチミツが採れるの?』とびっくりする方が多いです。あとはミツバチの生態や働きに感心する方もいらっしゃいますね。何回か参加していただくと味の変化なども顕著にわかったりするので、そこでも驚いていただけます」
――そんなに味の変化があるんですか!? 確かにお店などでもいろいろな花のハチミツが売られていますが…。
伊藤「そうですね、味の変化は花の種類によるので、季節によっても全然違う味になります。大手町ビルからだと、蜂の活動エリアである半径2キロの中に皇居や日比谷公園がすっぽり収まるんです。私もプロジェクトに携わって気付きましたが、丸の内は都会でありながら、意外とハチミツの味に違いが出るほど花の種類が多いエリアなんだと思いますね」
丸の内産のハチミツで、丸の内産のスイーツを
現在40~50万匹のミツバチを養蜂している丸の内ハニープロジェクト。昨年の採蜜量が500kg、今年は700kgに届きそうだという。
――日本のハチミツ自給率が7%ぐらいということなので、ますます丸の内で採れたハチミツは貴重ですね! 採れたハチミツ「丸の内ハニー」は、エリアの飲食店・ホテルなどで活用されているんですよね。
伊藤「現在、常設で丸の内ハニーを味わっていただける店舗は8店舗あります。また、イベントなどで提供されることもありますので、ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいですね。
さらに、秋に向けて丸の内ハニーを使った新メニューを準備していただいている店舗もあります」
――それは素晴らしい! このプロジェクトでは、採取した花のDNA調査もされているとお聞きしました。蜂蜜を採取するだけでなく、学術調査も行っているとはびっくりです。
伊藤「蜂は花の蜜と一緒に花粉を運んでくるので、花粉のDNAを分析することで、どんな花から蜜を集めてくるのかがわかるんです。先ほど季節や花によってハチミツの味が変わるというお話をしましたが、実はハチミツの味って、毎週変わっているんです。
例えば、4月のハチミツは桜がメインで、夏が近づいてくると樹木の花やクローバーの割合が多くなっていきます。6月以降は蜜源植物が減ってしまうので、ミツバチや蝶など、蜜を集めてまわる生き物たちにとっては苦しい時期になります。そこでこのプロジェクトでは、彼らの役に立つように、蜜を集めやすい植物をハンギングバスケットやプランターに植えて、街に設置する活動も試験的に行っています」
――花粉のDNA分析から、このエリアにどんな花があって、どういう季節、タイミングで蜜を集めてくるのかがわかるというのはすごいですね。私はエリアの特性、面白さのレイヤーの研究を「メタ観光」という考え方で取り組んでいるのですが、花粉のDNAから見えてくるエリアの植生は得難い情報で、この丸の内を中心するエリアの魅力が見えてくると思います。
周りを見回してみると丸の内仲通りの街路灯にもハンギングバスケットが設置されていて、季節ごとにさまざまな花が植えられている。景観を意識しているのかと思っていたが、ミツバチのためでもあったということだ。
――プランターなどを設置する活動は、大手町・丸の内・有楽町エリアのまちづくりを推進する「エコッツェリア協会」と連携しているんですよね。エコッツェリア協会についても教えてください。
伊藤「エコッツェリア協会は、サステイナブルな社会づくりに向け、ビジネス交流施設『3×3Lab Future』を拠点に、さまざまな方々が交流するための企画やプロジェクトを推進しているまちづくり団体です。『丸の内ハニープロジェクト実行委員会』の事務局でもあり、花粉DNA調査で得た結果を街に活かそうと共に取り組んでいます」
採蜜を通して人と人がつながり新たなコミュニティが生まれる
「丸の内ハニープロジェクト」は今年で10年目を迎える。年を重ねるごとに参加者たちが顔見知りになり、その流れで企業に出向いて講演したり、飲食店とつながったりと、企業同士のコラボレーションも生まれているという。もはやハチミツだけの関係ではなく、社会活動が生まれる場でもあるのだ。
――これからの「丸の内ハニープロジェクト」の展望を教えてください!
伊藤「今年の秋ぐらいに、10周年記念イベントを開催できたらと思っています。ハチミツを使ったグルメが楽しめるイベントにして、これまで参加していただいた皆さんへの感謝と、これからも一緒にやっていきましょうという気持ちを伝えたいですね」
――伊藤さんにとって、ハニープロジェクトとはなんですか?
伊藤「そうですね、一つの“メディア、媒体”でしょうか。プロジェクトが、このエリアでのイベントや植栽などいろいろな方面につながっているんですよね。養蜂活動が人と人をつなぐ場となり、新しいものを生み出す可能性を秘めているのが『丸の内ハニープロジェクト』なんじゃないかなと思いました」
――最後に、丸の内エリアで好きな場所を教えてください。
私は丸の内で働き始めて1年3ヶ月になります。実際に丸の内で働くまでは、どこか緊張感を持っていたんです。“丸の内OL”という言葉から連想されるような、ステレオタイプなイメージを持っていたこともあって、敷居が高くひとつのブランドとして確立している場所なんだろうなと考えていたんです。実際に働いてみると、格式が保たれているのはもちろんですが、エリア自体に緑がたくさんあるので意外と開放感がありました。また、丸の内ハニープロジェクト他、さまざまな企画で、丸の内に関わる人とお話する中で、人と人との交流や、新しい取組も行われているまちなんだとイメージが変わっていきました」
歴史のあるビルから最先端のビルまでさまざまな建築が並び、日本屈指のオフィス街である丸の内。そんな場所にも緑がしっかり息づいていることを教えてくれるミツバチ。そして、採れたハチミツが丸の内の飲食店で実際に使われていることに感心させられた。
また、地域の人たちと活動する伊藤さんが活き活きとしていたことも印象的だ。人々をアクティブにさせてくれるところも丸の内エリアの魅力の一つ。改めて思うが、この街の面白さはとどまるところを知らないのだ。
伊藤月乃(いとう・つきの)
●1994年、静岡県生まれ。官公庁、大学での勤務を経て、2024年より三菱地所株式会社/一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会(エコッツェリア協会)にて勤務。環境と共生するまちづくりに向けて、イベント・セミナー等の企画・運営に従事。
聞き手=玉置泰紀(たまき・やすのり)
●1961年生まれ、大阪府出身。株式会社角川アスキー総合研究所・丸の内LOVEWalker総編集長。国際大学GLOCOM客員研究員。一般社団法人メタ観光推進機構理事。京都市埋蔵文化財研究所理事。産経新聞~福武書店~角川4誌編集長。
■関連サイト
丸の内ハニープロジェクト
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう