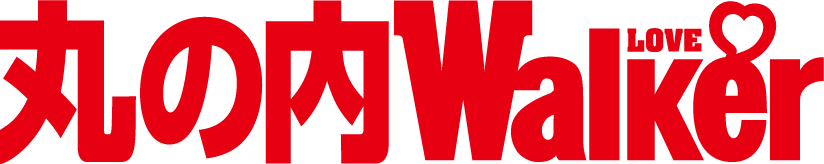「東京駅丸の内駅舎」に使われてるレンガ、何個か知ってますか? 職人延べ75万人で作り上げた世界最先端のレトロモダン建築の歴史に迫る!!
2025年01月31日 12時00分更新
高層ビルや歴史的建造物など、丸の内の建築群を現場のレポートを交えながら紹介する連載「丸の内建築ツアー」。今回は、丸の内を日本最大のオフィス街へと成長させる原動力となった「東京駅丸の内駅舎」を構想から計画、建設、戦災の焼失からの復興、戦後の姿に戻す復原と、タイムスリップしながら紹介します。
中央停車場の構想と設計
1854年に日本が開国し、それから20年も経たない1872年10月14日に日本初の鉄道が新橋~横浜間に開業します。その後、1883年7月28日に東北方面の上野~熊谷間が開通、1889年には東海道本線が神戸まで全通、1891年には東北本線も青森まで全通します。そのような流れの中、新橋までで止まっている東海道本線と上野までで止まっている東北本線を高架鉄道によって結び、途中の鍜治橋付近に「中央停車場」を設ける構想が浮上。1896年に第9回帝国議会でこの案が可決されました。
そして同時期に、明治政府による皇居警備の必要性が薄れてきたことから、皇居の目の前に広がっていた陸軍兵営を移転したことを契機に、陸軍兵営跡地の丸の内一帯が1890年に三菱財閥へ払い下げられました。当時は三菱ヶ原と呼ばれ、草が生い茂る一面の野原にビジネスセンターを構築する計画と、中央停車場を皇居の東側一帯の丸の内に置くことが決定します。
1896年に帝国議会で可決された後、高架線や中央停車場の工事を担当する新永間建築事務所が発足。当時、ヨーロッパで唯一市街地を貫通する高架鉄道を有していたドイツ・ベルリンを参考とするため、ドイツから鉄道・建築技術者の「フランツ・バルツァー」を招き、1898年に着任、中央停車場を含めた設計に着手します。その頃、丸の内では1894年に第1号館(三菱一号館)が竣工、1895年には現在の明治生命館のある場所に第2号館が竣工し、徐々に一丁倫敦(いっちょうロンドン)と呼ばれる煉瓦造のオフィス街が形成され始めていました。
バルツァーによる中央停車場の設計では、駅舎は切石を用いた煉瓦造の建物に入母屋破風や唐破風を採用した瓦葺屋根を載せた分棟型の和風建築のデザインとなっていました。また、駅の動線面では、南側に入口、北側に出口、中央に皇室用乗降口と都市部の電車専用出口が配置された現在の駅舎に通じるものでした。なお、この外観デザインは当時、欧米列強に肩を並べようとしていた日本では受け入れられなかったほか、後に設計を行った辰野金吾からも「赤毛の島田髷」と酷評されることになります。
そのようなことから、1903年にバルツァーが帰国した後、中央停車場の駅舎は再設計が行われることになり、当時、近代建築の権威であった建築家「辰野金吾」によって設計されることになりました。最初の設計案は1904年にできあがりましたが、予算が42万円で全長300m近い建物配置であったため、南北に出入口、中央に皇室専用口というバルツァーの案を採用しつつも、出入口のみ3階建てで他は1~2階建てで繋ぐという規模感でした。
その後、1905年に日露戦争で日本が勝利したことや鉄道国有化によって、予算が3.8倍の250万円に増額され、駅舎の規模も総3階建てに拡大、1910年に設計が完了します。
東京駅丸の内駅舎の建設と意匠
建築家・辰野金吾によって設計された中央停車場は、まずは中央停車場以南を複々線の高架橋として1900年に着工、1902年に中央停車場部分の高架橋の着工、1908年3月に駅舎の基礎工事に着手します。高架橋のみ先行して部分完成し、1910年に仮駅であった呉服橋駅(現在の東京駅の北側)まで山手線が開業、東京駅が完成するまでの間は東京駅を通過して仮駅の呉服橋駅に発着していました。
建設工事は、駅舎基礎工事を杉井組、鉄骨工事を石川島造船所、建築工事を大林組、内装工事を清水組、新設される高架橋を杉井組・鹿島組・大倉組で行われ、用いられた鉄骨は、1901年に操業を開始した直後の八幡製鉄所で製造された国産のものが半数以上を占めていたことから、この頃から日本国内の技術や人のみで近代建築を建設できるようになってきたことが伺えます。
駅舎の構造面では、基礎杭に松杭11,050本を60cm間隔で打込んだ上に厚さ1.2mのコンクリートを打設した堅固なものとなり、建物の荷重を煉瓦の壁だけでなく、鉄骨の柱や梁でも支える構造となっています。当時は木材を用いることも多かった各階の床も鉄筋コンクリートによるスラブを採用したことで、非常に堅牢な構造となり、のちの1923年に発生した関東大震災でも駅舎には全く被害が生じませんでした。
最終的に用いられた鉄骨の総重量は約3,140トン、煉瓦は構造用煉瓦約833万個、動員した職人の延べ人数は約75万人にのぼり、1914年12月15日に竣工、駅名も諸外国の例に則り「中央駅」とすべきという意見がありつつも、1914年12月5日に「東京駅」に決まり、1914年12月20日に開業しました。
竣工当時の規模は、地上3階、地下1階、延床面積約23,900㎡、高さ34.8m、全長約335mとなり、外観デザインは、屋根は銅板葺とスレート葺のものとなっており、南北には円形のドーム屋根を配置、外壁は赤煉瓦に白い花崗岩を帯状に配置した「辰野式フリー・クラシック」と称される様式の壮麗な駅舎となりました。また、内観も南北のドーム天井には鷲の像や十二支をモチーフにしたレリーフなどの彫刻や装飾が施されていました。
1階に駅機能や貴賓室、2~3階は南側にホテル「東京ステーションホテル」、北側に鉄道員の事務所が配置され、開業当時から戦後の1948年までは南口が乗車専用口、北口が降車専用口と分けられており、中央は皇室口、皇室口の北側に電車降車口が設けられています。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう