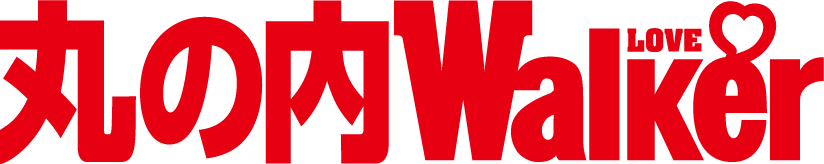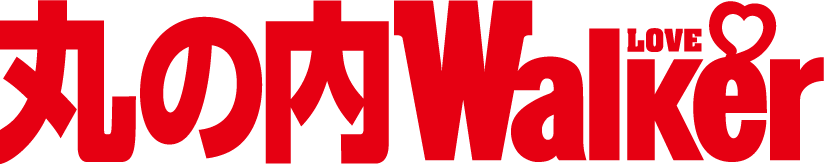「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025」このコンサートが気になる! クラシック好きがあなたに教えるおすすめ演目とトリビア
2025年04月30日 12時00分更新

東京国際フォーラムを中心に、東京・丸の内エリアで開催されるクラシック音楽の祭典『ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025』(以下、LFJ)。5月3日(土・祝)から5日(月・祝)までの3日間、無料公演も含めると90以上の公演が楽しめる音楽祭です。
そんなLFJの中でも注目すべきコンサートを、「ちょっとしたトリビアを交えながら紹介してくれ」という、シンプルながら地味な無茶振りを上司から頂戴してしまいました。
これもひとえに筆者へのクラシック音楽に対する情熱が認められた証だとポジティブに考えることにして、さっそく注目コンサートを紹介していきましょう。
ベートーヴェンの「定番」と
「なんでこのタイトル?」という謎の曲を聴く
〈ベートーヴェンに横溢するファンタジーと覇気 inウィーン〉
•公演番号:121
•時間: 5月3日 (土・祝) 10:00〜10:50
•場所:ホールC
•テーマ/都市:ウィーン
•演奏曲目:
・ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24「春」
・ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 op.70-1「精霊」
クラシックの作曲家の中でも、もしかしたら一番有名かもしれないベートーヴェン。彼ほどの才能を持つ人でも一から十まで独学だったわけではなく、生涯の中で何度か作曲家に師事したことがあります。たとえば、当時からすでに人気の作曲家だったハイドンにも教わっていたことも(ベートーヴェンの日記にレッスン料の記録が残っているほどです)。
とはいえ、何しろ売れっ子だったハイドン。多忙ゆえにあまりレッスンの時間は取ってもらえなかったらしく、その期間、ベートーヴェンはこっそり他の作曲家に学んでいたようですが……。

ベートーヴェンは、実はモーツァルトにも弟子入りしようとしていたとか。実際に「会ったことがあるかどうか」は歴史家の中でも意見が分かれています
そんな時期の傑作であるヴァイオリンソナタ第5番は、ベートーヴェンの……というのみならず、ヴァイオリンソナタ(ざっくり、ピアノとヴァイオリンの二重奏だと思ってくれれば問題ありません)の傑作に数えられています。最初から最後まで、朗らかで優しい旋律があふれんばかり。
一方のピアノ三重奏曲第5番も、知名度では劣るかもしれませんが、ウィーンで活躍していたベートーヴェンが書いた傑作の一つです。ピアノ、ヴァイオリン、チェロというクラシック音楽らしい組み合わせの妙が楽しめます。
ちなみに、ピアノ三重奏曲第5番の愛称の「精霊」ですが、むしろ「幽霊」という呼称のほうが知られているかもしれません。ドイツ語だと「Geistertrio」と呼ばれています。精霊トリオ、幽霊トリオ、みたいなニュアンスですかね。ピアノ三重奏曲を「ピアノトリオ」と呼ぶので、それにちなんだもの。
しかし、そのような名前で呼ばれるようになった理由は、はっきりしないのだそう。曲調としても活気あふれるもので、不穏な感じもまったくないんですよね。いや、ほんとうに、なんでそう呼ばれるようになったのでしょう……? このコンサートを聴いて、みなさんにその謎を解き明かしてみてほしいものです。
文化の中心、パリで生まれた名曲たち
今年のラ・フォル・ジュルネのテーマにぴったり
•公演番号:115
•時間: 5月3日 (土・祝) 20:30〜21:20
•場所:ホールA:エッフェル
•テーマ/都市:パリ
•演奏曲目:
・ラヴェル:ツィガーヌ
・デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」
・ドビュッシー:海-管弦楽のための3つの交響的素描
芸術の都、パリ。クラシック音楽の歴史でも、多くの作曲家を輩出した重要な場所です。20世紀初頭においても、今でも知られる作曲家が多数活躍していました。
たとえば、ドビュッシーの「海」。曲自体も彼の代表作といってよいぐらいの傑作ですが、初版のオーケストラスコアの表紙デザインに、ドビュッシー自身の希望により葛飾北斎の「冨嶽三十六景」が使われたのは有名な話。当時のフランスにおける日本美術ブーム(ジャポニスム)がうかがえるエピソードです。

ドビュッシーは気難しい性格だったそうですが、音楽を聴いて「確かに気難しそう!」と思う人は少ないかも?
あるいは、ラヴェル。活躍した場所も時代も近いことからドビュッシーと一括りにされることもありますが、古典的な形式や自身のルーツ(バスク地方の生まれでした)を強く意識した彼のスタイルは、ドビュッシーとはかなり異なるものです。
「ツィガーヌ」は、「ロマ」を意味するフランス語。ハンガリーの地域性を持ったロマの音楽として構想されており、旋律やリズムで民族性を強く表現しています。さまざまな時代や場所をつなぐような名曲。
デュカスの「魔法使いの弟子」はご存知でしょうか? 魔法使いの見習い(弟子)が魔法でほうきに水くみをさせるのですが、それを止める魔法を教わっていなかったので大パニックになる……という詩から生み出された作品。
この作品は、ウォルト・ディズニーのアニメ映画「ファンタジア」に使用されたことで有名になりました。ミッキーマウスが、ほうきを止められずに大慌てするという内容で、基になった詩に忠実なストーリーです。
さまざまな国の文化に影響を受け、そして世界中に影響を与えた、フランス生まれの名曲たち。それらを耳にすることで、我々は時空も国境も超えた精神的な旅に出ることができるわけです。今年のラ・フォル・ジュルネのテーマは、「Mémoires(メモワール) ―音楽の時空旅行」。まさに、そのテーマにぴったりなコンサートでしょう。
ヘンデルはドイツで生まれたけど
ロンドンですごい人気だったって知ってた?
•公演番号:213
•時間:5月4日 (日・祝) 15:30〜16:15
•場所:ホールA
•テーマ/都市:ロンドン
•演奏曲目:
・ヘンデル:「水上の音楽」から 抜粋
・ヘンデル:ジョージ2世の戴冠式アンセム第1番「司祭ザドク」 HWV258
・オラトリオ「メサイア」から 抜粋
今も昔も、「自国を飛び出し、海外でも大ヒットした芸術家」はいるものです。クラシックでいえば、ヘンデルはその1人といってよいでしょう。彼はドイツ出身なのですが、まず、イタリア(ヴェネツィア)で人気を博しました。
そして、次に渡ったイギリスのロンドンでも数々のオペラがヒット。多くの作品がイギリスで愛されるようになり、ヘンデルはそのうちにドイツに戻らなくなり、現地に帰化したほどでした。「ハレルヤ・コーラス」で有名すぎる「メサイア」もロンドンで書かれたものです。

「ヘンデル」は英語読みでは「ハンドル」になりますが、現地でもドイツ語読みの「ヘンデル」と発音されていたそう
このコンサートで演奏される「水上の音楽」も、イギリス王ジョージ1世の舟遊びの“ために”作曲されたもの……というエピソードがありますが、今の研究によるとどうもそうではないようで。
そんなエピソードが生まれたのも、先述したように「ドイツに戻らず」活躍したヘンデルの経歴に理由がありそうです。
ドイツのハノーファー選帝侯の宮廷楽長に就いていたにも関わらず、外遊先のロンドンに予定を超過して定住していたヘンデル。ところがよりによって、そのハノーファー選帝侯がイギリス王として迎えられることになります。それが、他ならぬジョージ1世。いわゆる「ハノーヴァー朝」の始まりです。
勝手に留守にしていた場所を治めていた人が、自分が大活躍している国の王になったとあれば、ヘンデルからすれば気まずくなりそうなもの。そんなところから、ジョージ1世の舟遊びの“ために”作曲したという伝説が生まれたのかもしれない。しかし、実のところ、2人の関係はずっと良好だったそうな……。
ともかく、国王とも仲が良く、ロンドンっ子たちにも愛されたヘンデル。ジョージ2世の戴冠式アンセム第1番「司祭ザドク」も、伝統的に戴冠式で使われるのはもちろん、サッカー・UEFAチャンピオンズリーグの入場曲の原曲になっています。それほど、イギリスの歴史に密着している作曲家なのです。
このコンサートで、英国民を魅了したヘンデルの典雅な美しさを堪能してみては?
クラシックの歴史にその名を残すシューマン夫妻
2人のピアノ協奏曲をセットで楽しめる!
•公演番号:314
•時間:5月5日 (月・祝) 18:15〜19:10
•場所:ホールA
•テーマ/都市:ライプツィヒ
•演奏曲目:
・ローベルト・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 op.5
・クララ・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 op.7
クラシックの歴史の中でも、夫妻揃って優れた作曲家という例は珍しい。一般的にクラシック音楽で「シューマン」といえばローベルト・シューマンですが、妻のクララ・シューマンも卓越した技術を持つピアニストであり、そして作曲家でした。
このコンサートは、そんな夫妻のピアノ協奏曲を続けてどうぞ、というものになっています。

音楽評論家としても活躍したシューマン。当時の作曲家たちとも多くの交友を持っていました
まず、夫であるローベルト・シューマンの「ピアノ協奏曲 イ短調」はとても有名。古今のピアノ協奏曲の中でも演奏される機会は多く、筆者より年上世代だと「ウルトラセブン」でとても印象的に使われたことで知っているという人が多い曲です。
そのあとに、クララのピアノ協奏曲もあわせて聴けるというのがおもしろい。クラシックが好きでも、ローベルトのほうは聴いたことがあるけど、クララのピアノ協奏曲は……という人もいるはず。そういう人にはうってつけのコンサートでしょう。ちなみに、この曲の初演で指揮したのはあのメンデルスゾーンだというトリビアもあります。
夫妻のピアノ協奏曲の“共演”が聴ける機会というのはとてもめずらしい。クラシックの祭典らしい面白い企画です。
ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025は、およそ45分の公演を並べることで、朝から晩までさまざまなプログラムをハシゴできるようになっています。誰もが知る名曲から、愛好家でもなかなか聴かないような曲まで、バリエーションも豊富。
今年のテーマは、「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」。音楽の発展に多大な貢献をした都市とその時代にスポットライトを当てます。本記事で紹介したコンサートも、「ウィーン時代のベートーヴェン」「20世紀初頭のパリ」など、時代や都市に注目したテーマがあるわけです。それを意識して聴くと、より一層楽しめるはず。
すでに売り切れてしまった公演もありますが、ここでご紹介したものを含めてまだまだチケット購入可能なステージはたくさんあります。気になったら、公式サイトをチェックしてみてください。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう