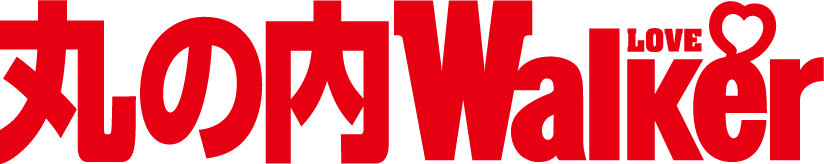「讃州讃岐は高松様の城が見えます波の上」とも謳われた
日本有数の巨大な“海城”である高松城は、鯛が泳ぐほど美しい堀を持つ西国支配の要となった名城だった!
2025年05月08日 12時00分更新
日本三大海城の一つ、高松城は
近世城郭の海城としては最初で最大の例
今回、探検してみた高松城(香川県高松市)はいわゆる「海城」である。防衛のため、それ以上に水運を押さえるため、海に面して築かれ、海水を堀に用い、舟入や船着場を設置している城のことをいう。
中でも、高松城(讃岐国)、今治城(伊予国)、中津城(豊前国)は日本三大海城(三大水城とも)と呼ばれている。この三つの城の特徴は、海水を堀に引き込んだ水城としての独特な構造を持ち、軍事・戦略的に重要な役割を果たした城と言うことが言える。
中でも、高松城は近世城郭の海城としては最初で最大の例で、「讃州讃岐は高松様の城が見えます波の上」ともうたわれた。
かつては、3重に堀がめぐらされ、城壁は瀬戸内海に直接面し、外堀・中堀・内堀のすべてに海水が引き込まれて、あたかも波の上に浮いているように見えたという。潮の満ち引きで水位を調整することで、敵の侵入を阻止するつくりになっていた。
元は、豊臣秀吉に讃岐国に封じられた生駒氏が築城した城だったが、江戸時代に入って、水戸黄門として知られる徳川光圀の兄である松平頼重が3代将軍・徳川家光に、西国諸藩を監視する要として讃岐国に封じられ、徳川幕府の重要拠点として増改築して今に残る形になった。
3年に一度の世界的な芸術祭「瀬戸内国際芸術祭」は2025年で6回目だが、筆者は4回参加していて、高松市を拠点に高松港から瀬戸内海の島を見て回っている。2025年も取材に来たが、今回は念願の高松城をしっかり歩いてみた。
高松城は別名、玉藻城とも呼ばれ、城跡自体が高松市立玉藻公園になっている。「玉藻(たまも)」は、古来の日本語で「美しい海藻」や「水草」を意味し、和歌や文学で海の美しさや波に揺れる情景を象徴する言葉として使われてきた。
和歌や連歌では、「玉藻」は海の清らかさや優美さを表現する枕詞として使われ、『万葉集』や『源氏物語』では海辺の風情を彩る言葉として用いられ、柿本人麻呂が万葉集で讃岐の国の枕詞に「玉藻よし」と呼んだ事に因んだという。
「玉藻城」の名称は、江戸時代中期以降に文献や地元で定着したとされ、高松松平家初代藩主の頼重の時代(17世紀中盤)に始まり、松平氏の統治下で広まったと思われる。披雲閣での茶会や和歌の会が、名称の普及に寄与したかもしれない。
上の写真には、城郭を思わせる建物が二つ見える。左側は重要文化財の月見櫓、右側は「時鐘楼」と言って、高松松平家初代藩主の松平賴重が承応二年(1653年)、大判30枚を使って大阪で作った報時鐘が納められている。
当時は外濠の西南隅の内側にあったが、その後、一番町に移転。明治33年秋には四番丁小学校へ、その後、松平家に返納され昭和8年高松城跡に設置。昭和30年、城跡は高松市所有となり、昭和55年に市制施行90周年を記念して現在の位置に模擬櫓を建設して保存されている。
堀の水は港湾地区の埋め立てで直接海に面することはなくなったが、今も海水が引き込まれている。透明度が高いこともあり、スズキやボラはもちろん、タイなどが泳ぐ姿も見られる。
水門は、海とつながる濠の潮の干満による水位調整で活躍している。タイやヒラメが見られる濠では、タイのエサやり体験「鯛願成就(たいがんじょうじゅ)」や和船「玉藻丸」の内濠遊覧「城舟体験」(3~11月)を楽しめる。
・乗船料金:大人(高校生以上)500円、小人(5歳以上)300円 *5歳未満は乗船できない。
・乗船時間:10:00から15:30まで30分毎。11:30〜13:30は船は出ない。 *12月から2月は運休する
●高松城の成り立ち
高松城は、豊臣秀吉の四国制圧後、天正15年(1587年)に讃岐一国の領主となった生駒親正(いこま ちかまさ)によって、翌年、現在の高松市にあった香東郡野原庄と呼ばれる港町に築かれた。縄張りは築城の名手、黒田孝高(如水)とも細川忠興とも言われている。
豊臣秀吉は天正13年(1585年)、長宗我部元親を降伏させ、四国を豊臣政権の支配下に置いた。讃岐国は、秀吉の家臣である仙石秀久、尾藤知宣などを経て最終的に生駒親正に与えられ、讃岐一国(約17万石)の領主に任命された。
生駒親正(1526年〜1603年)は、秀吉の側近で、尾張国(愛知県)出身の中級武将。秀吉の天下統一に貢献し、四国統治の要として讃岐を任された。親正は、讃岐の統治基盤を固めるため、新たな居城の建設を計画。高松城の築城は、この目的を果たす中心的なプロジェクトだった。
地理的には、瀬戸内海の海上交通の要衝であり、対岸の備前(岡山)や淡路島との交易・軍事ルートを押さえる戦略的立地だった。周辺には、香東川や新川などの河川があり、水運や灌漑に適していた。
初期の城は、本丸、二の丸、三の丸、堀、石垣、天守閣を備えた平山城で、海水を堀に引き込む水城として設計された。
●高松松平家初代藩主の松平賴重による高松城の増改築
生駒親正の築城からおよそ50年後の寛永19年(1642年)、松平頼重(1622年〜1695年)が高松藩初代藩主に就任し、高松城の増改築を行った。頼重の整備は、生駒氏の初期構造を強化し、「玉藻城」の美観と防御力を高めた。
生駒氏の統治時代に財政難や内紛(生駒騒動)が続いたため、幕府は徳川一門の松平頼重を派遣し、藩の安定を図ったと思われる。頼重は徳川家との血縁を背景に、高松城を幕府の西国支配の拠点として強化する役割を担った。
頼重は、徳川家康の孫で、水戸徳川家の祖・徳川頼房の嫡男であり、水戸徳川家を継いだ徳川光圀(いわゆる「水戸黄門」として知られる)の兄にあたる。玉川上水より9年早い時期の寛永21年(1644年)、現代まで水不足で知られる高松城下に、配水枡・配水管を地中埋設し、日本で初めてといわれる本格的な上水道を敷設している。
武者小路千家の祖、一翁宗守を藩の茶道指南役に据えるなど、文化面でも大きく寄与し、和歌もたしなんだことで知られ、茶会や和歌の会も多く開かれた。
頼重の就任時、城は基本的な構造が整っていたものの、老朽化や防御力の不足が課題だった。頼重は高松城を藩の中心として強化するため、増改築や整備を積極的に進めた。
高松城は瀬戸内海に面し、西国大名を監視する戦略的要衝であり、幕府の西国支配を強化するため、防御力を高めなくてはならなかった。また、徳川一門の大名として、城の規模や壮麗さで藩の権威を示す必要もあった。
さらに監視や攻撃の拠点である櫓の数が不足していたことから、艮櫓(うしとらやぐら)を、北東の方角に新たに建設。また、北の丸には渡櫓・水手御門鹿櫓などを建設するほか、これらを多聞櫓でつなぎ海側からの攻撃に備えた。さらに、月見櫓を海に面した場所に建設、防御だけでなく、風光明媚な櫓として、城の挌を上げることにも寄与した。
堀の浚渫(しゅんせつ)作業も行われたと思われ、海水の流れを改善し、魚類の生息環境も整え、食料供給の役割も強化した。石垣の補修と増築も行われ、特に北の丸と東の丸を新たに造り、海側に拡張し、石垣を整備することで実態としては波浪や敵の攻撃に耐えられるようにした。
また、藩主の政庁や家臣の詰所として、城内の施設が不足していたことから、藩主の公邸や政務の場である披雲閣(ひうんかく。書院造の建物)を整備した(現存は後世のものだが、基礎は頼重時代に整備)。家臣団の詰所や武器庫を増設し、桜の馬場の区画を整理し、効率的な運用を可能にした。庭園も整備して、藩主や来客の接待用に日本庭園を拡張した(現在の玉藻公園の原型)。
こうして、城が単なる軍事拠点ではなく、藩の政治・文化の中心としての役割を強化したのだ。
7件の重要文化財の指定を受けた貴重な近世城郭の
代表的な海城を歩いて回ってみた
頼重の退任後は、子の頼常が藩主になり、頼重の整備した高松城は、以後松平氏の居城として機能し続けた。頼常は実は徳川光圀の子であり、逆に、水戸徳川家は、光圀が頼重の子である綱條(つなえだ)を藩主に迎えており、その後も両家は養子縁組を繰り返した。
松平氏の治世は11代228年間にわたり、高松は城下町として栄えた。明治維新後は、明治3年(1870年)に廃城伺を提出して受理され、明治4年(1871年)の廃藩置県後、高松城は軍や政府の施設として使用され、天守や披雲閣など、老朽化もあり、多くの建物が解体された。明治23年(1890年)に、城郭の一部が松平家に払い下げになり、さらに、公益財団法人松平公益会に継承され、昭和29年(1954年)に高松市が譲り受けた。
そして、昭和30年(1955年)5月5日に、高松市立玉藻公園として一般に公開された。現在の玉藻公園の面積は7万9587m2(およそ2万4千坪)で、往時の城域66万平方m2(およそ20万坪)の8分の1の広さだ。
現在も、頼重時代に築かれた櫓や石垣の一部が残っていて、艮櫓、月見櫓、水手御門、渡櫓などが重要文化財に指定されている。頼重の整備した堀や庭園は観光資源として今も親しまれている。
●披雲閣(ひうんかく)
江戸時代の松平氏時代には披雲閣と呼ばれる現在の2倍の規模にあたる三の丸御殿があったが、明治時代に老朽化により取り壊された。現在の披雲閣は、大正6年(1917年)に松平家高松別邸として、当時の金額で15万円と3年の歳月をかけて建設されたもの。
142畳の大書院をはじめ、外に見える植物から名付けられた槇の間、松の間、蘇鉄の間などの部屋があり、波の間には、昭和天皇・皇后両陛下が宿泊された。
太平洋戦争後は、アメリカ軍に接収されるなどしたが、高松市が譲り受けてからは、貸会場として市民に利用されている。また、披雲閣の再建に合わせて内苑御庭という枯山水の庭が作庭された。披雲閣は平成24年(2012年)7月9日、披雲閣の本館、本館付倉庫、倉庫の3棟が国の重要文化財に、庭園(披雲閣庭園)は平成25年(2013年)10月17日に国の名勝に指定された。
●艮櫓(うしとらやぐら)
昭和22年(1947年)、旧国宝(現在の重要文化財)に指定された。元々は東の丸の北東の隅(現在の県民ホール敷地内)にあったが、昭和40年(1965年)に旧国鉄から高松市が譲り受けて、2年の歳月をかけて旧太鼓櫓跡に移築をした。完成は延宝5年(1677年)といわれ、月見櫓と同時期に作られた。三重三階・入母屋造・本瓦葺で形は月見櫓と似ているが、初重に大きな千鳥破風があるのが特徴。
●旭橋と旭門(大手)、桝形石垣
旭門は寛文11年(1671年)ごろ、松平家が行った城の改修で設けられた新しい大手門。門に対して斜めにかけられた旭橋は敵に対し横方向から攻撃できる構造になっている。
欄干の親柱には松平家12代当主の頼壽(よりなが)伯爵の「旭橋」と昭子夫人の「あさひはし」の文字が見られる。旭門を入ったところの枡形石垣は攻め込んだ敵を包囲するためのもの。
●桜御門
三の丸入口の櫓門で、昭和20年(1945年)の米軍による高松空襲で焼失したが、令和4年(2022年)、77年ぶりに復元され蘇った。復元には古写真と礎石に残る柱跡などが有力な手掛かりになった。門の手前には高松空襲で焼けた桜御門の石垣石石材が展示されている。
●天守台
寛文10年(1670年)に松平家が改築した天守は三重五階(三重四階+地下一階)、唐造り(南蛮造り)で四国最大の規模をほこっていた。天守は明治17年(1884年)に老朽化を理由に取り壊され、天守台のみ残っている。平成17年(2005年)から平成25年(2013年)にかけて行われた天守台の修復工事で地下一階部分から58個の礎石が当時のまま見つかった。
天守は、最下重が萩城や熊本城の天守のように天守台より出張り、最上重が小倉城や岩国城の天守のように「唐造り」であった。その様子は、解体される以前に写真におさめられ、また明治17年(1884年)にイギリスの週刊新聞「ザ・グラフィック」でイギリス人のヘンリー・ギルマールの絵によって紹介されている。平成17年(2005年)には、英国ケンブリッジ大学図書館で天守の鮮明な写真(明治15年撮影)が発見された。
地元では、高松城の天守再現計画は1980年代から議論され、1670年に松平頼重が改築した四国最大の南蛮造り天守(高さおよそ26.6m)を復活させようとしている。古写真の発見や天守台修復で期待が盛り上がってはいるが、史料不足や文化庁の基準などの課題で「調査」段階にとどまっている。
現在、「高松城の復元を進める市民の会」の運動や玉藻公園管理事務所の岡一洋所長が、天守再建を訴える映画「REBIRTH 高松城を築城せよ!!」(約30分、2022年)を制作するなど後押しして、史料収集や遺構を保護しながら安全な天守が建てられる方法を検討中だ。

パブリックドメインの写真。日本人の写真家によって撮影された1882年12月30日の高松城天守閣。1882年12月30日に来日したイギリス人旅行者フランシス・ヘンリー・ヒル・ギルマールによって紹介された。Main tower of Takamatsu castle, December 30, 1882. It was taken by a Japanese photographer when came to Japan who Britain traveler Francis Henry Hill Gilmarl on December 30, 1882.
●月見櫓・水手御門・渡櫓
昭和22年(1947年)に、3件とも旧国宝(現在の重要文化財)に指定された。月見櫓は北の丸の隅櫓として延宝4年(1676年)ごろに完成したと言われ、出入りする船を監視する役割を持つとともに、藩主が江戸から船で帰るのを、この櫓から望み見たので「着見櫓(つきみやぐら)」とも言われている。
総塗籠造り(そうぬりごめづくり)の三重三階・入母屋造・本瓦葺で、初重は西側に切妻破風と南北に唐破風、二重は東西に唐破風と屋根の形を対比させている。月見櫓に連なる薬医門様式の水手御門はいわば海の大手門にあたる。
●鞘橋(さやばし)
本丸と二の丸を繋ぐ唯一の連絡橋で、ここを落とすと敵を防げる最終防衛ラインともいえる。当初は欄干橋だったが、江戸時代の中期から末期にかけて屋根付きの橋になった。
高松城愛があふれる高松市文化財課の大嶋さんに
お城の魅力を聞いてみた
高松城の取材では、高松市創造都市推進局文化財課の大嶋和則課長補佐に説明していただいた。
「天守台の高さは13.1mありまして、その上に三重四階、地下一階の天守が建っていました。天守台は26.6mあったので、全体では約40m、構造物としては45m近い高さがあったと考えられます。この高さは、四国では最大級で、西日本でも有数の規模を誇る天守だったとされております」
「この場所は、かつて海がすぐそばまで迫っていたんですよ。ですから、瀬戸内海を航行する船から見ると、非常に目立つ存在だったと思います。遠くからでも、堂々とした姿がはっきりと見えたことでしょう。まさに、『讃州讃岐は高松様の城が見えます波の上』の歌に詠まれたような、素晴らしい景観だったと思います」
「ただ、この天守は明治17年、つまり1884年まで存在していたんですが、残念ながら解体されてしまいました。古写真が残っておりますよね。あの写真を見ると、本当に見てみたかったな、という思いが強まります」
「解体の理由は、主に老朽化によるものでした。明治になると、陸軍が一時的にこの城を使用したんですが、わずか2、3年で丸亀の方に移ってしまいまして、城の建物の維持管理が難しくなったんです。現存しているのは、艮櫓や月見櫓など、外側の囲いに必要な建物だけで、天守をはじめとする他の建物は『もう不要だ』と判断されてしまったのではないでしょうか」
「石垣の解体修理と発掘調査を行いましたところ、地下一階の部分がしっかりと確認できました。実は、残っている遺構は少ないのではないかと当初は思っていたんですが、調査を進めると、礎石の配置や柱の痕跡など、非常に貴重な資料が出てきたんです。これらは本物の礎石で、一旦解体した後、元の位置に忠実に積み直しております」
「天守の構造について少し補足しますと、現在の天守は松平頼重公の時代、1670年に改築されたもので、南蛮造りと呼ばれる独特の様式でした。生駒氏の時代に天守があったかどうかは、はっきりしない部分もございますが、文献によると、頼重公が既存の天守を解体し、バージョンアップした形で再建したとされております」
「規模としては、文献に地下一階の大きさが『東西六間、南北五間』と記載がありまして、当時の高松の一間がおよそ1.97mでしたから、東西約11.82m、南北約9.85mの大きさになります。この礎石の配置とも一致しており、非常に興味深い発見でした」
また、海城と言うことについては、以下のように説明してくださった。
「高松城は海城、つまり水城として知られております。ご覧いただいているこの堀には海水が流れ込んでおりまして、スズキやタイといった魚が泳いでいるんです。餌やり体験もご案内できますよ。ただ、釣りはご遠慮いただいております」
「この堀は、瀬戸内海と直接繋がっているんです。水深は真ん中でおよそ2mほど。とても透明度が高いので、もっと浅く見えるかもしれませんね。 他の城の堀と比べると、高松城の濠は本当に透明度が高いんですよ。高松城は海と繋がっているので、水の流れがあり、冬になるとさらに透き通って見えます。こうした特徴が、玉藻城の魅力の一つなんです」
平成17年(2005年)から平成25年(2013年)にかけて行われた天守台の修復工事や、天守の再現計画についても話してくださった。
「この天守台の石垣は、九千個もの石が使われていて丁寧に積み直しました。大きい石だけでそれだけの数で、間に小さな石も使っています。二十センチ以上の石は、ほぼ元の位置に戻しているんですよ」
「天守の再現計画については、実は史料が少ないんです。明治時代の古写真が二枚と、発掘調査のデータ、各階の規模を書いた文献が主な手がかりです。もっと詳細な設計図や資料が必要なんです。もし何かご存じの方がいらっしゃったら、ぜひ文化財課までご連絡ください! また、石垣・盛土・礎石といった遺構を傷つけず、安全な天守が建てられるかということが最大の課題で、現在その調査を行っているところです」
「それでも、市民の皆様のご支援があって、『高松城の復元を進める市民の会』や、岡さんのドキュメンタリー映画など、復元への機運は高まっています」
また、生駒氏から松平氏への城の変遷についても話が聞けた。
「月見櫓や水手御門は、松平頼重公の時代に整備された部分が多く、生駒親正公が築いた当初の城を拡張したものです。生駒氏の時代には、このあたりは砂浜、片浜と呼ばれる浜辺だったんですよ。石垣も一部は生駒氏のものですが、松平氏がより精緻な石垣に改修しました」
「たとえば、現在の県立ミュージアムや県民ホールがあるあたりまで、松平氏が新たに堀や石垣を拡張したんです。生駒氏の石垣も、実はかなりしっかりした作りで、発掘調査では生駒氏の家紋が入った瓦も見つかっています。こうした発見は、玉藻城の歴史を紐解く上でとても貴重ですね」
現在の高松城の景色に欠かせない披雲閣についての話も、興味深いものだ。
「大正6年(1917年)、十二代当主松平頼壽公が別邸として建てた建物で、昭和天皇も宿泊された格式高い施設です。設計には、清水組の技師が関わり、非常に精巧な建築技術が施されています。ご覧いただくと、ガラスが波打っているのがおわかりいただけると思います。これは、当時の手作りガラスの特徴で、現代では再現が難しい貴重なものです」
「現在、耐震補強工事が進行中で、鉄骨を入れて耐震性を高める大規模な作業を行っています。この工事は一部が完了し、次のエリアに移る予定で、全体の完了には10年以上かかる見込みです。工事中であっても、披雲閣の一部はイベントや貸し出しでご利用いただけます」
「披雲閣の庭園もたいへん見事で、国指定の名勝に登録されております。この庭園は枯山水の様式で、大正時代には飛び石だった部分に、昭和3年(1928年)の全国産業博覧会で出品された石の橋が架けられました。この橋は一つの巨大な石から切り出されたもので、欄干も繰り抜いて一石から作られたものなんです。現代ではこんな大規模な石造りの橋を作るのは難しいと言われています」
「(今、見ている部屋の)窓の外に立派な蘇鉄が見えますよね。この蘇鉄にちなんで、この部屋は『蘇鉄の間』と呼ばれております。他にも、松の木が見える『松の間』や、槇の木が眺められる『槇の間』など、部屋からはそれぞれの植物が美しく見えるように設計されているんです。また、披雲閣には一部二階がございますが、そこからは瀬戸内海の波が見えることから、『波の間』と名付けられています」
「蘇鉄について少しお話ししますと、実は薩摩の島津家から贈られたものと伝わっております。資料は残念ながら残っていないのですが、こうした交流の証として大切に保存されてきました」
「披雲閣の建築にも注目いただきたいのですが、屋根のラインが微妙に湾曲しているのがおわかりでしょうか。蘇鉄の間は全体に反った屋根で、大書院は丸く膨らんだ曲線を描いているんです。これは意図的な設計で、和の建築美を強調する技法なんです。こうした細やかな意匠が、披雲閣の魅力を一層引き立てています」
「披雲閣の歴史についても少し触れさせていただきます。元々、この二の丸には、本丸御殿や藩主の政務施設がありました。生駒時代(1588年〜1639年)には、本丸に御殿がありました。松平頼重公の時代(1642年〜)になると、本丸に加えて二の丸にも御殿が整備され、さらに桜の馬場の東端に『対面所』という政務を行う施設が設けられました」
「披雲閣はこれらの機能を集約し、再構築されたものなんです。江戸時代の披雲閣は、現在の御殿の約2倍の規模で、写真や図面も残っております。天守を撮影した古写真と同じ時期に、披雲閣の前身となる御殿を天守台から撮った写真もあるんですよ」
■施設概要
所在地:
香川県高松市玉藻町2-1
開園時間:
東門は4月から9月は7:00~18:00、10月から3月は8:30〜17:00。
西門は日の出から日没まで
入園料:
大人:200円、小人(6~15歳):100円、65歳以上・6歳未満:無料(証明書提示)
アクセス:
JR高松駅から徒歩約5分。ことでん高松築港駅から徒歩約3分
公式サイト:
http://www.takamatsujyo.com/
高松市公式ホームページ:
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shisetsu/park/tamamo/index.html
戦国LOVE WALKERの最新情報を購読しよう