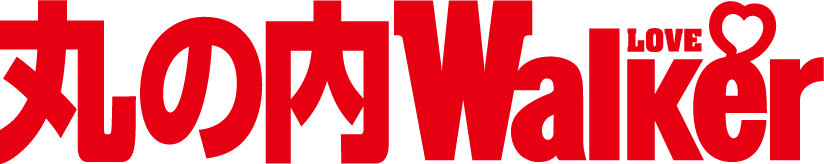大河ドラマ「べらぼう」の舞台、東京都台東区に「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」が、吉原や江戸城などタイムスリップした世界でオープンしたぞ
2025年02月01日 12時00分更新
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で注目を集める蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は寛延3年(1750年)、江戸・新吉原(現在の台東区千束付近)で生まれ、20代で吉原大門前に書店「耕書堂」を開業した。吉原細見や黄表紙本の発行に携わる中で、平賀源内や大田南畝ら文化人と交流を深め、東洲斎写楽や喜多川歌麿ら江戸文化を代表する作家たちを見出し、「江戸のメディア王」として大成功を収めた。
その蔦重(つたじゅう)ゆかりの地である台東区に大河ドラマ館「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」が2025年2月1日オープンした(2026年1月12日まで)。
戦国時代ではない平和な時代の話だが、大河ドラマを応援している戦国LOVE Walkerとして、早速内覧会に駆けつけた。実は筆者はドラマ館と同じ台東区在住で、浅草近辺も大好きなエリア。編集者として大先輩である蔦重の生きていた、戦は無くとも生き抜くのは生半可ではない江戸の世界をじっくり見てきたぞ。
「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」は台東区浅草の浅草寺にほど近い台東区民会館の9階ホールで開館している。周辺には仲見世通りや雷門、五重塔などが賑わう浅草寺のほかにも、歩いて回れる範囲に、蔦屋重三郎の菩提寺、正法寺や、「べらぼう」で綾瀬はるかが演じる九郎助稲荷を祀る吉原神社や吉原の帰りに名残惜しくなって振り返ったという見返り柳などが点在する。
台東区民会館もエントランスや入り口、エレベーターなど「べらぼう」の世界観に飾り付けられている。
ドラマで見た”あの!”小道具から花魁の衣装、4Kシアターの高画質な名所・旧跡まで堪能できる
ドラマ館の構成は、エントランス〜べらぼう入門編~五十間道ゾーン〜企画展示コーナー〜蔦重が見出した才能〜仲ノ町ゾーン〜江戸城ゾーン〜4Kシアター〜エンディングからなっており、ちょっとしたタイムトリップが体験できる。
ドラマに出てくるお馴染みの小道具や解説パネル、登場人物の紹介パネル、衣装や撮影可能な楽しいフォトスポットが楽しめ、4Kシアターでは、台東区の名所・旧跡の映像も紹介。エンディングにはドラマに登場する役者からコメント付きの色紙が並ぶ。個性的なコメントの中にはクスリと笑えるものも。
■お土産館「たいとう江戸もの市」
台東区ならではの土産品や「べらぼう」にちなんだグッズも並び、江戸情緒を感じさせる飾りつけも。
■大河ドラマ館「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」開催概要
会期:
2025年2月1日~2026年1月12日
開設場所:
東京都台東区民会館9階(台東区花川戸2丁目6-5)
アクセス:
各線浅草駅 徒歩5~9分
開館時間:
9時~17時(最終入館16時30分)
休館日:
毎月第2月曜日(第2月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始等
入館料:
個人:大人(中学生以上)800円、 小人(小学生)400円
団体:大人(中学生以上)640円、 小人(小学生)320円
※ 未就学児は無料。 ※ 障害者手帳を持っている人及び付添いの人1名は無料。 ※ 団体は20名以上から受け付ける。
公式サイト:
https://taito-tsutaju.jp/features/exhibition
■KADOKAWA発行の「べらぼう」をもっと知る事が出来る本
鈴木俊幸『本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代』(単行本)
「本屋」が時代を作った! 大河ドラマ「べらぼう」考証担当者の人気講義が一冊に。武家も庶民も読んだベストセラー『経典余師』は大人の参考書!? 顧客ファーストの貸本屋、大盛況の影に地道な努力あり! 役人と狂歌師のダブルワーク、天明狂歌の牽引者・大田南畝とは何者か? 江戸で刊行の『東海道中膝栗毛』が全国で爆売れした理由とは――。社長自ら、「蔦唐丸」と名乗り広告塔となった、べらぼうな男<蔦重>を生んだ江戸文化、300年の歴史を徹底解明する!
https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001747/
佐藤至子『蔦屋重三郎の時代 狂歌・戯作・浮世絵の12人』(角川ソフィア文庫)
江戸後期を代表する版元の蔦屋重三郎と、同時代の狂歌・戯作・浮世絵の才人たち。総勢12人について、その活動や人となりのわかるエピソード、作品の魅力と読み解き方をわかりやすく紹介する。天明の狂歌大流行の中心人物・大田南畝、「宝暦年中の色男」朋誠堂喜三二、『八犬伝』を執筆する前の曲亭馬琴、若かりし日の葛飾北斎、喜多川歌麿……。一人ひとりの人生をたどれば、蔦重の時代と江戸の娯楽文化のありようが見えてくる。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000254/
小林ふみ子『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)
天明期、江戸で狂歌が大流行した。狂歌とは、五七五七七の形式に載せて滑稽な歌を詠む文芸である。ブームの仕掛け人・大田南畝の昂揚感のある狂歌は多くの人を惹きつけ、誰もが気軽に参加できるその狂歌会は流行の発信源となった。楽しい江戸のまちの太鼓持ち「狂歌師」という役どころは、いかにして人びとを魅了したのか。平賀源内や山東京伝にも一目置かれ、蔦屋重三郎の良き助言者であった大田南畝の人物像がわかる決定版。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322309000243/
大久保純一『歌麿 UTAMARO ジャパノロジー・コレクション』(角川ソフィア文庫)
美人画を得意とした浮世絵師、喜多川歌麿。蔦屋重三郎のもとで出版した狂歌絵本『画本虫撰』や『百千鳥狂歌合』などの評価絵本でその画才を認められ、寛政前期には、《ホッピンを吹く娘》を含む『婦女人相十品』『婦人相学十躰』の揃物や、『当時三美人』など、女性の半身像を描いた大首絵を次々と発表して人気を博す。特に蔦重版では、華やかな雲母摺を背景に、女性たちを表情豊かに、その内面までも描き出した。卓越した画力を示す傑作の数々を詳説する歌麿入門の決定版。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322312001178/
渡邉 晃『写楽 SHARAKU ジャパノロジー・コレクション』(角川ソフィア文庫)
見開かれた目、きつく結んだ唇。歌舞伎役者たちの魅力を描いた絵師、東洲斎写楽。「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」をはじめとする役者の表情を切り取った大首絵。躍動感あふれる役者の全身像や、相撲絵や武者絵。天才絵師として形容される写楽を、当時の浮世絵出版の流れや、北斎や歌麿などの同時代の絵師との比較、版元・蔦屋重三郎との関係など、幅広い視点で見つめ直し、次世代への影響や最新の研究についても解説する決定版。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322312001179/
大田南畝 編/宇田敏彦 校注『万載狂歌集 江戸の機知とユーモア』(角川ソフィア文庫)
「吉原の夜見せをはるの夕くれハ入相の鐘に花やさくらん」。大田南畝らが編纂し、江戸に熱狂的ブームを巻き起こした『万載狂歌集』。狂歌史上もっとも重要なアンソロジーである。『千載和歌集』の部立に倣いながら、文芸界、歌舞伎、芸能、遊里など多彩な人々の作を取り上げ、庶民生活を活写する。「よろつのたからたからかに、世にきこえたるくさくさのことのは、かきあつめすといふことなし」。詳細な注釈とともに748首を味わう。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322403001251/
戦国LOVE WALKERの最新情報を購読しよう