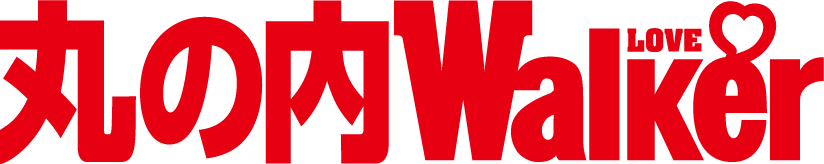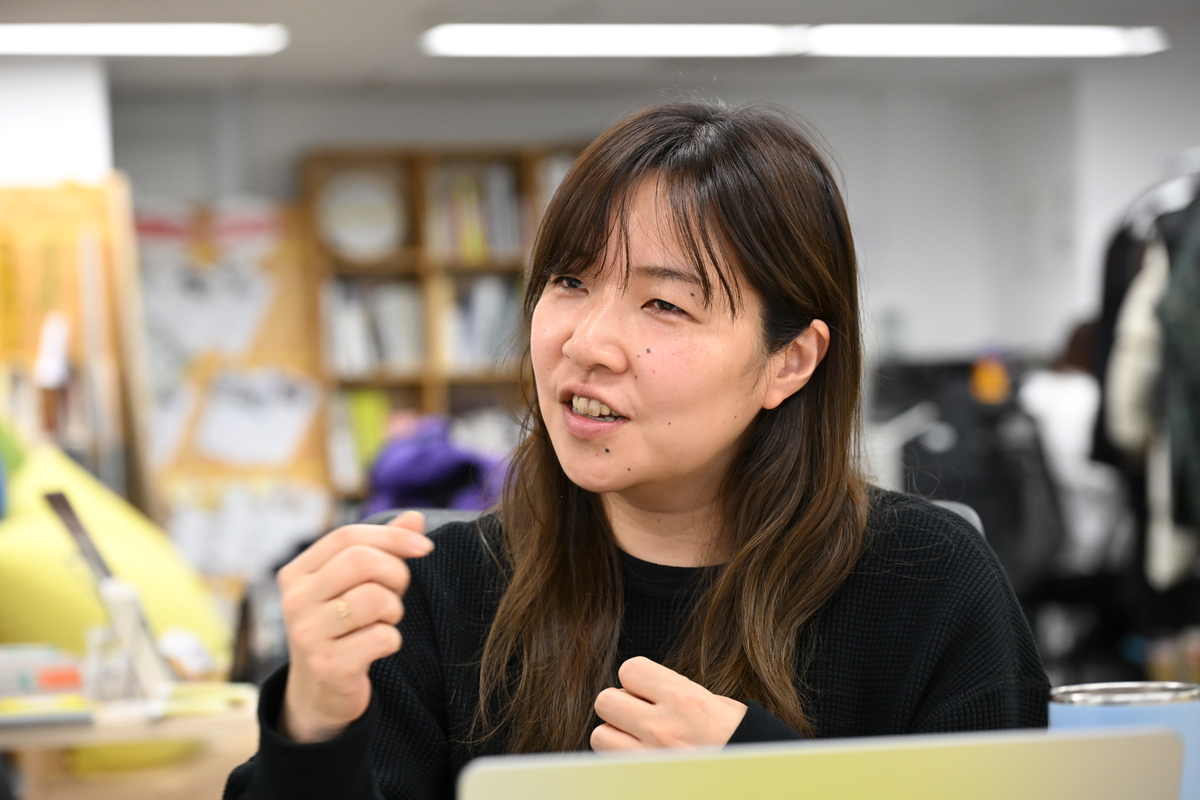アーティストが「普通に」いる街づくりを目指して活動する丸の内びと― 中森葉月さん、金森千紘さん
2025年04月01日 12時00分更新
アーティストと、ワーカーや企業が自然と交わるプロジェクト
――――2022年2月1日にスタートして、どんな活動を始められたんですか?
金森「当初は『アートアーバニズム』の仮説を実証するという大きな目的以外、具体的には何も決まってなくて、スタジオの機能をどうするかを考えるところから始めました。アーティストの活動が自然に起こるような街ではなかったので、演劇・ダンスの人のための稽古場やコワーキングスペースを作ろうとか、アーティストがこの街に来てくれるにはどうしたらいいかなど、仕組み作りに取り組みました。
展示を行うだけでなく、アーティストと協働するアートマネージャーを街に増やすためにミーティングができるように場所を整えたり、若手アーティストの制作場としてスペースを開放したり、さまざまな活動を受け止める場所を目指したんです。有楽町はアーティストが来る用事がない街なので、どうしたら持続的に活動が起こるか考えるのが大変でしたね。それでも最初の3カ月で約300人の方々が参加してくれて、このプロジェクトに価値を感じてくれる人がいることを確認することができたんです」
――――ゼロから始めて300人はすごいですね。特に象徴的なプロジェクトはありますか?
中森「演出家で振付家の倉田翠さんと、このエリアのワーカー十数人と一緒にワークショップをして、期間中に舞台作品を作ったんです。倉田さんは、舞台経験のない人たちとも作品制作をされる作家で、今は長野県のまつもと市民芸術館の芸術監督も務められているのですが、そこでは劇場の主催事業として少年刑務所の方とワークショップをやったり、過去には京都市東九条地域の住人と共に制作されていたりします。自分にとって『わからない』『わかりたい』人と作品を制作することに関心があって、倉田さんにとっては大丸有で働いているサラリーマンも同じく『わからない』存在だという話になって、それだったら一緒に作品を作れるんじゃないかと面白がってくれたんです」
――――実際にどういうふうにワークショップは進んでいったのでしょうか?
中森「参加者一人ひとりとじっくり話をして、その方の人生から言葉や動きを拾い集めてそれを演出、 振付していくというやり方をされていました。弁護士事務所の方や旅行代理店の方など、有楽町で実際に働いている方々が作品に参加してくれたんです。皆さんご自身の人生を語ってくださって、その言葉がそのまま舞台の上でも話されていたり、普段の仕事の内容が動きとして表現されたりしていました。稽古は仕事帰りの夜に開かれていて、参加者の中には仕事終わりに駆け付けたり、稽古の後に急いで仕事に戻るような方もいらっしゃったんです。皆さんが本当に熱心で、この作品をきっかけにできたつながりがとても強くて、いまだに何かあると連絡をとったり集まったりされています。参加者の方の振り返りコメントの中には『この街がグレーに見えていたけど、プログラムを通じて違ったものに見えた』といった声があり、それがとても印象的でした」

「大手町・丸の内・有楽町で働く人たちとパフォーマンス? ダンス? 演劇?をつくるためのワークショップ」 成果発表公演。『今ここから、あなたのことが見える/見えない』は2022年5月に有楽町にあるオフィスビルの一画で初演された
撮影=加藤甫
――――劇団に所属している役者さんではなく、一般のサラリーマンの方々がワークショップに参加されて、それぞれのお仕事を生かしたお芝居になったんですね。それは面白い! 企業とのコラボレーションではどんな課題がありましたか?
中森「ガラスメーカーのAGCさんやコンサルティング会社のPwC Japanグループさんとのコラボレーションでは、アートと企業の活動をどのように絡めたらいいのかという課題がありましたね。
AGCさんではガラスのリサイクルに関する取り組みを行っており、社内でサステナビリティに関する勉強会を開催しつつ、外部の方々とも積極的に意見交換する場を作っていました。その中で、建物解体時にガラスがコンクリートと一緒に廃棄されるという課題があることを伺い、これを『アートを通じて社会に伝えられないか?』という話が持ち上がったんです。ガラスだけなら再生可能なのですが、高層ビルの解体時にはガラスとコンクリートを分別するのにコストがかかるので廃棄されることがほとんどだという…。
そこで、アーティストの内海昭子さん、磯谷博史さんとともに、採掘現場や廃棄現場を訪れてリサーチを行い、その結果をもとに作品を制作しました。さらにその作品展示と同時に、サステナビリティに関心をもつさまざまな方やAGCさんを招いたディスカッションテーブルを設け、作品をきっかけにして、持続可能なガラスのあり方を話し合う機会を設けました」
――――制作した作品について具体的に教えてください。
金森「たとえば、砕かれたガラスがモーターによって下へこぼれ落ちる様子を表現した内海さんの作品ですね。リサイクルできるはずのガラスが実際には産業廃棄物として廃棄されてしまう現状を象徴しています。
さらに、作品を見る人が『ガラスの価値』や『再利用の可能性』について考えを巡らせるきっかけになることを意識し、展示設計の工夫も取り入れました。作品を見る前にリサーチのプロセスを知ってもらったり、作品を見たあとに再びリサーチの様子を振り返るといった流れを意識しました」
――――反響はどうでしたか?
中森「AGCさんや建築関係者の方々から『異なる立場の人と展示空間でともに時間を過ごすことで、普通の展示会では難しい文脈を共有した議論をすることができた』という声があり、作品を通じて普段とは異なる視点で問題を考えるきっかけになったようです。アートがこうして社会課題にアプローチできるというのは、すごく意味のあることだと感じましたね」
――――このようなプログラムを大丸有エリアでやっていくということについて、実際に効果みたいなものはありましたか?
金森「YAUと何か一緒に取り組めないか?とプログラムの相談をしてくれる方が出てきましたね。一度参加した方が違うプログラムに参加してくださったり、その成果発表の場にご自分の会社の方を連れてきてくださったりとか。 個人レベルではありますが、ここを使う人が増えたりアートというものに触れる率が高くなった人はいるんじゃないかなと思います」
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう