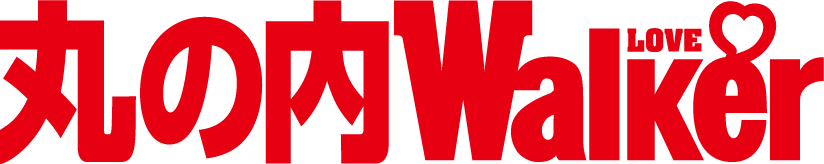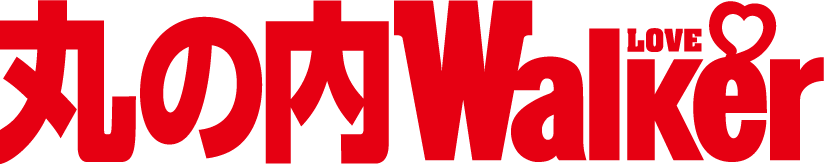クラシック音楽の聴き方、楽しみ方ってどうすればいいの? 「ラ・フォル・ジュルネ」で考えた
2025年05月06日 07時00分更新

クラシックをよく知らなくても大丈夫?
クラシックの祭典、「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025」(以下、LFJ)。最終日(3日目)となる5月5日(月・祝)、筆者も行きました。たくさん聴いてきました。
筆者はクラシックが好きです。なので、クラシックのコンサートとなれば自分なりに楽しみ方をいくらでも見つけられます。そのために、「LFJに取材? はいはい、行きまーす」と挙手して向かいました。明るく楽しい職場とは、こういう環境のことをいうのでしょう。

会場の一つ、東京国際フォーラム。GWということもあり、多数のお客さんでにぎわっていました
しかし、クラシックが好きといっても、“好き”の度合いは人それぞれです。最近クラシックを聴き始めた人もいれば、「興味があるのでコンサートに行きたい」という人もいるでしょう。
クラシックという音楽は「むずかしい」と思われがちです。そんなことはない! と言いたいのですが、実のところ、そういう面もあるといえばあるのがクラシック。現代の音楽の演奏時間や曲構成に慣れた我々からすると、「長すぎる」「展開がよくわからない」「そもそも曲をよく知らない」となるのはむしろ自然なことです。
そんなクラシックの聴き方、楽しみ方を、まだよく知らない。そんな自分でもLFJに行ってよいのだろうか。来年はLFJに行ってみたいけど、楽しめるだろうか。そんなふうに考えている人もいるかもしれません。
結論から言うと、クラシックが好きな人はもちろん、よく知らない人でも行きやすい、楽しみやすいのがLFJだと思います。その理由を、5月5日に開催されたコンサートの感想を交えながら説明していきましょう。
LFJは「入門」に向いている
ラ・フォル・ジュルネは、「熱狂の日」を意味し、もともと1995年にフランス西部の港町ナントで誕生したクラシック音楽祭。ラ・フォル・ジュルネ TOKYOは、いわば“日本版”です。
期間中に、およそ45分〜60分の公演を多数並べているのが特徴。普通のクラシックのコンサートと比べれば、短めの演奏時間です。また1公演の大人の料金が2000円台からと、クラシックのコンサートとは思えない価格で楽しめる公演がほとんど。
これらの要素により、いくつものプログラムを気軽にハシゴできるようになっています。さらに、多彩な無料イベントも用意されているため、いろいろな楽しみ方で音楽に触れ合えるのですね。

オーケストラで使われる楽器を体験できるスペースもあります。写真はハープを演奏しようとがんばる筆者。ペダルの踏み方が素人丸出しですね……
幅広い層が楽しめるという点では、親子で揃って盛り上がれるという点も忘れてはいけません。幼いうちに音楽に触れてほしい……そんなコンセプトから、3歳以上の未就学児の子供でも入場できるコンサートが用意されています。

会場内には「子供も参加できる」ことをアピールするポスターもありました
時間的にも、金額的にも、リラックスして臨めるコンサートがたくさん。親子連れにも優しい。クラシックをよく知らない人への「入門」として、LFJはピッタリといえるでしょう。
今年のテーマは「音楽の時空旅行」
それってクラシックを聴くことそのものじゃないか
さて、5月5日の有料コンサートの中で筆者が見てきたのは、たとえば以下のプログラムです。
公演番号:323「四季世界一周」
(曲目)
《ヴェネツィアの春》
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 抜粋
《パリの夏》
フォーレ:夢のあとに
サン=サーンス:死の舞踏
《ブダペストの秋》
ブラームス:ハンガリー舞曲第17番
セルキン:あなたの愛に
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
《ニューヨークの冬》
ガーシュウィン:「パリのアメリカ人」から ブルース
パーキンソン:ルイジアナ・ブルース・ストラット
バーンスタイン:ウエストサイド・ストーリー(メドレー)
今年のLFJのテーマは、「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」。音楽の発展に多大な貢献をした都市とその時代にスポットライトを当てています。
このコンサートは、そのテーマをわかりやすく表現したものといえるかもしれません。何しろ、「世界一周」ですから。
当時の音楽の中心地だったイタリアの作曲家、ヴィヴァルディの「四季」からスタートし、19世紀後半から数多くの作曲家を輩出したフランスの楽曲でパリを表現。そこからブラームスにインスピレーションを与え、バルトークを輩出したハンガリー(ブダペスト)が舞台となった音楽につなぎ、最後は20世紀のクラシック音楽で大きな存在感を発揮したアメリカのニューヨークへ……。

会場ではコンサートごとにプログラムも配られています
一口に「クラシック」といっても、長い歴史があるわけです。異なる時代の楽曲を、都市と“四季”というコンセプトでパッケージした、LFJならではのおもしろいコンサートでした。
そうそう、演奏が始まる前に、演奏者が「いろいろな曲をやりますけど、好きなタイミングで拍手してください」と前置きし、会場を和ませていました。これも、普段はクラシックのコンサートに行かない客層が多いLFJならではの光景かもしれません。
もう1つ紹介すると、筆者が好きな曲のシューベルト「ピアノ五重奏曲」のコンサートも聴いています。第4楽章が歌曲「鱒」の旋律による変奏曲であることから、とても有名。読者のみなさんも「シューベルト 鱒」で検索してみてください。旋律を聴けば「ああ、これか!」となるはずです。
公演番号:322「颯爽と泳ぎ、跳ねる、若者たちの五重奏」
(曲目)
シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667「ます」
もちろん、シューベルトの名曲をコンサートで聴きました……という言い方もできます。しかし、「音楽の時空旅行」というテーマを頭に入れて聴いてみると、また多面的な楽しみ方が見えて(聴こえて)くる。
音楽の都、ウィーンで生まれ育ったシューベルトの若い時代の傑作(といっても、シューベルトは31歳の若さでこの世を去るのですが……)。そして、この曲の作曲を依頼したのは裕福な鉱山技師の楽器愛好家、ジルヴェスター・パウムガルトナーといわれています。

プログラムには曲目紹介もあるので、「初めて聴く曲だなあ」という人でも安心
モーツァルトを愛し、ベートーヴェンと同じ時代に生きた歴史に残る作曲家が、アマチュアの演奏家のために音楽を書く時代がありました。それがおよそ200年の時を越えてプロが演奏しているというのも、クラシックの面白みでしょう。そう考えられるのも、「音楽の時空旅行」というテーマを念頭に置いているからこそ。
音楽の発展に多大な貢献をした都市とその時代にスポットライトを当てる「音楽の時空旅行」というテーマは、異なる時代の音楽を楽しむこと、遠く離れた土地の文化の薫りを感じることでもありましょう。まさしく、クラシックを聴くことそのものともいえるかもしれません。
音楽祭にテーマを用意することは、「クラシックのことをよく知らない」という人のために補助線を引いているとも考えられます。こういうテーマがありますよ、こういう楽しみ方がありますよ……という大きなテーマを用意し、それに沿った45〜60分のコンサートたちを楽しむ。それなりのお金を出して長時間のコンサートに行くより、ずっと気軽ではないでしょうか。
クラシックとの向き合い方がわかれば
「聴き方、楽しみ方を見つけた」と胸を張って言える
LFJはさまざまなクラシックのコンサートがあるので、自分が興味のあるものに行ってみましょう。楽しめれば文句なし。そこからクラシックのコンサートに行くのもアリでしょう。「ちょっと違ったかも」と思ってもいいんです。また他のコンサートに行ってもいいし、興味が出るまで放っておく、という向き合い方もあるのではないでしょうか。

地上広場には多くのキッチンカーが出店しているので、「コンサートの合間にお茶でも」ということも簡単にできる
筆者が音楽に関する本を読んでいたとき、「自分なりに勉強して、クラシックを聴いて、それでもピンと来なかったのであれば、その人は立派にクラシックへの入門を果たしたのだ」というような記述を見つけたことがありました。
わけもわからずにクラシックをありがたがっている人よりも、自分なりに興味を持って親しもうとしてみたものの、いまいち掴めなかったという人のほうが、クラシックという対象にしっかり触れているということなのでしょう。
クラシックを「高尚で、難解なもの」と考えている人もいるかもしれません。もちろん、そういう面を持つジャンルであることは否定しません。でも、これが「タイ料理」だったらどうでしょう? 「韓国映画」だったら? あるいは「ガーデニング」でも、「ソロキャンプ」でもいいです。
興味を持ち、ある程度の下調べをしてやってみたけど、「うーん、しっくりこなかった」と思った。それでいいのではないか、と。無理やり好きになったり、知識を詰め込む必要はないはずです。
たとえば、めちゃくちゃ唐突な例え話で恐縮ですけど、「焼肉」で考えてみてください。以下のような人がいたとします。
「焼肉、たまに行きます。どちらかというと赤身肉のほうが好き。ホルモンはみんな好きというけど、自分はちょっと。ライスは頼む派です。高級店は人生で3回くらいしか行ったことがないです」
この人、焼肉との向き合い方を知っていますよね。好きなものもあればそうでもないものもある、しょっちゅう行くわけではないけれど、自分なりに楽しんでいる。クラシックも、それと同じことだと考えていいのでは?
クラシックに対して、自分なりの聴き方、楽しみ方を見つけられれば、それはとても幸せなことだと思うのです。「クラシックとの向き合い方」がわかれば、「聴き方、楽しみ方」を見つけたと胸を張って言える。LFJは、そんなクラシックとの向き合い方を見つけるのに最適な場所ではないでしょうか。
5月5日、クラシックが好きな人間として、LFJのさまざまなコンサートを満喫しました。クラシックに親しみがある人も、そうでもない人も、次のLFJにはぜひ(気軽に)参加してみてください。あなたらしいクラシックとの向き合い方、きっと見つかると思います。

また来年。LFJでお会いしましょう
ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025
開催日:2025年5月3日(土・祝)・4日(日・祝)・5日(月・祝)
会場:東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町、東京駅、京橋、銀座、八重洲、日比谷、みなとみらい

文 / モーダル小嶋(ASCII編集部)
1986年生まれ。「アスキーグルメ」担当だが、それ以外も担当することがそれなりにある。編集部では若手ともベテランともいえない微妙な位置。クラシック音楽も好き。お気に入りの作曲家はブラームスとラヴェル。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう