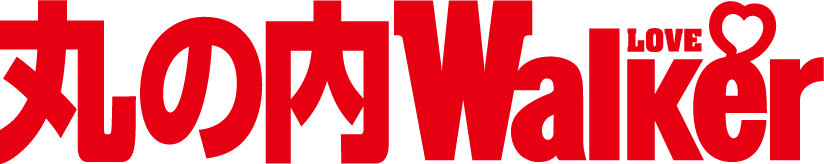エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀「大阪・関西万博2025をブラタマキ」 第4回
円環、循環、日本館。「大阪・関西万博」の日本館はハローキティにも火星の隕石にも出会える「ごみ」から「水」への物語
2025年05月23日 19時00分更新
2025年大阪・関西万博を筆者が歩く連載も第4回。今回はいよいよ、我が国のパビリオン「日本館」にお邪魔した。テーマは「いのちと、いのちの、あいだに」。命が終わり役目を終えた瞬間、新たな命が始まり、循環していくプロセスを表現している。
この「命の循環」を建築構造と館内展示の両方で表していて、全体が大きな円環構造になっていて、それぞれの場所が始まりであり、終わりであり、再生である。どこからでも見始められるのだ。
政府直営パビリオンであり、ホスト国日本の象徴として、会場最大級の規模(敷地面積約1万3000m²)を持っている。
科学的もあり哲学的でもあるアプローチだが、ファクトリー、工場(実際に稼働できる)と詩的でアートな表現が一体となっていて、それらが楽しくてかっこいいエンタテインメントになっている。「めっちゃきれい!」と言いながら回るのも、全然ありという感じの場所だ。
総合プロデューサー・総合デザイナーは佐藤オオキ氏で、デザインオフィス 「nendo」(ネンド)代表。東京2020オリンピックの聖火台デザインを担当した。パビリオンでは、全体のストーリーとビジュアルコンセプトを構築している。
初期には、曼荼羅のようなダイアグラムで「始まりも終わりもない」循環のイメージを提示していた。そこから、循環のプロセスを身近な例(ごみの分解、藻類の活用、ものづくり)に落とし込み、建築と展示で表現することを考えた。設計は、日建設計が担当している。
館内は以下の3つのエリアで構成され、来場者が円環状で巡ることで「循環」を体感出来る。
(1)ファームエリア(水から素材へ):
主役は、化石資源への依存や食料不足など、さまざまな課題を解決しうる存在として注目されている藻類。 藻類が次世代の原料として持つポテンシャルを紹介。
(2)ファクトリーエリア(素材からものへ):
日本の伝統的な循環型ものづくりを展示。 長持ちするものを頑丈に作るのではなく、柔らかく壊れやすく作ることで持続可能性を追求する日本独自の考え方を表現している。
(3)プラントエリア(ごみから水へ):
ゴミが微生物の力で水や他の資源に変わる過程を展示。 新しい命の始まりを象徴するエリア。
展示の流れは、ゴミ→水→素材→もの→ゴミというサイクルを、3つのエリアを巡ることで理解できるようになっている。例えば、パビリオンに実際に設置されたバイオガスプラントで生ゴミを分解し、エネルギー(バイオガス)や水に変換。水は浄化したうえで中央の水盤に、バイオガスは電力として一部再利用されるといった具合だ。
パビリオンの内外壁には、国産スギ材のCLT(直交集成板)パネル560枚が使用されている。CLTは、複数の板を繊維方向が直角に交わるよう重ねて接着した合板で、高い強度を持つ。四角いCLTパネルをずらして配置し、円環状の構造を形成している。
円形は「始まりも終わりもない」命の循環を象徴する。内外壁に使用された木材も、最小限の加工(塗装なし)で、万博終了後に企業や自治体による再利用を予定されている。解体・転用が容易な設計で、ゴミにならず循環を継続できる。
板壁は、鉄骨をCLTで挟んだユニークなつくりで、CLTパネルを隙間を空けてドミノのように配置し、さらには、CLTパネルの間にガラスを嵌め込む事で、中と外の境界を曖昧にしているのも特徴だ。
外から内部が見え、内部には外から光が差し込む設計で、「あいだ」を建築的に表現している。3ヵ所の入口は週替わりで使用され、どのエリアからでも循環を体感出来るようになっている。
水から素材へを表現するファームエリア
「水から素材へ」をテーマに、藻類や微生物が「素材」を生み出す最新の「バイオものづくり技術」を展示している。藻類に扮したハローキティの展示はインパクト十分。
藻類に扮したハローキティの展示
>ハロー! かたちで選ぶ「藻類×ハローキティ図鑑」。人類よりもずっと昔から地球上に存在している「藻類」は、普段は目立つ存在ではないが、人類共通の課題を解決し得る切り札として注目されている。
光合成を通じて水を酸素と糖に換えるだけでなく、栄養価の高い食料になったり、石油に代わる燃料を生み出したり、化粧品などの原料を作り出したりする。
大阪・関西万博「日本館」では、そんな藻類たちの可能性を拓く日本の技術開発について紹介する展示を実施している。その一つとして、世界中で愛されるキャラクター・ハローキティが藻類の姿に扮して登場。
自然界に存在する藻類は一説には30万種類以上と言われ、肉眼では見えないほど小さなものから50mに達するものまで、大きさやかたちもさまざまだ。そのうち32種類が“藻類×ハローキティ”として、1mを超える立体物になって日本館に並んでいる。
素材からものへというプロセスを伝える
ファクトリーエリア
「素材からものへ」というプロセス。ファームエリアで育てられていた藻類を原料に加えたバイオプラスチックを用いて、3Dプリンターによる積層造型を用いたスツールを製作する様子の紹介や、日本の循環型ものづくりについて、伝統を最先端の比較を通じて持続可能な未来を示す。
3Dプリンターによる積層造型を用いたスツール製作の様子がラボ感が強くてカッコいい。
このエリアでは、日本の伝統的なものづくり(壊れやすく、やわらかく作ることで長持ちさせる)と最先端を対比しながら8つの事例で紹介する。ドラえもんを活用し、親しみやすい教育的体験を提供してくれるのも楽しい。
例えば、「桶とサッカーボール」は分解可能な共通点を示す。壊れたパーツのみ交換できる。空気入れ不要の分解可能なサッカーボールもある(株式会社モルテンのMY FOOTBALL KIT)。
ひとつの布を無駄なく使って無駄なく仕立てる日本の着物は、糸を引き抜けば再び一枚の布に戻すことができ、仕立て直しが容易だ。分解可能な接着剤(例: スマホの再利用向け)は使用時はしっかり固定が出来て、役目を終えたら簡単に分解できる。
日本館のアテンダントユニフォームは「日本の美意識を纏う(まとう)」をコンセプトに制作された。着物の構造をもとに、余白を大切にする日本的な感覚を体現。着心地、動きやすさ、暑さ対策などの機能性に加え、環境に配慮した素材の使用や会期終了後のリサイクルなど、さまざまな視点に基づいた工夫が盛り込まれている。
あるいは、「流れ橋と月面着陸」。京都の流れ橋は、川が増水した際に橋桁が流されることで橋全体にかかる負担を軽減し、一番重要な部分を守る設計になっている。月面着陸機の脚部も、衝撃で敢えて潰れるようにしてあり、衝撃を吸収する。
「風呂敷とトランスフォーム」は、「機能に応じてものを増やす」のではなく、「ひとつのものが担える役割を増やす」という観点で取り上げられている。
「焼杉と大気圏再突入カプセル」では、焼杉は表面を炭化させることで腐食を防止。大気圏再突入カプセルはカプセル表面に融点の低い素材を用い、それが蒸発しながら「打ち水」のように熱を冷ますことで、内部の温度を保つ。
伝統と先端技術の対比ではないが、伊勢神宮の式年遷宮は、20年ごとの建て替えで職人技術を継承している。スカイツリーの「やわらかく作ることで地震の揺れを受け流す」つくりは日本古来から使われている和釘を連想させる。
命の循環」を「ごみから水へ」というプロセスで体現する
プラントエリア
「命の循環」を「ごみから水へ」というプロセスで体現するエリア。生ごみをバイオガスプラントで微生物により分解し、エネルギー(バイオガス)や水に変換する。生ごみを分解する過程で生じた水は、浄化したうえで中心の水盤に送られ、バイオガスは発電に回され日本館の電力の一部として活用される。
まさに、 命の終焉(ごみ)が新たな命の始まり(水、エネルギー)につながる「循環」を表現しているのだ。ごみは単なる廃棄物ではなく、資源(水、エネルギー)として再利用可能であることを示す。 微生物の自然な分解プロセスを、視覚的かつインタラクティブに伝えてくれる。
具体的には、万博会場内で出た生ごみや会場内の食品廃棄物(飲食ブースの残飯、野菜くず)を収集し、タンク内で微生物により分解。そして、バイオガスに変換し、副産物として排水と残渣が生じる。バイオガスは発電機の燃料として使用する。排水は浄化し、中心の水盤に送る。
コンパクトな設計で、万博会場のスペースに最適化(1日最大1000kgの生ごみ処理を想定)されている。
印象的なキャッチコピーを提供しているコピーライターは渡辺潤平氏。広告キャンペーンの企画立案のみならず、コーポレートスローガンの策定や商品・企業のネーミング、作詞など、言葉を中心としたコミュニケーションを幅広く手掛ける。カンヌ国際広告祭、ACC賞、TCC新人賞、日経広告賞、ギャラクシー賞など受賞。山梨県北杜市にて書店「のほほん BOOKS&COFFEE」を経営している。

各麹菌の遺伝的特性、とりわけ味に味にかかわりの深い特徴を、線香花火をモチーフにしたオブジェで表現している。麹菌は日本の発酵食品(味噌、醤油、酒、酢など)に欠かせない微生物(カビの一種)で、デンプンやタンパク質を分解し、甘味や旨味を生み出す酵素(アミラーゼ、プロテアーゼ)を生成する。日本食文化の基盤であり、「国菌」として日本醸造学会で認定されている(2006年)
「ごみ」から「水」へをテーマにする
プランとエリアの最終局面
水盤は、バイオガスプラントで、生ごみの分解過程で生じた排水を浄化して使用する、「ごみ」から「水」へをテーマにするプランとエリアの最終局面。微生物の働きによって、ごみがすべてのいのちの源としての水に生まれ変わっていることを感じることができる。
日本館の円環状CLT(直交集成板)建築の中心に配置された水盤で、来場者が周囲を歩きながら観察できる。日建設計の設計に基づき、CLTパネルの隙間から水盤の光や水面が外の景色と融合し、「あいだ」を空間的に表現している。
火星に水が存在したことを示す
火星の隕石「Yamato 000593」
今回展示されている火星の隕石は、「Yamato 000593」。2000年11月29日、南極観測隊の一員として昭和基地に赴いていた国立極地研究所の今栄直也氏が、やまと山脈の近くを探査中に発見した。
およそラグビーボールほどの黒い石。隕石であることはすぐにわかったものの、それがどこから来た石なのかは分からなかった。
翌年、観測隊は日本に石を持ち帰り、詳細な分析を始めた。石やガラスを切ることができるカッターで切断し、それを光が透けるほど薄く研磨し、光学顕微鏡で光を当て、その組織を確認していくと鉱物の特徴的な模様が見えてきた。
「ナクライトだ!」研究者たちはみな驚いた。ナクライトとは火星由来である可能性が高い、とても珍しい隕石だったからだ。さらに詳しく分析し、隕石に含まれるガスの成分を調べると「Yamato 000593」は火星からやって来たということが証明された。
国立極地研究所の昭和基地は、南極の東オングル島、日本から直線距離で約1万4000km離れたリュッツォ・ホルム湾東岸に位置する。 南極には隕石が多出する「隕石フィールド」と呼ばれるエリアがいくつかあり、今回の隕石はそのひとつであるやまと山脈(昭和基地の南西約350キロメートルに位置する)付近で発見された。
白い氷上では、黒い隕石は発見されやすい。低温かつ乾燥した環境のため、隕石が風化せず保存状態がいい。氷河の流れが山脈でせき止められることによって、隕石が氷床の表面に集められることなど、さまざまな条件が重なり、南極は地球上でもっとも隕石が見つかる場所といわれている。
「Yamato 000593」という名前は、発見場所であるやまと山脈氷原に由来し、数字の頭の00は採集した年度(2000年度)。続く0593はその年度に採集した隕石の通し番号を表している。
しかし、なぜ、今回の日本館で火星の隕石なのか。
「Yamato 000593」に大きな注目が集まるのには理由がある。それはかつて、火星に水が存在したことを示す重要な証拠となるからだ。今の火星は大気が薄く、気温の変化が激しいことから、生物が住めない環境と言われているが、かつて地球上の生物が大海原で進化を遂げていったように、火星にも海があり、生命が存在した時代があるかもしれないのだ。
2024年には、火星の地下奥深くに液体の水があるらしい、ということがわかってきた。火星に水があるならば、将来人類が火星で暮らすことができるかもしれない。
「Yamato 000593」をはじめとする火星隕石の研究によって、火星の過去と現在が解き明かされつつある。それは、私たちの未来の暮らしを変える鍵となる可能性がある。
水の循環が表現されるプランとエリアの〆としてはピッタリかもしれない。
1970年に開催された大阪万博では、アメリカ館にアポロ12号が持ち帰った「月の石」が展示され、人々の注目を集めた。今回はまた、アメリカパビリオンで、そのときの石を見ることができる(筆者は70年万博の時は小学3年生で6回、会場に足を運んだが行列に負けて見れなかったものの、今回は見た)。半世紀の時を経て、2025年の万博で今度は「火星の石」が展示されたのだ。
日本館の大森俊輝氏に話を聞いた
大阪・関西万博日本館の大森俊輝氏に話を聞いてみた。解説が熱い。
「この隕石は、2000年に日本の南極観測隊が南極のやまと山脈付近で発見したんです。サイズはラグビーボールくらいで、重さ12.7kg。火星由来の隕石としては世界最大級で、今回はじめて一般公開されるんですよ」
「どうして、これが火星から来たってわかるの? って思いますよね。この隕石に閉じ込められてるガスの組成が、NASAのヴァイキング探査機が実測した火星大気組成データと一致したからなのです」
「およそ1000〜1300万年前に宇宙に飛び出して、数万年前に地球に到達したと考えられているのです。想像するだけでワクワクしますよね」
で、もっとすごいのが、この隕石には水がない限り生成しないとされている粘土鉱物が含まれているんです。つまり、火星に昔、水があったって証拠。水があれば、生命の可能性にも繋がるじゃないですか。ロマンを感じませんか。学術的にも価値が高くて、研究者も大興奮の逸品なんです」
「日本館のプラントエリアでは、この隕石をケースに展示しています。実物はもちろん、触れるかけらも用意してますので、実際に火星の石に触れられるんですよ。さらに、館内の他のエリアでは、『はやぶさ』と『はやぶさ2』が小惑星イトカワおよびリュウグウから持ってきたサンプルも展示します」
「日本館は、ごみから水が生まれ、水から藻類を培養し、新たな素材を作り出す。素材は新たなものへと生まれ変わり、役目を終えれば再びごみとなる。始めもなければ終わりもないという循環をパビリオン全体で表現しているため、ぜひ見に来てください」
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう