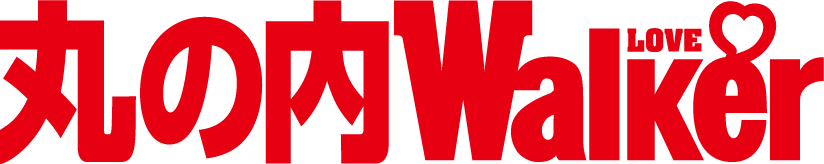今回から始まった連載「スタートアップのスタート地点」は丸の内を拠点に日本で、そして世界へ羽ばたくスタートアップを紹介し、スタートアップから見た丸の内の魅力や利点などをお伝えしていく。その記念すべき第1回は、リアルタイム遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」を提供している株式会社ジザイエ(以下ジザイエ)。
ジザイエは丸の内で創業したスタートアップで、元々は東京大学の稲見教授が研究総括を務めるプロジェクトで自在化身体技術を社会実装することを目的として起業した。自在化身体技術というのは、ロボットや建設機械など、大小様々な機械を自分の身体のように動かし、人間の可能性を拡張する技術で、その研究の応用として生まれたのが「JIZAIPAD」となる。
今回はジザイエの代表取締役CEOの中川純希氏に、取り組んでいるプロダクトやソリューションについてお聞きしつつ、丸の内の魅力についても語っていただいた。
リアルタイムで遅延なく映像が見られる「JIZAIPAD」
――ジザイエは丸の内で創業されたとのことですが、現在の拠点や社員数はどのくらいですか?
中川氏:ジザイエは創業まもなくの2023年1月に大手町ビルヂングのInspired.Labへ入居しました。現在は御茶ノ水にも拠点があります。社員数はパートまで含めて45名ほどで、大手町がメインで、御茶ノ水はハードウェア製品を作っています。
――事業内容としては「JIZAIPAD」が主要製品ですか?
中川氏:はい。リアルタイム遠隔就労支援プラットフォームと呼んでいますが、PCやスマホを使ってリアルタイムで遅延なく映像が見られるアプリケーションが基本で、就労支援のためのロボットやドローンを遠隔操作するアプリケーションを作っています。開発しているのはエッジコンピューターです。
――創業のきっかけはなんでしょう
中川氏:元々は東京大学の稲見教授が研究総括する文科省系のプロジェクトに研究成果を社会実装する役割をしてほしいと言われて所属していました。研究は自在化身体技術といって、人間がロボットやAIと「人機一体」となり、自己主体性を保持したまま行動することを支援し、人間の可能性を拡張する技術です。ロボットアームを遠隔操作し、一人ではできなかった作業をするのですが、オペレーターに遅延なくきれいな映像を途切れることなく送ることが難しいということに行き着きました。通信環境が不安定な場所でも、特別な通信網を整備することなく、一般的な回線で高画質・低遅延な映像がリアルタイムで届けられるような映像圧縮伝送技術の開発を始めたのがジザイエの始まりとなっています。
――創業したときには商品となるサービスができていてビジネスを開始したという感じでしょうか
中川氏:きちんと準備をしてビジネスを始めたつもりでしたが、実際には市場のニーズがとても多様で、画一的な商品をそのまま導入するだけではうまくいかないことがわかってきました。一つひとつの現場に合わせて、エンジニアが柔軟に対応する必要がある市場だったんです。そして、そうした対応力を持つ企業は、ほとんど存在しないことも見えてきました。プロダクトとして、たとえばコンセントに繋げば動くとか、WebでこのURLを開けば使えるという形にする必要があり、その開発をここInspired.Labで始めました。
――開発で苦労されたことはなんでしょう
中川氏:ソフトウェアとハードウェアの両方をプロダクトとして提供するのですが、必要とされるスキルセットが違うエンジニアを採用して、バランスを取りながら開発をしないといけないというのが難易度が高いところです。
――今提供しているサービスでの課題はありますか?
中川氏:現在数百台を想定したアプリケーションですが、今後は数千台、数万台となることが予想されるので、そのときにしっかりと耐えられるインフラ設計にすることです。映像プラットフォームとしてより使いやすい機能を備えることも必要ですし、接続の安定性や、接続が切れた際のアラートの出し方、フェイルセーフを踏まえたアプリケーション設計にするなど、いろいろと課題はあります。
――顧客はどのような業種ですか?
中川氏:今導入していただいてる顧客の多くは建設業になりますが、最初は農業の領域をやっていました。プロトタイプや最初の実証実験は農家でさせていただいています。農地は通信環境が不安定であることが多く、ビニールハウスの中は高温多湿な環境。また農家の方からは実際に現場に行かないと状況がわからないという声も多く、高画質な映像を検証するには最適な環境でした。しかし業界構造やビジネスモデルの観点からスケールしづらいということで、今は建設業が主体となっています。
――今後伸ばしていきたいことはありますか?
中川氏:ロボットやドローンを遠隔操作するのはプロトタイプまでできていて、製品として提供するということを考えています。また、ロボットの遠隔操作や監視・警備といった防犯などの仕事を求職者とマッチングさせるような機能をつけていきたいですね。
――広げていきたい業種はありますか?
中川氏:建設、土木、製造工場、造船所などに向いていると思うのですが、大きな現場で通信環境が悪く、人手不足で困っているというのが共通の課題です。あとは防災ですね。ダムの遠隔管理といったことにも使えないかと考えています。山の中や海にせり出しているような場所を遠隔管理するようなことができるといいなと思っています。
小さな時間の節約ができる丸の内はスタートアップに向いている
――丸の内に拠点を作ろうと考えた理由はなんでしょう
中川氏:弊社が顧客とする会社はリモートができないことが多いので、僕らも現場へ行かなければなりません。ハードウェアも関わってくるので、各チーム協力し合って開発するということがとても重要です。リモートを推奨している会社にもかかわらず、現場にもっとも行っている会社で、フル出社の会社ですとよくネタにするのですが、フル出社することを考えると社員が通いやすい場所、かつ行きたいと思えるオフィスにする必要があると考えました。そこで丸の内であれば、どこからでもアクセスしやすい。社員採用への応募で通勤をネックとして捉えられることもないので、社員のリテンションのためと考えたときに丸の内が最適でした。
――働く現場としての魅力はありますか?
中川氏:丸の内は働く場所としてはとても便利だと思っています。交通手段も多く出張にも行きやすいし、取引先の会社にいくのも1本の路線で行けることが多くて、乗り換えても30分以内で着けるという利点があります。東京駅から東海、東北、北陸もすべて行けますし、海外出張時には成田や羽田にも行きやすい。さらにいうと、地下街でつながっているので雨に濡れずに移動できる快適さがあります。
また、飲食店も近くにたくさんありますし、ちょっとうれしいのは、たとえばお土産がほしいとか、家族向けのプレゼントがほしいというときに周りに選択肢がたくさんあることです。他ではちょっと買物と思っても移動で小一時間かかったりすることもありますが、丸の内は選択肢が多いのでこれまでに渡したものと被らないものも選べる。そうした選択肢が多いのはすごく魅力的です。
――他の地域は検討しなかったのですか
中川氏:以前、IT系に人気の町の会社にいたことがあるのですが、たとえばランチを食べに外へ出るたびに往復するのに時間が取られて食べる時間が少なくなったり、雨だと出掛けるのも億劫になったりしました。その点丸の内は地下街も充実していて、会社周辺だけで完結できる。毎日のことなので、小さな積み重ねではありますが、そのような快適さがとても気に入っています。
――ビジネスという視点ではいかがでしょうか
中川氏:経営者としては、丸の内に本社がある企業が多いので、すぐに会いに行けるということはありますね。あと、スタートアップなので、僕らが訪問しなければいけないところ、来ていただけるケースが多いですね。今入居しているInspired.Labは大手企業とスタートアップのコラボレーションを支援しているので、そうしたつながりで起業当初加速できたのは大きかったです。また人の採用のしやすさもあるので、採用費用を抑えられます。人が集まりやすいですし、辞める人も少ない。そうした案件獲得にかかる費用、採用費用などを踏まえると費用対効果も高いと思います。
――丸の内はスタートアップ企業にいいところでしょうか
中川氏:スタートアップで大事なことは10分、15分という時間をいかに有効活用するかがもっとも重要だと考えています。丸の内はそれを実現できる場所です。さっとランチに行ける、買物ができる、顧客にすぐ会いにいける。またイベント会場もたくさんあるので、イベント開催時に困ることもない。細かいところですが一つ一つで時間が節約されています。スタートアップは時間との勝負。だからこそ丸の内でブーストできるのは大きな価値があります。
――最後にこれを読んでいる方にメッセージをいただけますか
中川氏:僕らは『すべての人が時空を超えて働ける世界へ』というのをビジョンとして掲げています。現在はブルーワーカーを中心に遠隔化を手掛けていますが、今後は働きたいけど働けない方、たとえば高齢になって現場には出られないけど在宅なら働けるという方や、ケガで外出できない、障がいがある、そのような方々も参画できるようなプラットフォームを育てていきたいと考えています。建設や製造といった現在の領域にとどまらず、誰もが場所や身体的制約にとらわれずに働ける仕組みを早期に実現していきます。
――ありがとうございました
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう