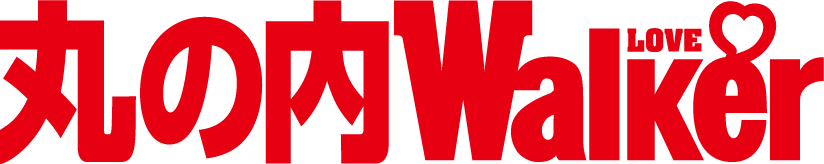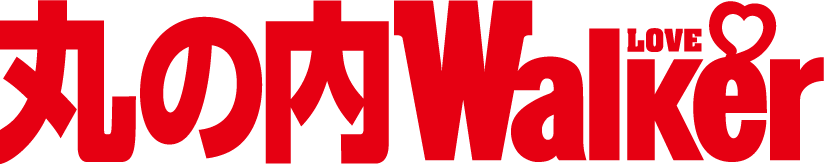アップデートする街・丸の内のストリートを彩る新作アートを深堀りレポート!
2025年07月17日 12時00分更新
丸の内仲通りを中心にアート作品が展示され、街なかでいつでもアート鑑賞ができる環境を私たちに提供してくれる「丸の内ストリートギャラリー」。実は1972年からスタートしていて、50年以上の歴史があります。
ここでは、時代のニーズに合わせて定期的に新作が設置されたり、作品の入れ替えが行われていて、いつでも“旬”なアートが見られるんです。
今回、3年ぶりに新作の設置と、一部作品の入れ替えが行われた「丸の内ストリートギャラリー」。新たに丸の内を彩ることとなった作品を早速観てきました!
都市に現れる2つの大きな顔
まずご紹介するのは、中村萌さんによる新作「Whirling Journey」という作品。
都市のなかにどーんと異質なものが現れるような存在感があり、今回新たに展示された作品のなかでも、一番パッと目をひく作品に感じます。実際、仲通りを歩く人たちのなかにも、足を止めてじっと見入っている人がたくさんいました。
そんなインパクトの大きな作品ですが、2つの顔のやわらかであどけない表情や、あたたかみのある色遣いにはホッと心が落ち着きます。仕事で忙しい時なんかも、合間にこの作品を観れば癒されそう。
この作品は、もともとは木彫りで造られた彫刻作品から型を取り、ブロンズ作品として鋳造したものだそう。7月8日に開催されたプレス説明会で、中村さんは「この作品は素材となった丸太の形を活かしています。少し右に傾いているような形も、もとの丸太の形そのままです」と話します。木という自然の素材を感じられる作品だからこそ、より温かみのある作品になっているのかもしれません。
地底の営みが大地に現れる
続いてご紹介するのは、山本桂輔さんの新作「眠りながら語らい、歌う」という作品。
6つの土台に、それぞれ彫刻が載っています。土台となっている丸太は本物の木。山本さんは「展示期間は約3年の予定ということなので、土台の木がどのように変化していくかは分かりません。変化しないものはないと思うので、この作品が、日々変化していく街とどう対話していくかも含めて見ていきたいです」と話します。
それぞれの彫刻は、真ん中の一番大きな人は王冠をかぶっていたり、キノコのかさの上に顔があったり、鳥小屋があったり。1つ1つが可愛らしくも少し奇妙な雰囲気がある作品です。6つの物体それぞれにどんな関連性があって、どんなストーリーがあるんだろう…と、作品を眺めながら想像が膨らみます。
山本さんはキノコをモチーフとした作品を多く制作していて、「キノコは地底にある菌糸体が本体で、菌糸が集積されて形作られたものがキノコとして地表に現れています」と話します。この作品も地底での生命の営みを大地、空へと繋げていくものだそう。
彫刻で気づく虫の美しさ
3つ目となる新作は佐藤正和重孝さんの「Symbiosis(共生)」。
日頃から甲虫をテーマにした作品を多く作っている佐藤さん。「丸の内の屋外に作品を展示することになり、まず思ったのは都会にないものを出現させたい、ということでした。私は都会はきれいすぎると思っていて、そこに虫を持っていきたいと思って制作しました」と話します。
真ん中にいるのはフンコロガシ。「フンコロガシがフンを転がす姿はユーモラスですが、彼らは大真面目ですし、その行為は実は環境にも役立っていて、とても美しいものでもあると思います」と話す佐藤さん。
私はどちらかというと虫は苦手です。ですが、虫を愛し、その美を見出す佐藤さんの目を通して造り出されたこの作品は、虫たちの造形のカッコよさや美しさを気づかせてくれるものとなっています。
力強くも繊細なガラス作品
最後にご紹介する新作はイワタルリさんの「No.2506031」。
岩田ガラスの3代目であるイワタさんは、親に言われて後を継いだわけではなく、子供の頃から溶けたガラスが大好きで、自然とこの道を選んだと言います。
イワタさんが作品を作る時に意識しているのは「人間の存在感を感じること」。「戦争から6年後に生まれた私は、戦争のことを意識することも多く、戦争には強く反対します。自分の存在感を感じ、他者の存在感を感じ、それを互いに尊重することが大事です。ですが、戦争はそんなお互いの存在感を殺し合うことです。戦争に反対し、互いの存在感を大事にしていく、ということが常に作品の根底にはあります」と話します。
鋳込みガラスによる今回の作品は、6つの柱状のガラスが並びます。どっしりと構える力強さもありつつ、ガラスという素材の繊細さも感じられるこの作品。なんといっても淡い緑の色合いがきれいで、屋外展示ということもあり、日に透ける色味が美しいです。時間帯によって見え方も変わってきそうで、これぞまさにパブリックアートの醍醐味ではないでしょうか。
6つのガラスはぱっと見は同じように見えても、よく見るとヒビの入り方などが全く違っています。イワタさんのお話を聴いた後だと、それぞれが尊重されるべき個性を持った人間のような存在にも感じられました。
都市のなかの緑と調和する作品たち
今回新たに、彫刻の森美術館のコレクションから3点の入れ替え作品の展示もスタート。彫刻の森芸術文化財団 東京事業部長 坂本浩章さんによると、今回の展示のテーマは「都市の森に佇むいのちの協奏」。「丸の内仲通りは都会とは思えないほど木々が多く、江戸時代からの生態系が残る皇居が隣接した緑豊かな場所です。そのようなエリアを意識して、自然や大地からの恩恵、人と自然の強い生命力をアートで発信できればと思いました」と話します。
1つ目の作品は、イタリアの作家ウンベルト・マストロヤンニの「幸運の木」。
ウンベルトは戦後イタリア彫刻界を代表する巨匠の一人。この「幸運の木」は、戦後まもなくの悲壮感から脱却・再生し、生命に明るい希望を見出しているような作品です。木をモチーフにした作品が、実際に木のある空間で観られるというのもパブリックアートのおもしろいところですよね。
続いては、八ツ木のぶの「象と人(雷)」。
貫くような1本の赤い棒状のオブジェクトがまさに雷を思わせます。力強さを感じさせる作品です。
最後に、ポーランドの作家マグダレーナ・アバカノヴィッチの「群衆の一人」。
個性は剥ぎ取られて群衆のなかに埋没しながらも生き残る人間の不屈の意志が伝わる作品。都市のなかで生き、多くの人のなかで自分を見失いそうな時にも力を与えてくれそうな作品です。
ご紹介してきた現代作家による新作4点、入れ替え作品3点に加え、継続作品10点の計17の作品が展示されている「丸の内ストリートギャラリー」。仕事の合間に、ショッピングやランチのついでに、仲通りを散歩しつつアートで心を潤わせてみませんか?
丸の内ストリートギャラリー
展示場所:丸の内仲通り、丸の内オアゾ前、一号館広場(三菱一号館美術館)

文 / オシミリン(LoveWalker編集部)
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう