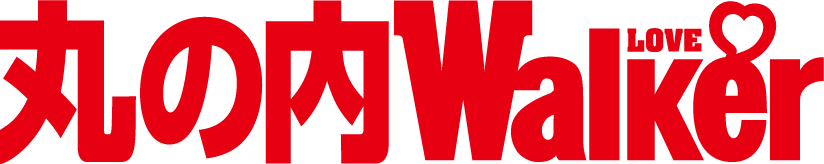圧巻の西洋建築を誇る東京ステーションホテル その100年の歴史を守り100年先を見据える丸の内びと―― 八木千登世さん
2025年09月25日 12時00分更新
日本において「使われ続ける重要文化財」の希少性
一度は壊して高層ビルに建て替える計画もあった東京駅の赤レンガ駅舎。しかし「残したい」という市民や専門家の声が高まり、1999年に保存・復原が合意された。2003年には重要文化財に指定され、2007年から大規模な工事がスタート。歴史ある建物を「使いながら守る」ことで、駅もホテルも新しい形で甦った。
――そんな中で大きなターニングポイントになったのは、重要文化財になったこと。そして、ドームが再建されたことですよね。
八木「国鉄、JRの中で1970年代、80年代、90年代と何度もこの古い駅舎を壊して、近代的な高層ビルを建てようという計画がありました。ただ、日本建築協会や市民団体の方々によって『この赤レンガを守っていきたい』という声がどんどん大きくなり、社会問題にも発展するんですね。
その後、1999年にJR東日本と都知事がここを保存復原しようと合意をして、2003年に 国の重要文化財に指定されました。保存・復原工事に着工したのがその4年後の2007年。ホテルは2006年の3月までで一旦クローズしましたので、6年半休業していました」
――国民の声って大切ですね。
八木「本当ですね。この姿が残っていてよかったと思います」
――90年代ぐらいから2000年にかけて、丸の内をオフィス街から一般の人のための街にしようということで、煉瓦造りの三菱一号館美術館が作られたり、東京中央郵便局もビルにはなりましたが元の建物を残したりだとかしましたよね。東京駅が重要文化財として赤レンガの姿で復活したことが、この街全体の空気の軸だったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか?
八木「重要文化財として今でも使われているものは、明治生命館や高島屋などがありますね。ただ、いわゆる駅であり、ホテルであり、そして美術館でありという複合施設としての重要文化財の活用というのは、ここが見本になる……保存復原工事のミッションでした。
日本は木の文化なので、古くなったら壊して新しいものを建ててきましたね。そういった意味では、こういったモダン建築や近代建築を使い続けるという例が少ないんですね。歴史的建造物は残っていても、ほとんどが眺めるだけの博物館のような形なので、実際は使われていないことが多いです。保存復原工事のプロジェクトリーダーの田原幸夫先生は、建築というのは使ってこそ価値があるということをおっしゃっており、まさにロールモデルになるべきプロジェクトだったと思いますね」
――すごく重要なテーマですよね。さまざまな施設をどうするかという時に、必ず議論になりますから。その中でも東京駅はすごいロールモデルだと思います。
八木「壊して一から造る方がよっぽど簡単ですし、保存にはお金も手間もかかりますからね。ですが、残すことの価値を考えたときに、このように歴史や文化を守っていくことは大切なのだという啓蒙になると思うのです。本当に重要な役割を持っていると思います」
開業110周年を迎えて感じるイギリスとの深い縁
――そうしてリニューアルオープンを果たされたわけですが、コンセプトはどういったものだったんでしょうか?
八木「保存復原工事で駅舎を創建当時の姿に復活させようというプロジェクトの中で、ホテルはどうするべきかという議論がありました。やはり東京の中心にあって日本の玄関口であるという地の利の良さプラス、重要文化財であるということの希少性を組み合わせて、唯一無二のオーセンティックのホテルを作っていこうという基本方針ができたのです。それまでにあったホテルとは違う方向性で、 格式を持った日本の顔となるようなホテルを造ろうと一新することになりました」
――内装が特徴的で、カーテンやカーペット、椅子もそうですけど、美的な感覚でコンセプトがすごく統一されているなと感じます。
八木「 デザインのコンセプトはヨーロピアンクラシックです。再開業にあたってコンペを行ったのですが、最終的に残った数社すべてが偶然にもイギリスのデザイン会社でした。採用されたのはリッチモンドインターナショナルで、ヨーロッパの古城や文化財をラグジュアリーホテルに改装することを非常に得意とする会社なんですね。 日本での施工例は他にはありません。
そもそも駅舎を設計した辰野金吾は、建築の国賓留学生第一号 としてイギリスのロンドンで勉強しています。不思議とつながりますよね。2年間ロンドンで勉強し、その後フランスなどヨーロッパをまわって、その知識で日本各地にたくさんの近代建築を作っていくわけです。建物自体がイギリスの影響を受けていますので、ホテル再開業の際に選ばれたインテリアデザインがイギリスの会社によるものというのは当然だったのかもしれないですね」
110周年の節目にふさわしく、館内は特別な企画で彩られている。イギリスのリバティ社とのコラボレーションによる「リバティルーム」、限定のカクテルやオリジナルグッズ、そしてスタッフ全員が身につけるパープルバッジだ。
――110周年のお話も伺いたいのですが、リバティとコラボレーションされるんですね。
八木「まさに先ほどのイギリスの話と繋がっているんですが……。実は以前にもブランドのコラボレーションをやっていて、いずれもイギリスの会社だったんですね。これまでにスーツケースブランドのグローブ・トロッターと、ローラアシュレイとコラボレーションしました。
リバティも今年ちょうど150周年を迎えていまして。日本でも昔からリバティは有名ですし、お花柄の生地のイメージがある方も多いと思います。
小物や服といったファッションファブリックとしてのリバティは以前から日本にありましたが、インテリアファブリックとしてのリバティが日本へ上陸したのは一昨年のことなのです。 壁紙ですとかカーテンですとか、ダイナミックに使われるファブリックに関しては、日本での取り扱いは始まったばかり。大阪ではちょうど万博があり、イギリスパビリオンにもちょうどリバティのインテリアファブリックが採用され、日本の東と西で同時期にお披露目する機会に恵まれました。 ホテルのお部屋そのものもイギリスの会社がデザインしていますので、インテリアと非常にマッチするんですよね。 そこがやっぱり大きなコラボレーションのポイントかと思います」
特に注目なのがリバティルームだけのサービス。2部屋しかなく、一つは淡いピンクで優しい雰囲気の部屋、もう一つはボタニカルでエキゾチックな部屋になっている。そんな空間でゆっくり過ごせるよう、リバティルームでだけ、部屋でのアフタヌーンティーが楽しめるのだ。
八木「ご自分だけの世界で、ご自身のペースでゆったりとお茶を飲んでいただいて、空間を楽しんでいただければと思います。 それが一番の楽しんでいただくポイントかなと思っています。先々であれば予約もまだ取れますし、110周年を機にこのお部屋を作り、しばらくは定番にしたいという考えはあります」
――110周年の取り組みは他にもたくさんあるんですよね!
八木「2つのリバティルームをイメージしたカクテルを販売中です。秋田・五城目町の希少なフレッシュなラズベリーを使用していて、10月15日までのご提供となります」
――カクテル繋がりで、「バー&カフェ カメリア」や「バー オーク」といった東京ステーションホテルさんのバーは本当に素晴らしいですね。シグネチャーカクテルも有名ですね。
八木「ありがとうございます。オークにしてもカメリアにしても再開業前からずっとあるバーです。今はお休みしておりますが84歳の伝説のバーテンダー・杉本壽が作った『東京駅』というカクテルもございます」
発売以来人気のステーショナリーセットも110周年特別仕様に。駅舎が描かれたカードと封筒が入った「メッセージカードセット」と、メモ用紙とボールペン、ステッカーが入った「文豪セット」の2種類がある。
八木「2つのボックスを並べるとホテル全体のイラストが完成するんです。ホテルの前をハイカラさんもいればスマホを持っている人も歩いていて、110年の歴史と時代を感じられます。
文豪に愛されたホテルでもありますので、『文豪セット』には原稿用紙モチーフのメモが入っております。このメモ、客室のベッドサイドにも設置しているんですよ。丸い形のステッカーは東京鉄道ホテル時代のデザインです」
――アールデコ風のデザインがすてきですねえ! ところで皆さんがつけられているパープルバッジが気になるんですが。
八木「開業110周年を記念して作られたアイテムで、全スタッフが着用しています。館内でお声がけいただけましたらどなたにでも差し上げています」
今年から1階のロビーラウンジではアフタヌーンティーの提供をスタートした。これまでは夕方に楽しむハイティーのみだったが、ティータイムものんびり過ごすことができるのは朗報。午後はフレンチトーストにするかアフタヌーンティーにするか、ぜいたくな悩みを抱えることになりそうだ。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう