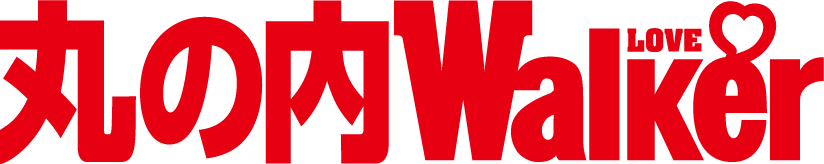丸の内の隠れたレジェンド!再開発第一世代、「オフィスの丸の内」 を代表する「三菱ビルヂング」
2025年10月10日 12時00分更新
三菱ビルヂングの建設
三菱ビルヂングは、三菱グループの象徴的な存在として建っていた「三菱本館」を含むビルの建て替え事業で誕生しました。丸の内の一画に残されていた三菱本館のブロックは、東半分に1918年竣工で第22号館として建てられた「三菱本館」と1921年竣工のその増築部分、西半分に1964年竣工の三菱重工ビルおよび1937年竣工の旧三菱商事ビルが立地し、長らく三菱の本拠地として機能していました。三菱本館は竣工から半世紀を経ても堅牢で使用に耐えましたが、時代はより高層で効率的なオフィスビルへと移りつつありました。
戦後、三菱化成工業をはじめとする入居テナント各社から増室要望が寄せられ、さらに三菱商事からも旧社屋を建て替えて共同利用ビルを建設したいとの意向が示されたことから、三菱地所は1971年3月にブロック全体の再開発を決定します。これにより、三菱本館(増築部を含む)の建替えと西側に旧三菱商事ビル解体後の三菱重工ビル増築が並行して進められることになりました。
1971年9月6日に着工された「三菱本館改築工事」は、建築主と設計は三菱地所、施工は清水建設と竹中工務店、大林組によって行われ、1973年3月28日に竣工を迎え、新たに「三菱ビルヂング」と名付けられました。完成した建物は地上15階、地下4階、延床面積61,137㎡を誇る大規模ビルで、同時に西側の仲通り側で完成した三菱重工ビル増築部分とあわせ、ブロック全体の床面積は約10万7,000㎡に達しました。両ビルは低層階で一体化しつつ、高層部は切り離す設計を採用し、都市景観との調和を図っています。三菱ビルヂングには三菱化成、三菱油化、三菱モンサント化成、三菱瓦斯化学、三菱樹脂といった化学系5社が主に入居し、再びグループの中核拠点として機能しました。
また、この建設に際しては都市環境への配慮も重視されました。東側の東京中央郵便局寄りの敷地を幅7m・長さ100mにわたり公共歩道(現在でいう歩道状空地)として提供し、緑化を施して有楽町方面と東京駅方面を結ぶ快適な歩行空間を創出しました。さらに、丸の内地区における本格的な地域暖房事業も開始され、三菱ビルヂング地下に設けられた集中暖房センターを拠点に周辺のビルへ熱供給を行う公益事業が展開されました。この取り組みは、丸の内二丁目地区全体へ広がり、現在の供給エリアの総面積は約14.6ha、供給延床面積は約123万㎡へと拡大し、先進的な都市インフラの一例となりました。
三菱ビル完成により、丸の内総合改造計画は事実上完了し、30棟に及ぶ旧建物が取り壊され、かわって13棟の近代的高層ビルが建設されました。更に、仲通りの拡幅や緑化とともに、丸の内は世界有数のビジネスセンターへと姿を変えています。新しい三菱ビルヂングは、かつての財閥本拠地の重厚さを受け継ぎながら、現代的な都市空間の中核として新時代を象徴する存在となりました。

「三菱ビルヂング」と西側の「丸の内二丁目ビル」は1階の貫通通路で接続されており、まちの賑わいや回遊性を創出するリニューアル「Marunouchi Bloomway(丸の内ブルームウェイ)」により通路には季節の植物で彩った花壇を配置している
以上で今回の建築ツアーは終了。建て替え前の第22号館では、現在でいうコンペが採用されたり、国内で初めてスチールサッシが採用されたりと、戦前も戦後もかなり時代に先駆けたビルとして建てられたことが分かります。その前衛的な姿勢は、丸の内二丁目地区の地域暖房事業や「Marunouchi Bloomway(丸の内ブルームウェイ)」などにも引き継がれていますし、これからもこのエリアを引っ張っていくのではないでしょうか。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう