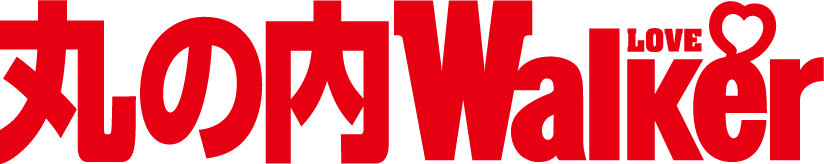エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀のアート散歩 第35回
安藤忠雄建築にどっぷり浸かる超プレミアムなツアーを体験。大阪・神戸・淡路・直島を巡った3日間はかつてないアートの旅だった
2025年07月14日 18時00分更新
「瀬戸芸美術館連携」プロジェクト公式ツアー、安藤忠雄建築鑑賞コース(大阪・神戸・淡路・直島 3日間)の主役はもちろん、世界的な建築家であり、その個性的人柄で多くの人を惹きつける安藤忠雄氏だ。
現在、大阪のVS.(グラングリーン大阪)で個展「安藤忠雄展|青春」(2025年3月20日〜7月21日)を開催中の世界的な建築家、安藤忠雄氏には、筆者はシュシュや関西ウォーカーなどで、大変お世話になった。表参道ヒルズ(2006年竣工)や、同じく「桜の会・平成の通り抜け」プロジェクト(2004年~)など、安藤氏の精力的な活動を追いかけ取材し、多くの記事を作ってきた。
安藤氏の建築は日本国内はもちろん、ヴェネツィア(イタリア)やエクス=アン=プロヴァンス(フランス)など、枚挙にいとまがないが、今回のツアーの直島、淡路島、神戸、大阪は、その中でも極めて重要で大規模な作品(と言うよりはエリア、ゾーンと言うべき取り組み)が知られており、改めて、プレスとして一足早く回ってみて、安藤氏のスピリットに感動した。
今回のツアーでは3個の大きな青りんごに出会えたのも嬉しかった。このオブジェは、安藤氏が設計した建築物や展覧会で頻繁に登場し、彼のメッセージ「いつまでも挑戦心を持ち続けること」を体現している。安藤氏は、米国の詩人サムエル・ウルマンの詩「青春」(Youth)に着想を得て、「青りんご」に「永遠の青春」という想いを重ね合わせた。
この詩は「青春とは年齢ではなく、心の状態であり、挑戦心や希望を失わないこと」と説いている。安藤氏は「熟した赤いりんごではなく、未熟で酸っぱい青いりんごのように、常に挑戦し続ける精神」を表現しているのだ、と言う。青りんごは、直径約2〜2.5mのオブジェで、繊維強化プラスチック(FRP)製。 台座にはサミュエル・ウルマンの「青春」の詩と安藤のメッセージが刻まれ、訪れる者に「挑戦心」と「希望」を伝えている。
「瀬戸芸美術館連携」プロジェクトは、2025年4月18日から開催されている瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸) 2025の広域連携事業として、瀬戸芸の会期中を中心に、香川・岡山・兵庫3県の8つの美術館で、日本人の現代アーティストによる作品を中心とした14の展覧会を順次開催していく。
参加している美術館は、香川県が4館(香川県立ミュージアム、高松市美術館、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館MIMOCA、直島新美術館)、岡山県が2館(岡山県立美術館、大原美術館)、兵庫県が2館(兵庫県立美術館、横尾忠則現代美術館)。
瀬戸芸とほぼ同時期に大阪・関西万博が開催されており(2025年4月13日~10月13日)、海外からの観光客も瀬戸内に多く来ることを期待し、最先端の現代アートやそれぞれの地域の文化・魅力を発信するため、8館共通の割引チケットを発売し、周遊ツアーも催行する。瀬戸内からアートのメッセージを発信し、瀬戸内がアートの聖地として位置づいていくことを目指す。
また、対象展覧会を効率的に周遊できる5種類のツアーを設定している。
近隣の美術館を回るツアーと、アーティスト別のツアーがあり、全てのコースに通訳案内士が同行する。いずれも初日は朝、士新大阪・岡山を出発し、最終日の夕刻に岡山・新大阪に戻る行程で、美術館だけでなく周辺の観光も含まれている。その土地ならではの食事、人気の宿泊先を楽しめる。
旅行代金は250,000円(ツインルーム)〜310,000円(シングルルーム。それぞれ、おとな・一人)。筆者はツインルームで体験したが、正直安いと感じた
安藤忠雄建築鑑賞コース(大阪・神戸・淡路・直島 3日間)は、すでに受付の終わった一本目の7月15日出発以外に、7/23の2本目以降が募集中。現在、募集をしている安藤コースは、7/23(水)発、7/29(火)発、9/17(水)発、10/7(火)発、10/29(水)発、11/5(水)発、11/11(火)発、11/20(水)発の都合8本となる。*9/23発は売り切れ
●旅行代金
250,000円〜310,000円(大人・1名)
・2名一室 大人1名250,000円(ツインルーム )
・1名一室 大人310,000円(シングルルーム)
・こども同額
筆者はツインルームを体験したが、この料金を高いと思うか、妥当と思うかで言えば、十分価値があると言いたい。以下が日程だが、個人で、この内容、濃度の安藤ツアーを体験するのは容易ではない。安藤忠雄建築の神髄を一気に体験できるコースは得難い。
安藤氏には、街中や空港でひょっこり会うこともたびたびあり、関西ウォーカーの編集長をしていたときは、新しい建築が出来るときにファックスを頂いたりしていた。もはや、偉人と言うべき人だが、本当に変わらない。海外に行って、建築に触れたり、展示を見たりして、改めてすごさに気づくことも。この3日間は間違いなく特別な時間になる。
●コース
1日目
JR新大阪駅― うめきた「VS.」(鑑賞)― こども本の森 中之島(鑑賞)―神戸(昼食)― 兵庫県立美術館(鑑賞)―国営明石海峡公園・淡路夢舞台(鑑賞)―淡路島(夕食・泊)
☛宿泊先 グランドニッコー淡路(スーペリアツイン 39㎡)
2日目
ホテル(朝食)― 本福寺水御堂(鑑賞) ―高松(昼食)―高松港~(フェリー)~宮浦港― ANDO MUSEUM(鑑賞)・家プロジェクト(na11B 角屋・na12B 護王神社、na13-B 南寺など鑑賞)… 直島新美術館(鑑賞)―直島(夕食・泊)
☛宿泊先 ベネッセハウス パーク棟(パークツイン 28㎡)
3日目
ホテル(朝食)― ヴァレーギャラリー(鑑賞) … 李禹煥美術館(鑑賞)― ベネッセハウス ミュージアム(鑑賞・昼食)- 地中美術館(鑑賞)―宮浦港~(フェリー)~宇野港―JR岡山駅16:30頃+(新幹線)+JR新大阪駅17:35頃
旅行代金には以下のものが含まれる。交通費(片道新幹線運賃・貸切バス運賃・高速道路料金・駐車場料金・フェリー乗船料)、添乗員料金・通訳ガイド料金、宿泊代、昼食代、夕食代、鑑賞料、旅行特別補償保険料。
*集合場所まで、解散場所からの交通費は含まれない。
【VS.(グラングリーン大阪、大阪市) 個展「安藤忠雄展|青春」(会期終了後は、建物の外周の見学になる)】
個展の会期は2025年3月20日〜7月21日。大阪では16年ぶり、2017年に東京・国立新美術館で30万人を動員した「安藤忠雄展|挑戦」に続く安藤忠雄氏の大規模個展になる。
今回のツアーでは、VS.の展覧会終了後は、建物内には(その時のイベント内容による)基本的には入らずに、外周とグラングリーン大阪と安藤氏との関係が紹介される。
会場の「VS.」は安藤氏が設計監修した(設計・監理:日建設計)。2024年9月にオープン。安藤氏は、VS.の設計において、うめきた公園の緑を最優先に考え、建築の存在感を最小限に抑えつつ、力強い空間を創出した。
建物の大部分を地下におさめ、少し出っ張ってしまったコンクリートは緑で覆ってしまおう、と言うコンセプト。うめきた公園の緑豊かな環境を損なわず、建築を風景に溶け込ませ、地上のコンクリートキューブは緑で覆われ、公園の一部として調和させる。 地下の大空間には、15mの天井高を持つ展示空間を実現し、コンクリート打ち放しの壁と自然光を活用している。
「安藤忠雄展|青春」は、安藤氏の建築哲学や人生観を「青春」というテーマで紐解く展示。彼の代表作や未公開資料を通じてその軌跡を体感出来る。初期作品から最新作までを、模型、図面、写真、映像で展示している。住吉の長屋(1976年、大阪)、光の教会(1989年、大阪)、地中美術館(2004年、直島)、こども本の森 中之島(2020年、大阪)などの代表作をはじめ、海外作品も紹介され、ヴェネツィアのプンタ・デラ・ドガーナやアメリカのフォートワース現代美術館などが含まれる。
北海道の「水の教会」(1988年)をほぼ原寸大で再現。自然光と水面が織りなす静謐な空間を会場内で体感できる。安藤氏の「光と自然」を活かした設計思想に浸れる。実際に水が張られた水盤に立つ十字架。その背景のパノラマ映像では、雄大な自然の四季の移り変わりが流れ、時折聞こえる鳥のさえずりや自然の音が、遠く北海道の建築へと観客をいざなう。
また、安藤氏は大阪市内の会場に近いところに事務所を構えていることもあり、ゲリラ的に突然、会場に現れて急遽サイン会を開くこともしばしば。筆者は、取材の日に、兵庫県立美術館の特別展「藤田嗣治×国吉康雄: 二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」 (6月14日~8月17日) の内覧会で会っていたのだが、その後、訪れたVS.に来られてサイン会を開き、筆者もゲットした。
天井高15mのスタジオでANDO建築を没入体験できるゾーンは五感で楽しい。代表作「光の教会」、雄大な丘から大仏様の頭がのぞく「真駒内滝野霊園頭大仏」、そして歴史的建造物を保存再生し現代アートの美術館に生まれかわらせた「ブルス・ドゥ・コメルス」。天井高15mのキューブ型スタジオで展開するオリジナルの映像により、この3作の建築空間を疑似体験できる。
「安藤忠雄の現在」エリアでは、最近作と共に、進行中の仕事を「37年目の直島」「時間をつなぐ」「つくる/育てる」「こども本の森」「都市ゲリラ2025」「大阪から」の6つのテーマに沿って紹介している。 福武書店(現・ベネッセホールディングス)の福武總一郎氏の構想でスタートした直島のアートプロジェクトでは、安藤氏は、その最初期から今日まで建築家として関わり続け、「ベネッセハウス ミュージアム」から5月末に開館の「直島新美術館」に至るまで、10もの建築を実現している。
■公式サイト
https://vsvs.jp/exhibitions/tadao-ando-youth/
【こども本の森 中之島(大阪市)】
2020年7月開館。安藤氏が大阪市に寄附した施設。乳幼児からたのしめる絵本や幼年童話、児童文学、小説、各分野の図鑑、自然科学書、芸術書など様々なジャンルの本に対しニュートラルに接してもらうため、新しい手法で丁寧に本を差し出す。 ここでは本の対象年齢に縛られすぎず、こどもたちが素直にものを見る眼差しや豊かな感受性を何よりも大切にしたいと考えている。蔵書数は約20,000冊(絵本、幼年童話、児童文学、小説、図鑑、自然科学書、芸術書など多様なジャンル)。
コンクリート打ち放しとガラスを用いたミニマルなデザイン。自然光が差し込む開放的な空間で、中之島公園の緑や堂島川の水辺と調和している。3階建ての構造で、中央に吹き抜けがあり、螺旋階段や大きな窓が特徴。子どもが動き回れるよう、遊び心のある空間設計になっている。外観には「青りんご」のオブジェ(直径約2m、FRP製)が設置され、安藤の「青春」の哲学を象徴している。
従来の図書館の分類ではない独自の分類が直感的に分かりやすく、本の一節を立体的に見せる展示も面白い。
奥まった部分にある円筒形の部屋は遊び心溢れる空間。映像で本の世界に誘ってくれる。
■公式サイト
https://kodomohonnomori.osaka/about/
【兵庫県立美術館(神戸市)】
安藤忠雄氏設計。前身である兵庫県立近代美術館(1970年10月創建)の活動実績とコレクションを受け、開館は2002年4月。HAT神戸エリアにある。1995年の阪神・淡路大震災後、神戸の復興を願い、安藤氏が注力したプロジェクト。
神戸の海辺に位置し、海を望む「海のデッキ」や水辺のテラスが特徴。自然光と水面の反射を活かした設計になっている。大きなガラス窓や吹き抜けを通じて自然光が内部に差し込み、展示空間に変化と生命感を与えている。円形テラスは各展示棟とギャラリー棟、そして海と山をつなぐ美術館のシンボルになっている。
美術館は、被災地に新たな文化的拠点を提供し、地域の再生を象徴し、海と空を背景に、コンクリートとガラスが自然環境と調和している。安藤氏の「建築は自然と対話する」という哲学を見ることが出来る。
美術館の屋外「海のデッキ」に、直径約2.5mの「青りんご」オブジェ(繊維強化プラスチック製)が設置されている。
特別展は、「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア-百年目の再会」(6月14日〜8月17日)。「瀬戸芸美術館連携」プロジェクトの対象展覧会でもある。20世紀前半の激動の時代、海外で成功と挫折を経験した二人の日本人画家、藤田嗣治(1886年〜1968年)と国吉康雄(1889年〜1953年)の展覧会。それぞれフランスとアメリカに渡った二人は、その地で画家としての地位を確立した。パリとニューヨークで交流したことでも知られているが、太平洋戦争で大きくその立場が隔たることとなった二人の作品を画期となる時代ごとに展示している。
■公式サイト
https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2506/index.html
●Ando Gallery(兵庫県立美術館2階/入場無料)
安藤氏からの建物の寄贈、展示物の一部寄託により2019年5月、Ando Galleryが兵庫県立美術館内に新たにオープンした。安藤氏の建築模型(住吉の長屋、光の教会、ブルス・ド・コメルス等)やドローイングなどを紹介している。こちらも「瀬戸芸美術館連携」プロジェクトの対象。
既存の免震構造の建物の上に、増築するという難題に対して、免震装置に手を加えることなく、約600㎡の展示室を増築した。増築部は鉄骨造とし重量増分は約0.6%であり既存建物への影響はほとんどない。美術館の二つの棟の間に浮くように作られているが、増築にあたり、免震層の吸収エネルギーの確認や、免震装置取付き部の検討、杭の地盤応答変位の影響などの検討を追加で行い、大臣認定を再取得して現行基準を満たすことを確認した。
2・3階部分にあたる第2展示棟は、吹き抜けの大きな空間が山のデッキへと続き、「りんご」が置かれた海に向かうテラスへ外部通路で直結している。
●青木野枝《Offering / Hyogo》
阪神・淡路大震災30年の屋外彫刻作品。2025年1月公開。2025年1月17日に阪神・淡路大震災から30年を迎えるのを機に、公益財団法人伊藤文化財団からの寄贈により、青木野枝の作品《Offering / Hyogo》が兵庫県立美術館の屋外4階スペース<風のデッキ>に設置された。
山側には摩耶山頂が見える六甲山系があり、海側は入り江となった海が見え、山側と海側の間を風が吹き抜ける。
【淡路夢舞台(淡路島)】
兵庫県の淡路島に2000年3月9日、国際園芸・造園博「ジャパンフローラ2000」の会場として開業。関西国際空港などの大阪湾埋め立て用土砂採取で荒廃した淡路島北部の灘山(標高160m)を再生する「環境創造型プロジェクト」として生まれた。1995年の阪神・淡路大震災で計画が一時中断し、さらに敷地内に活断層が発見され、設計を変更し2年遅れで開業した。設計者の安藤忠雄氏は震災復興の希望を込め、「人と自然が共生する舞台」を目指した。
経済活動のために削られた山を、植樹や庭園で本来の自然に復元することを目指し、5年間の植生調査と植樹を行った。100万枚のホタテ貝をリサイクルした「貝の浜」は、廃棄物から美を生み出す安藤の哲学を体現している。自然再生を目的とした「環境創造型プロジェクト」。
約28ヘクタール(280,000㎡)、延床面積は約109,000㎡の敷地に、様々な施設が遊歩道でつながれ、迷路のような冒険心をくすぐる空間を形成している。季節や天候、時間帯で変化する景観によって、訪れる者は多様な体験が出来る。
構成施設は、「グランドニッコー淡路」「海の教会」「あわじグリーン館」(日本最大級の温室)「国際会議場」「百段苑」(100個の花壇が階段状に並ぶ「祈りの庭」)「貝の浜」(100万枚のホタテ貝を敷き詰めた水辺空間)「海回廊・山回廊」「円形フォーラム・楕円フォーラム」「野外劇場」などからなる。
■公式サイト
https://www.yumebutai.co.jp/
●海の教会
十字架型のスリットから光が差し込み、静謐で神聖な空間を創出している。安藤氏の建築では、光の教会や水の教会も連想される。挙式などがなければ自由に見学できる。
●茶室(国際会議場)
床面積は約4.5畳(約8㎡)と非常にコンパクト。伝統的な茶室の「侘び寂び」を現代的なコンクリートで再解釈している。コンクリート打ち放しの壁に、竹や和紙、木材を組み合わせ、現代と伝統の融合を表現している。周辺エリアは、緑豊かな庭園に囲まれ、茶室へのアプローチも自然と一体感のある設計になっている。
【直島新美術館(直島)】
2025年5月31日開館。ベネッセアートサイト直島における安藤忠雄設計のアート施設として10番目になる。安藤氏は、1992年開館のベネッセハウス ミュージアム以降、30年以上にわたり直島の数々の建物を手掛けてきた。丘の稜線をゆるやかにつなぐような大きな屋根が特徴的な建物は、直島の本村地区近くの高台にあり、地下2階、地上1階の3層からなる美術館で、展示スペースは約1,500㎡。
トップライト(天窓)から自然光が差し込む階段室が、地上から地下の4つのギャラリーを結ぶ。カフェテラスは、豊島や瀬戸内海の漁船を望む開放的な空間になっている。焼杉のイメージに合わせた黒漆喰の外壁と石積み塀は、本村地区の伝統的な家屋や集落の景観の特徴とリンクしている。アプローチは、訪問者が集落の歴史や暮らしを感じながら美術館に到達する設計になっている。
日本も含めたアジア地域のアーティストの代表作やコミッション・ワークを中心に展示・収集する。企画展示の開催や、トーク、ワークショップといったパブリックプログラムなど展示以外の美術館活動にも取り組み、より多様な視点や表現、時代や社会に対する多義的なメッセージを発信するとともに、繰り返し人々が訪れ、島内外の多種多様な人々が出会う交流・連携の場としても機能させていく、とのことだ。
直島新美術館が島の数々のアート施設をつなげ、美術館群として捉えることで、より一層自然や集落と一体化したアート体験を創出するとともに、アートと建築、自然、そしてコミュニティの調和・融合のさらなる発展形に期待したい。
■公式サイト
https://benesse-artsite.jp/nnmoa/
●開館記念展示―原点から未来へ
開館記念展示では、ベネッセアートサイト直島の初期から関わりのあった作家や、2016年以降ベネッセ賞をヴェネツィアからアジアへ移行したことをきっかけに関係性を築いてきた作家、さらには近年の現地調査で出会った作家等12名/組による、代表作やこの場所にあわせて構想された新作が、地下2階、地上1階の複数のギャラリー空間やカフェテリア、屋外の敷地に展示されている。
「アートが内包する私たちの生きる時代や社会・環境への鋭い眼差しや問いかけを通して、真に『よく生きる』について考察すること――直島から始まった活動の原点にあるこの思いを改めて確認し、アジアのアーティストたちの作品が放つ様々なメッセージが、未来への希望の手紙となることを願います」と言う(公式サイトから)。
開館年記念展示アーティスト(姓のアルファベット順)
- 会田誠(Aida Makoto)|1965年 新潟県生まれ 東京都拠点
- マルタ・アティエンサ(Martha Atienza)|1981年 マニラ(フィリピン)生まれ バンタヤン島(フィリピン)拠点
- 蔡國強(Cai Guo-Qiang)|1957年 泉州(中国)生まれ ニューヨーク(アメリカ)拠点
- Chim↑Pom from Smappa!Group|2005年 東京都で結成 同地を拠点に活動
- ヘリ・ドノ(Heri Dono)|1960年 ジャカルタ(インドネシア)生まれ ジョグジャカルタ(インドネシア)拠点
- インディゲリラ(indieguerillas)|1999年 ジョグジャカルタ(インドネシア)で結成 同地拠点
- 村上隆(Takashi Murakami)|1962年 東京都生まれ
- N・S・ハルシャ(N. S. Harsha)|1969年 マイスール(インド)生まれ 同地拠点
- サニタス・プラディッタスニー(Sanitas Pradittasnee)|1980年 バンコク(タイ)生まれ 同地拠点
- 下道基行(Shitamichi Motoyuki) + ジェフリー・リム(Jeffrey Lim)|1978年 岡山県生まれ 香川県・直島拠点、1978年 クアラルンプール(マレーシア)生まれ 同地拠点
- ソ・ドホ(Do Ho Suh)|1962年 ソウル(韓国)生まれ ロンドン(イギリス)拠点
- パナパン・ヨドマニー(Pannaphan Yodmanee)|1988年 ナコーンシータンマラート(タイ)生まれ バンコク(タイ)拠点
【ANDO MUSEUM(直島)】
2013年に開館。直島で8番目の安藤建築になる。家プロジェクト(1998年〜)のエリアに位置し、安藤氏はANDO MUSEUMを直島の歴史と自身の建築を融合させ、島民と観光客にプロジェクトの軌跡を伝える役目を持たせている。
直島・本村地区にある築約100年の木造民家の内部に入れ子状に組み込まれたコンクリートボックスは、緩やかな曲面天上を持ち、母屋の木造屋根部分に設けられたトップライトからの光が館内を照らす。過去と現在、木とコンクリート、光と闇といった対立する要素が刺激的にぶつかり合いつつ重層する、小さくとも奥行きに富んだ空間を構成している。
内部の展示は、安藤氏のこれまでの活動を紹介する建築写真や模型やスケッチ、また直島の歴史を伝える写真などが展示されている。
家プロジェクトは、香川県直島町の本村地区で1998年に始まったアートプロジェクトで、ベネッセアートサイト直島の一環として推進されている。直島は、1990年代ごろから過疎化が進み、空き家が増加し、伝統的な木造民家や集落の景観が失われる危機にあった。そこで、空き家をアート空間として再生し、集落の歴史や文化を後世に残しつつ、地域活性化を図る取り組みが進んだ。
■公式サイト
https://benesse-artsite.jp/art/ando-museum.html
【ヴァレーギャラリー】
2022年開館。安藤氏の設計。ベネッセハウスと地中美術館のあいだにある、李禹煥美術館向かいの山間に整備された、境界や聖域とされる谷間に沿うように建てられたヴァレーギャラリーは、祠をイメージした小さな建物。二重の壁による内部空間は内省的である一方、半屋外に開かれることで、光や風など自然エネルギーの動きも直接的に感じ取れる。安藤建築と、周囲の自然や地域の歴史を映し出す作品が響き合い、自然の豊かさや共生、根源的な祈りの心や再生などについて意識を促す。
アートディレクションは三木あき子氏で展示作品は以下の2人。
・草間彌生「ナルシスの庭」1966/2022年(JT International SA寄贈)
・小沢剛「スラグブッダ88 -豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏」2006年(恒久設置)
■ベネッセハウスミュージアム公式サイト
https://benesse-artsite.jp/art/benessehouse-museum.html
【ベネッセハウス】
ベネッセハウスは、香川県直島町のベネッセアートサイト直島内にある、安藤忠雄氏設計のアート施設兼ホテルで、1992年に開業した。美術館と宿泊施設を統合したユニークなコンセプトで、直島のアートプロジェクトの原点として知られている。
香川県香川郡直島町琴反地(ベネッセハウスエリア、南側海岸沿い) にあり、4つの棟(ミュージアム、オーバル、パーク、ビーチ)で構成されている。それぞれの開業は1992年(ミュージアム棟)、1995年(オーバル)、2006年(パーク、ビーチ)。
筆者は角川アスキー総合研究所などKADOKAWAグループの前は福武書店(現ベネッセ)で女性誌の編集をしていた時期があるが、当時から直島の開発は始まっていて、気にはなっていたが行けなかった。KADOKAWAに転職してからはアート系の取材をすることも増え、ベネッセハウスもプライベートでビーチに家族で宿泊したことがある。今回の取材では初めてパークに宿泊したが、まさに、「自然とアートの共生」を体感できる時間を過ごせた。
■ベネッセハウスミュージアム公式サイト
https://benesse-artsite.jp/art/benessehouse-museum.html
●ベネッセハウス ミュージアム(1992年)
美術館とホテルが一体となった施設で、現代アート(主に欧米作家:バスキア、ウォーホル、リキテンスタインなど)の展示が行われている。コンクリートの開放的な空間に、トップライトや大きな窓から海や丘陵の自然光を取り込み、安藤氏の「光と影」の哲学を体現している。ジャン=ミシェル・バスキアの絵画、リチャード・ロングのインスタレーションなどが展示されている。
●ベネッセハウス オーバル(1995年)
丘の上に位置する宿泊棟(6室)。モノレールでアクセスし、360度の瀬戸内海と山の景色を堪能出来る。楕円形の中庭とコンクリート建築が特徴的。プライベートで静謐な空間で、アート作品が客室や共用部に点在している。
●ベネッセハウス パーク(2006年)
海辺の宿泊棟。屋外作品(草間彌生の「南瓜」など)が周辺に点在している。2022年3月12日に、杉本博司氏の多様な作品群を本格的に鑑賞できる「杉本博司ギャラリー 時の回廊」が開業した。
杉本博司ギャラリーは、杉本の直島における長年にわたる取組みが、作家の究極の作品とも言える小田原の《江之浦測候所》の生まれるきっかけとなった経緯から、創作活動のひとつの原点とも言える直島と江之浦を繋げる形で構想された。江之浦測候所が建築と作庭などが中心となっているのに対し、このギャラリーは、杉本博司の代表的な写真作品やデザイン、彫刻作品などを継続的かつ本格的に鑑賞できる世界的にも他に例をみない展示施設になっている。
●ベネッセハウス ビーチ(2006年)
海岸沿いの全室スイート(8室)。開放的なデザイン。アートと自然の融合を強調。客室に作品が配置されている。
【李禹煥美術館(直島)】
香川県直島町のベネッセアートサイト直島内にある同館は、2010年6月15日に開館した。韓国出身のアーティスト、李禹煥のみを展示した美術館で、自然とアート、建築が融合した空間を構築している。海と山に囲まれたなだらかな谷あいに立ち、三角形と矩形を配置した設計プランは、自然と調和した律動的な空間の展開を実現している。
この美術館は、現在ヨーロッパを中心に活動している国際的評価の高いアーティスト・李禹煥氏と建築家・安藤忠雄氏のコラボレーションによる作品と言える。半地下構造となる安藤忠雄設計の建物のなかには、李禹煥氏の70年代から現在に到るまでの絵画・彫刻が展示されており、安藤忠雄氏の建築と響きあい、空間に静謐さとダイナミズムを感じさせる。
■公式サイト
https://benesse-artsite.jp/art/lee-ufan.html
【地中美術館(直島)】
地中美術館は、香川県直島町のベネッセアートサイト直島内にある、安藤忠雄設計の美術館で、2004年に開館した。地下に埋め込まれた構造で、自然光を活用した空間に、クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品を恒久展示している。
地中美術館のコンセプトは「自然と人間との関係を考える場所」。瀬戸内の美しい景観を損なわないよう建物の大半が地下に埋設され、地下でありながら自然光が降り注ぎ、一日を通して、また四季を通して作品や空間の表情が刻々と変わる。アーティストと建築家とが互いに構想をぶつけ合いながらつくり上げたこの美術館は、建物全体が巨大なサイトスペシフィック・ワークといえる。
安藤氏のコメント。
「地中美術館は、安藤忠雄の建築を構成する主な素材であるコンクリート、鉄、ガラス、木を使用し、デザインを極限まで切りつめて設計されています。地中だけで構造体を構築したこの建物は、非モニュメンタルでいて、建築的という相反する意味を両立させています」
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう