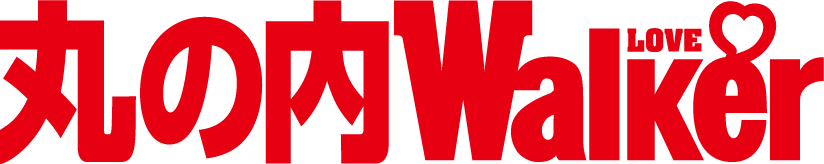東京駅から有楽町駅に架かる美しい煉瓦アーチ造りの「新永間市街線高架橋」は山手線と共に100年をつなぐ
2025年11月07日 12時00分更新
高層ビルや歴史的建造物など、丸の内の建築群を現場のレポートを交えながら紹介する連載「丸の内建築ツアー」。今回は特別編として、環状運転開始から100周年となるJR山手線が走るレンガアーチ橋の高架橋「新永間市街線高架橋(東京高架橋)」を紹介します。
山手線の概要と歴史
山手線は、JR東日本が運行する東京の都心を一周する環状鉄道路線であり、首都圏の鉄道網の中核をなす存在です。1周約34.5km、駅数は30。上野、東京、品川、渋谷、新宿、池袋といった世界的に知られるターミナルを結び、日本最大級の通勤通学・生活路線となっています。ラインカラーのウグイス色は、「山手の緑」をイメージして定められ、駅サインや車体帯色に用いられています。
その始まりは1885年(明治18年)に開業した「品川線」にさかのぼります。日本鉄道が建設した赤羽〜新宿~品川間の貨物支線が原点で、当時は都心部ではなく郊外を経由していたため、「山手の方を通る線路」と呼ばれるようになりました。以後、豊島線(田端〜池袋間)などの延伸を経て、1909年の国有化時に「山手線」として正式に命名されます。
1925年(大正14年)11月1日、長年の悲願であった東京駅〜上野駅間が完成し、山手線はついに環状運転を実現しました。これにより、東京の都市鉄道網は一気に統合され、都心の移動効率は飛躍的に向上します。
その後も京浜線(現・京浜東北線)や中央線、総武線などとの接続強化が進み、通勤圏は拡大の一途をたどりました。戦後の高度経済成長期には混雑率が250%を超える時期があったほか、GHQによりローマ字併記の指示があった際に読み方が一時的に「やまてせん」となった時期がありました。その後、列車の増発やホーム・車両の延伸・長編成化、京浜東北線と共有していた線路を分離するなどの進展により輸送力が確保されたほか、1971年に国鉄が全路線にふりがなをつけることを決定した際に命名当初の「やまのてせん」に読み方も戻されています。
平成に入ってからは、混雑解消を目的として一時期は6ドア車の導入や、205系、E231系、E235系電車と常に最新鋭の車両を導入、信号システムの更新が進み、現在も首都・東京の都市構造を支える“動脈”として日々進化を続けています。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう