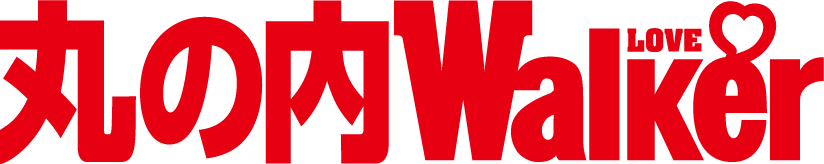東京駅から有楽町駅に架かる美しい煉瓦アーチ造りの「新永間市街線高架橋」は山手線と共に100年をつなぐ
2025年11月07日 12時00分更新
新永間市街線高架橋の歴史(計画~着工前)
19世紀末、東京の鉄道には上野・新橋・品川など複数のターミナルが点在していましたが、上野以北の東北本線と新橋以南の東海道本線が相互に接続されておらず、都市交通及び長距離輸送の非効率が問題視されていました。この状況を解決するため、1887年に東京府が交付した都市改正設計の一環として上野~新橋間を結ぶ南北連絡線の建設を決定します。
この構想を技術的に導いたのが、ドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテルとフランツ・バルツァーでした。当時のヨーロッパでは、郊外や地方から都心へ向かう鉄道路線の多くが、市街地の外縁部に頭端式のターミナル駅を設け、そこから先は馬車や徒歩で市街地内や他のターミナルへ移動するのが一般的でした。一方でベルリンの鉄道は、市街地を貫通して運行していたため、利便性や効率の面で他都市よりも優れていました。
ルムシュッテルとバルツァーはそのベルリンで市街線建設に携わった経験をもち、東京でも同様に都心部のターミナル間を貫通して高架線でつなぐ「ベルリン型都市鉄道」の導入を提案しました。
当初、鉄骨構造による高架橋案も検討されましたが、当時の日本では鋼材が高価で輸入依存度が高かったため、国産煉瓦を活用する煉瓦アーチ構造が採用されました。これにより、国内の建材産業の発展を促すという副次的効果も生まれました。1896年には、工事を統括する「新永間建築事務所」が設立され、日本人技師による詳細設計と工法研究が本格化。煉瓦の製造規格、目地の厚さ、アーチの角度まで厳密に規定され、近代日本の鉄道建築技術の礎を築く計画が整えられたのです。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう