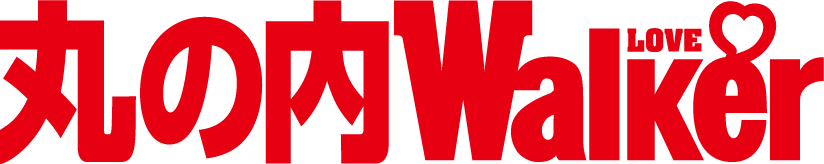東京駅から有楽町駅に架かる美しい煉瓦アーチ造りの「新永間市街線高架橋」は山手線と共に100年をつなぐ
2025年11月07日 12時00分更新
新永間市街線高架橋の歴史(着工~工事~完成)
東京高架橋の建設が始まると、まず支持地盤に達するまで3間(約5.5メートル)から9間(約16.4メートル)の松杭を打ち込みました。その後の煉瓦積みの作業は、一人あたり1日に370本までしか積むことが許されておらず、さらに煉瓦の洗浄も必要とするなど非常に慎重な工程であったため、工事の進捗はなかなか進まなかったといわれています。
煉瓦は国内各地から調達され、特に埼玉県深谷や利根川付近の窯業地で焼成されたものが多く使われました。施工を請け負ったのは、現在の鹿島建設にあたる鹿島組と、すでに解散して現存しない杉井組の2社でした。
工事は1900年9月20日に着工しましたが、1901年4月に日清戦争後の不況の影響で一部区間の工事が中断されます。1902年に再開されたものの、1904年3月には日露戦争の勃発により再び中断を余儀なくされました。その後、日露戦争終結後の1906年4月に工事は本格的に再開されます。また、同年3月に交付された鉄道国有法により路線は国有化され、当時まだ着手されていなかった東京駅以北の区間についても、鉄道局によって工事が進められることとなりました。
こうして完成した高架橋は、1910年に開業した有楽町駅や1914年の東京駅開業とともに供用を開始します。西側を近距離列車(山手線・京浜線)、東側を長距離列車が使用する複々線構造が実現し、東京の鉄道ネットワークを一新しました。なお、実際には長距離列車の貫通運転は行われませんでした。これは、東北本線側が単線であったことや、積雪によるダイヤの乱れが頻発していたため、東海道本線側への影響を防ぐ必要があったためです。
1923年の関東大震災では多くの鉄道施設が被害を受けるなか、東京高架橋は大きな損傷を免れ、その堅牢さを証明しました。戦中の空襲や戦後の混乱期も乗り越え、現在に至るまで100年以上現役で使用されています。バルツァーとルムシュッテルらの理念が形となったこの構造物は、日本の鉄道近代化を象徴する「赤煉瓦の記念碑」といえるでしょう。
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう