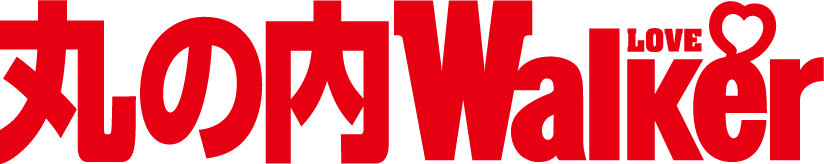エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀「大阪・関西万博2025をブラタマキ」 第6回
いのちは合体・変形だ! 河森正治「いのちめぐる冒険」は高精細スクリーンと大音響で大阪・関西万博のテーマをドライブする
2025年05月27日 12時00分更新
8人のテーマ事業プロデューサーが大阪・関西万博のテーマを深掘りしたシグネチャーパビリオン。「マクロス」シリーズなどで知られるアニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーターの河森正治氏のパビリオン「いのちめぐる冒険」のコンセプトは「いのちは合体・変形だ!」。
2025年大阪・関西万博を筆者が歩く連載、万博ブラタマキも第5弾。シグネチャーパビリオンの合同内覧会で取材はしていたが、目玉の超時空シアターとANIMA!を取材できていなかったので、ようやく体験してきた。
個人的にも大好きなアニメ作品の数々をクリエイトしたレジェンド河森氏だが、最初にお話をしたのは2019年の「河森正治EXPO」(東京ドームシティ、Gallery AaMo)。
このときに、1970年の大阪万博への深い気持ちを聞いて、ぜひ、大阪・関西万博でも一緒にやりましょうと話をしたが、こうして、河森氏にしかできないパビリオンを体感すると、感無量だった。大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」をドライブするような、刺激的なパビリオンだ。
パビリオンの建築は、宇宙や生物のつながりを体感出来る50個以上のキューブ状「セル」(細胞)を積み重ねた構造で、高さはおよそ7.4m。海水で練った軽量コンクリート(HPC)を使用し、環境負荷を減らしつつ、会期後も再利用可能なサステナブル設計になっている。
“セル”は鉄骨フレームと特殊なコンクリートパネルからなる2.4m立方のシンプルな構造体を最小単位としながら、進化し大きくなるにつれて機能を増やし、展示の次元を拡大していく。
海水コンクリートパネルは、貴重な真水資源を保全するために、真水を使用した一般的なコンクリートではなく、海水を使用している。緊張材として鋼線の代わりに炭素繊維ケーブルを使用することで、真水ではなく大阪湾の海水を配合することが可能になり、長寿命化などの多くの革新性をもたらしている。
全体に、多様な命を育むサンゴ礁をイメージし、ランダムに積まれたセルが生命のダイナミズムを表現している。
小野寺匠吾建築設計事務所の小野寺匠吾氏は、以下のようなメッセージをファクトブックに残している。
「僕たちはRestorative Design Exploration(建築を通して環境を回復する)をテーマに、このパビリオンでは『「海」で広がる低環境負荷建築 システム』の実現に挑戦しています。建築や展示を楽しみながら、ふと普段気づきにくい海洋の資源やいのちのめぐみ、環境の問題などにつ いて考えるきっかけになればと思います」
VRとMRを行き来する「超時空シアター」
「499秒 わたしの合体」。超時空シアターとは、30人がカメラ付きVRゴーグルを装着し、VRとMRを行き来しながら宇宙スケールの食物連鎖を同時体験する、世界でここでしか体験できないイマーシブ展示。
MR/VR技術や高精細スクリーン、振動する床、大音響を駆使し、いのちの連鎖を全身で感じるミュージカル風シアターで没入体験ができる。
筆者も参加してみたが、円形の空間でほかの参加者も見える形のMR(Mixed Reality:複合現実)は質感十分。何かあるとつい手を伸ばしてしまうぐらいで、30人が仲間と感じてくる。そこからVRパートに入ると、まさに河森ワールド「いのちは合体・変形だ!」で、最高の作品の世界に没入してしまう。ぜひ、実際に参加してほしい。
内容は、これまで数々のSF作品を生み出してきた河森氏が描く「宇宙スケールの食物連鎖」。音楽家、菅野よう子氏とのコラボによる主題歌(前編「ワカンタンカ/葉音」、後編「499秒/中島愛」)が、映像とシンクロして魂を揺さぶる。
映像はIMAGICA EEXによるプロデュースで、イマーシブ映像の草分け的存在・西郡勲氏がディレクションしている。音響は、SoVeCとソニーPCLによって、VRゴーグルの耳元から聞こえる音と会場のスピーカーから出力される音を立体的に演出、超時空シアターのために開発した圧倒的な立体音響を体験できる。
この最先端技術とクリエイティブの融合は、ドバイ万博の日本館も手がけたバスキュール社によるもので、ナレーションは坂本真綾氏が務めている。
全身で感じる「いのちのミュージカル」ANIMA!
映像と音楽と振動がシンクロする、全身で感じる「いのちのミュージカル」。菅野よう子氏が創り出す音の世界とインタラクティブな振動や立体音響、紗幕に映し出される映像で体感するまったく新しい世界初の没入型空間は、まさに河森氏と菅野氏が生み出した野生のオーケストラと言えよう。
SoVeCが提供する立体音響による新しいソリューション「音のXR体験」とソニーPCLが提供するソニーの床型ハプティクス(人の歩行にあわせて多彩な振動フィードバックを実現するデバイス)を使ったイマーシブ体験を組み合わせ、ヒトの五感に直接訴えかけ、全身で感じる新しい体験型エンタテインメントを共同開発し、提供している。
これらのソニーの先端技術(立体音響技術とハプティクス技術)を組み合わせることによって、立体的な空間の音響と床からの音と振動による全方位に包まれた新しい感覚を創り出し、圧倒的な映像と相まって、映像/音/振動が融合した全く新しい体験を生み出している。
ゴーグルなどは使わないが、超時空シアターとはまったく別の没入感が気持ちよい。紗幕に映写される映像と床の振動がリアルな異世界空間を作り出し、一緒に参加する来場者と、その空間を共有する感覚が実に良い。
河森氏は公式サイトに以下のようなメッセージを寄せている。
「ANIMA(アニマ)というのはラテン語で『生命』や『魂』を意味し、アニメーションの語源ともなった言葉です。私たちは普段、自分と自然や自分と他のいのちを分けて考えていますが、本来は私たちもそのつながりの一部であるはずです。超時空シアターと対となるこの作品では、映像・音・振動が一体となった空間の中で、ゴーグルなどの機器を装着せずに全身で野生のオーケストラを感じてもらうことを目指しました。その名前の通り、より根源的で魂に訴えかけるような、いのちの輝き、躍動、そして、その凄まじさに翻弄される体験を楽しんでください」
創造の源と「いのち球」
パビリオン誕生の軌跡。この展示では「宇宙スケールの食物連鎖」を描く。超時空シアター「499秒 わたしの合体」の世界観の根源となる原画スケッチを特別公開する。
河森氏が生み出した原画本展示では、テーマを視覚化するための初期スケッチやアイデアラフを展示。河森正治がどのように「いのちは合体・変形だ!」というコンセプトをもとに、超時空シアターを設計したのか、「今、ここに共に生きる奇跡」を描いたのか、その過程をじっくりと見ることができる。
地球上の多様な生態系とからだの中のミクロな世界、そして宇宙規模の交流を響鳴させながら、エネルギーや物質の循環がどのように起こるか、創造をかき立てたスケッチも展示されている。
原画では、河森氏が初めて挑んだカメラ付きVRゴーグルでの没入体験の設計の一部も見られる。イマーシブ体験の草分け的存在である西郡勲氏との共同作業として取り組んだのは、「MRの一体感とVRの没入感の重ね合わせ」。これらの世界に類を見ない仕組みがどのように構築されたのか、VRゴーグルの視点設計やインタラクションのアイデアを示したスケッチも必見。
また、河森氏によってデザインされた生物多様性を合体・変形させた象徴「いのち球」を、海洋堂が総力を上げて創った特別なフィギュアも展示。
本パビリオンのコンセプトデザイン「いのち球」は、「ゾウやクジラ、樹木やキノコ、アリそしてヒト。全てのいきものに上も下もない。いのちに大小もない」という構想から、生物多様性を合体・変形させた象徴だ。
「いのち球」のフィギュアは、生きものフィギュアの巨匠・松村しのぶ氏を筆頭に精巧な造形技術で知られる海洋堂および協力企業のスペシャリストによって制作された。従来の造形技術を超えた精密な細部によって、多種多様ないのちが複雑に絡み合いながらも共鳴、調和する姿を見事に再現している。
そして、パビリオンの看板として、屋外には、3.5mの「いのち球」のモニュメントがそびえ立っている。
廃棄されたPCや携帯電話に含まれる金属を一つ一つ職人がていねいに解体するリサイクルを担ったミナミ金属(石川県金沢市)代表取締役・岡村淳氏は、「携帯電話およそ20万個分を循環させた」。
自然の山を削ることなく、都市鉱山製の金を100%使用した金箔は、金銀の配合を河森プロデューサーの希望に合わせて調整しシャンパンゴールドカラーに。モニュメントに使用された金箔は、箔一(石川県金沢市)が手がけたもので、持ち込まれた金を伝統工芸士の手技によって1万分の1mmの薄さに仕上げ、一枚一枚をていねいに手作業でいのち球に貼りこんでいる。
製造と装飾を担った箔一代表取締役・浅野達也氏は、「日本の伝統美がモニュメントに宿るよう、職人のものづくりの技を結集して仕上げました。 会期中、金箔の輝きが長く美しく保たれるよう特別な技術も施しています」と語っている。
モニュメントの表面は、金箔特有のしわや「箔足」と言われる金箔の境界が残されており、さらにエイジング加工という高度な手法を用いることで奥行きのある豊かな輝きを放つ仕上がりになっている。
4m超の巨大ビジョンに映し出す「宇宙の窓」
4m超の巨大ビジョンに映し出すいのちの輝き。3万6千km離れた場所から見る今日の地球、卵の中で成長してゆく生命の姿など、人間の感覚器官では捉えられない時空スケールで撮影した超高精細映像を、4m超四方の巨大ビジョンに映し出す。
生物多様性超シナプス
地面に這いつくばって雑草を観察したり、川で1人、何時間もガサガサしたり。いきもの探しに並外れた情熱を傾けるフィールドワーカーたち。彼らをフィールドへ駆り立てるいきもの探しの魅力とは、いったい何なのだろうか。
自然の中での彼らのしぐさ、目線の動き、脳内で考えていることを分解して、グラフィックと動画で表現したもの。彼らに見えている世界の一端、フィールドでの「超シナプス」の瞬間を、覗いてみよう。
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう