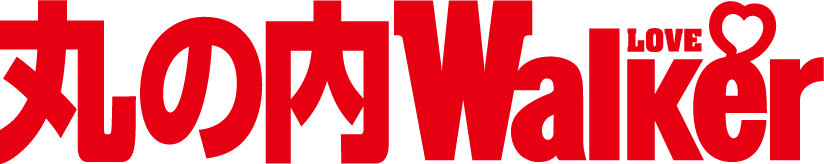エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀「大阪・関西万博をブラタマキ」 第14回
万博の最強シンボル「大屋根リング」を会場と森美術館(六本木)で登ってくぐって、藤本壮介の建築を体感した
2025年07月07日 17時00分更新
10回目の大阪・関西万博取材では、万博を象徴し、全体の形を構築している建築家・藤本壮介氏の『大屋根リング』をあらためてじっくり回ってみた。
2025年7月2日から東京・六本木の森美術館で始まる展覧会『藤本壮介の建築:原初・未来・森』(~2025年11月9日)に大屋根リングの5分の1の模型が登場することを知り、実物と、展覧会で紹介される貴重な資料も含めて、ある意味一番人気の高い施設であるリングと向き合いたくなったからだ。
6月30日に万博会場で大屋根リングを歩き、2日後の7月2日、開幕した森美術館の展覧会で模型というには巨大で迫力十分のリングと向き合い、3日間で極大の実物と精巧な模型の双方に接して、「それでも多様な世界は繋がることができる」という藤本氏の理念に共感を覚えた。
それほどに、大屋根リングを歩く老若男女は笑顔で楽しさに溢れていたからだ。
万博10回目にして
超じっくりゆっくり大屋根リングを堪能してみた
雨のときには逃げ込み、カンカン照りのときには日陰として逃げ込み、異動空間や休憩場所として頼りにしてきたリング。どうしてもパビリオンなどの取材で、しっかり、大屋根リングに向き合ってこなかった。
しかし、角川アスキー総合研究所の膨大なX解析データから徹底分析しても、圧倒的に人気の建築だ。個性的な建築が立ち並ぶ中でも一番ユニークな大屋根リング。もう一度しっかり向き合ってみよう。
大阪・関西万博(2025年4月13日~10月13日)のシンボルである「大屋根リング」は、建築家・藤本壮介が設計した世界最大級の木造建築物で、万博会場(夢洲)のほぼ全域を囲む巨大なリング状の構造物である。
外周約2km、幅約30m、高さ12〜20m(場所により変動)をほこり、円周内は東京ドーム約4個分に相当する巨大なリングで、万博会場の約70%を囲む。
主要構造は木材で、国産のスギ、ヒノキ(約7割)、外国産のオウシュウアカマツ(約3割)を使用しており、工法は、日本の伝統的な木造建築技術(貫工法)と現代のエンジニアリングを融合している。ギネス世界記録で、2025年3月に「世界最大の木造建築物」として認定されている。
「多様でありながら一つ」をコンセプトに、世界190ヵ国・地域の参加者が一つのリングでつながることを象徴している。リングの中央に位置する「静けさの森」(緑地エリア)を取り囲み、自然と人工物が共生する空間を創出している。
リングの屋上は「スカイウォーク」と呼ばれる遊歩道で、来場者は会場全体を見渡しながら歩ける。リングは完全な円形ではなく、場所によって高さや幅が変化する有機的なデザインで、歩くこと自体が楽しい。
リングは会場内の主要パビリオンをつなぐ動線として機能すると同時に、リングの屋根は日よけや雨よけとしても機能し、夏場の暑さや急な降雨から来場者を保護する。
夜間にはLED照明によるライトアップが施され、幻想的な雰囲気を演出する。リングは約1000以上の木造ユニットを組み合わせて構築されており、各ユニットは工場でプレハブ化され、現場で組み立てることで工期短縮と精度向上を実現した。大阪湾の人工島(夢洲)の軟弱地盤に対応するため、リングの基礎には最新の免震技術が採用されている。
使用木材はFSC認証を受けた持続可能な森林から調達され、万博終了後は一部を再利用し、遺構として大阪府内の公共施設や公園に活用予定だ。もっとも、リングの一部を夢洲に残す議論もある。日本国際博覧会協会(万博協会)は6月23日、「大阪・関西万博の大屋根リングの活用に関する検討会」で、大屋根リングの一部を現在のように人が上がれる形で保存する案をまとめた。
会場北東の200mか南側の350mを、費用が抑えられる「展望台」などとして残すことを目指す方針が確認されている。リングの1周2kmのうち、北東200mは大阪府と大阪市が秋以降に開発事業者を公募するエリアにあり、事業者負担での保存を目指すが、応じる事業者が現れなければ開発まで猶予がある南350mを保存する。こうした方針は、国や万博協会、経済界、府・市でつくる6月23日の検討会で打ち出され、同日の万博協会理事会で了承された。
SNSなどでは、すべてを残したいという声も散見される。実際に万博が開幕してから、大屋根リングを実際に見て歩いた人たちの意識が変わってきた、ということだ。
【改めてじっくり1周回ってみた】
いつもはお目当てのパビリオンに並んだりするわけだが、この日は、大屋根リングに一本勝負。ゆっくり、じっくり回ってみた。
【大屋根リングから見たパビリオンたち】
下から見ても面白い建築ぞろいだが、リングの二重になっているスカイウォークの高い方から見るとまた面白い。
【リングの植栽】
季節ごとの花や芝生が枯れないように、常時、係の人が作業をしている。
【リングの外に広がる海、咲洲など】
大屋根リングからは会場の外に広がる海が見える。特に西に広がる神戸方面は夕景が絶品だ。海の上のはじめての万博の醍醐味。
六本木の森美術館も行かないと、大屋根リングの秘密はわからない
この大屋根リングを設計した藤本壮介氏の森美術館『藤本壮介の建築:原初・未来・森』は、藤本氏にとって初の大規模個展になる。
活動初期から世界各地で現在進行中のプロジェクトまでを8セクション構成で網羅的に紹介し、約30年にわたる歩みや建築的特徴、思想を概観する。

森美術館公式より。前列左から2人目が藤本壮介氏、1人目が本展コラボレーターの幅 允孝氏(ブックディレクター、有限会社バッハ代表)、3人目が同コラボレーターの宮田裕章氏(データサイエンティスト、慶應義塾大学教授。大阪・関西万博・テーマ事業プロデューサー)、前列右端が同コラボレーターの倉方俊輔氏(建築史家、大阪公立大学教授)、後列左から3人目が森美術館館長の片岡真実氏。撮影:田山達之
展示には、模型や設計図面、竣工写真に加え、インスタレーションや空間を体験できる大型模型、モックアップ(試作モデル)なども含まれる。建築に携わる人だけでなく、だれもが藤本建築のエッセンスを体感できる、建築家をテーマにしたものとしては画期的な展覧会になっている。
展覧会のタイトルだが、北海道の雑木林は、北海道・旭川の隣町、東神楽町で育った藤本氏にとって原風景である。同様に、東京のような巨大都市の入り組んだ路地や雑多なものが併存する様も、「乱雑さの中にゆるやかな秩序がある」森の要素を見出せるところからきている。
小さい枝や葉などによって構成される森も、路地に存在する植木鉢や自転車、看板など小さなものも、ともに「ヒューマンスケール」であり、森も都市も複層的で、命が生まれ循環する場でもある。
森は人類誕生以前からの原初的な存在だが、この「森」という概念は藤本氏の創造における核のひとつであり、活動初期から現在まで、さまざまな形で具現化されてきた。そして、藤本氏は、この概念が未来の建築や社会のモデルとなると考えている。副題「原初・未来・森」には、そんな想いが込められている。
藤本壮介氏のメッセージ (公式サイトより)
「今回の個展は、いわゆる回顧展というより、現在進行形で、むしろ未来を向いているものです。これまでの集大成であると同時に、これからの方向性を模索する展覧会になると感じています。建築家とは、人と人、人と自然の関係を紡ぐ『場』を作る仕事でもあり、それは私にとっては自然と人工が溶け合う『未来の森』のような場所だといえるかもしれません。さまざまな価値観がバラバラであることの良さと寂しさが行き交うこの時代に、そこに豊かな『つながり』を作り出せないかと模索しています。『こんな建物や街で暮らしたら、世界はどう見えてくるのだろう』とみなさんの想像と希望が膨らみ、未来をポジティブに考えるきっかけとなれば嬉しいです」
藤本壮介氏の略歴 (公式サイトより)
1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞《ラルブル・ブラン(白い樹)》に続き、2015、2017、2018年にもヨーロッパ各国の国際設計競技にて最優秀賞を受賞。国内では、「2025年大阪・関西万博」の会場デザインプロデューサーに就任。2024年には《国際センター駅北地区複合施設(仮称、仙台)》(2031年度竣工予定、宮城)の基本設計者に選定される。主なプロジェクトに、《House N》(2008年、大分)、《武蔵野美術大学美術館・図書館》(2010年、東京)、《House NA》(2011年、東京)、《サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013》(ロンドン)、《ラルブル・ブラン(白い樹)》(2019年、フランス、モンペリエ)、《白井屋ホテル》(2020年、群馬)、《石巻市複合文化施設》(2021年、宮城)、《ハンガリー音楽の家》(2021年、ブダペスト)など。
展覧会は8つのコーナーからなる。音声ガイドは声優の森川智之さん。展示された模型やスケッチなどは一部を除いて撮影が可能。
大屋根リングが紹介されるのは5番目のコーナー。
5 【開かれた円環】
《大屋根リング》(2025年)の5分の1、部分模型(高さ4m超)を中心に、構想段階のスケッチや記録写真、リングで使用された日本の伝統的な貫(ぬき)接合技術を紹介するモックアップ、藤本のインタビュー映像などによって、リングをさまざまな角度から掘り下げる。
また求心性と発散性を同時に併せ持ち、分断を超えたつながりを象徴する「開かれた円環」というコンセプトに焦点を当て、《ハンガリー音楽の家》など関連する12プロジェクトの模型も展示されている。
1 【思考の森】
活動初期から現在計画中のものまで、藤本の100を超えるプロジェクトを紹介する大型インスタレーション《思考の森》。300平方mを超える空間で藤本建築の全貌を表現する。
模型や素材、アイデアの断片であるオブジェなどが、藤本建築の3つの系譜に分類され年代順に配置されて、ひとつの「森」を構成している。3つの系譜とは、閉鎖的な境界線が外部に開かれる「ひらかれ かこわれ」、空間の用途や性質が曖昧で多義的な「未分化」、ひとつの建築が多くのパーツで構成される「たくさんのたくさん」で、藤本建築の根幹をなすもの。
まさに森のように、広い展示空間に立体的に並べられ、見る人の導線もなく、高いところにつるされた模型は下からも見られ、低い模型は見下ろせる。模型の森に入り込んだような感覚になる画期的な展示空間。
2 【軌跡の森—年表】
倉方俊輔氏監修の下で制作された、藤本の活動の軌跡を総覧する年表。東京大学を卒業した1994年から今後竣工予定のものまで藤本による96のプロジェクト、同時期に竣工した国内および日本人建築家による主要作品、国内外の建築業界や社会一般の出来事などが掲載されている。
また、各時代に何を重視していたのか読み取れる藤本の言葉に加え、作品写真のスライドショー、本人のインタビュー映像も展示することで、藤本建築を歴史的文脈で読み解くことを試みる。
3 【あわいの図書室】
間(あわい)をコンセプトとするブックラウンジを、窓から景色の見える展示室に設けた。幅允孝氏が藤本建築から着想を得た5つのテーマ「森 自然と都市」「混沌と秩序」「大地の記憶」「重なり合う声」「未完の風景」により選んだ書籍40冊が1冊ずつ椅子に置かれ、椅子には本から抜粋された言葉が散りばめられている。
4 【ゆらめきの森】
利用者や居住者の動きを表現したアニメーションを建築模型に投影し、建築そのものではなく人の動きに焦点を当てる。学生たちが集い、談話し、交流する《エコール・ポリテクニーク・ラーニングセンター》(2023年、フランス、サクレー)、家族が時に離れ時に一緒に過ごす《T house》(2005年、群馬)、子どもたちがあちこちで遊び回り、斜面を登り下りする《UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店》(2020年、神奈川)など藤本の5つのプロジェクトを建築図面と共に紹介する。
6 【ぬいぐるみたちの森のざわめき】
《ラルブル・ブラン(白い樹)》、《太宰府天満宮 仮殿》(2023年、福岡)など、藤本が手がけた9つの建築がぬいぐるみとなり対話をするインスタレーション。
明るく話好き、寡黙で真面目などの性格が設定された建築のぬいぐるみたちは、お互いについてのユーモラスな会話を行う。会話からは、各プロジェクトの特徴やそれらが設計された背景などを知ることができる。また、藤本によるスケッチも多数展示される。
7 【たくさんの ひとつの 森】
藤本氏が2024年にコンペで選出され、基本設計を手掛けている音楽ホール兼震災メモリアル《仙台市(仮称)国際センター駅北地区複合施設》を紹介。
建物の構造が体感できる15分の1の大型吊模型を中心に、テーマ「たくさんの/ひとつの響き」が具現化された設計プロセスを見せる模型や資料を展示。また「ばらばらであり ひとつであり」というコンセプトに基づいて設計されたプロジェクトの模型と藤本のインタビュー映像、さらに70点の主要プロジェクトのコンセプト・ドローイングにより藤本建築を複合的に紹介する。
8 【未来の森 原初の森—共鳴都市 2025】
この未来都市の提案は、藤本壮介と宮田裕章によって考案された。模型と映像で表現される、大小様々な球体状の構造体が複雑に組み合わさった未来都市は、全体で高さ500m程度の範囲に収まる。住宅、学校、オフィスといった都市生活に必要なものが備わっている。
立体的に組み合わされた無数の球体群は、「森」と同様、絶対的な中心を持たず多方向に開かれ、人々が複層的に関係を構築する新たなコミュニティ形成が意図されている。
【展覧会オリジナルグッズ】
インク ―記憶のいろ―
価格:各3600円(税込)
藤本氏の記憶にある美しい2つの色を、カキモリ(東京・蔵前)が万年筆用インクに仕立てた。何度も調色を繰り返して再現された、芽吹きの明るいグリーンと夕暮れの淡いピンク。展覧会オリジナルのつけペンとともに。
END OF THE DAY
輪郭がゆっくりと解かれていく時間 かたちあるものは光の余韻に包まれ、消えゆく空とともに、かたちのない風景へと移ろっていく
SPRING FOREST
芽吹きの気配が、空間の内と外を曖昧にしながら広がっていく 生命の揺らぎが、建築と風景の境界をにじませる
他にも、魅力的なグッズがそろっている。
■開催概要
会期:2025年7月2日(水)~ 11月9日(日)
※会期中無休
開館時間:10時~22時
※火曜日のみ17時まで
※ただし、8月27日(水)は17時まで、9月23日(火)は22時まで
※最終入館は閉館時間の30分前まで
会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)
料金
[平日]:一般 2300円(2100円)/学生(高校・大学生)1400円(1300円)/中学生以下 無料/シニア(65歳以上)2000円(1800円)
[土・日・休日]:一般 2500円(2300円)/学生(高校・大学生)1500円(1400円)/中学生以下 無料/シニア(65歳以上)2200円(2000円)
※()=オンラインチケットの料金
※日時指定枠に空きがある場合は、当日、窓口にてチケットを購入できる。
※本展は、事前予約制(日時指定券)を導入している。専用オンラインサイトから「日時指定券」購入が必要。
※当日、日時指定枠に空きがある場合は、事前予約なしで入館できる。
※本展のチケットで、同時開催プログラムも鑑賞できる。
※表示料金は消費税込。
オンラインチケット販売サイト:森美術館オンラインチケット、アソビュー!、Klook
問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
チケット・料金の詳細:https://art-view.roppongihills.com/jp/info/#tickets
公式サイト
https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/soufujimoto/index.html
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行:株式会社角川アスキー総合研究所
発売:株式会社KADOKAWA
発売日:2025年6月30日
定価:1078円 (本体980円+税)
ISBN:978-4049112665
サイズ:A5判/84ページ
詳細はKADOKAWAサイトへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム:万博攻略法 イベントを見るならココ! パビリオンINDEX
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう