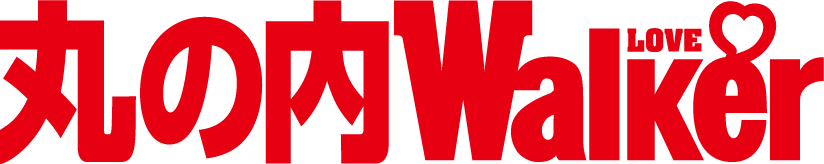現在、東京駅丸の内南口目の前にあるJPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」にて、特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』が開催中です。台湾の蘭という植物をめぐる日本と台湾の学術的ストーリーが、貴重な資料とともに紹介されています。
東京駅徒歩1分! しかも無料! 刺激受けまくりのミュージアム探訪
https://lovewalker.jp/elem/000/004/138/4138822/
台湾にとっての蘭、日本にとっての蘭、美術界にとっての蘭
漢字文化圏の文人文化の水墨画・書・工芸には、蘭が重要な題材として数多く登場します。蘭は古来より「四君子」の一つとして、文人文化では、孤高で高潔な君子の気風を象徴するものと考えられてきました。文人文化の水墨画には、蘭が重要な題材として数多く登場しています。中国清時代の『芥子園画伝』をはじめ、人々が伝統的な絵の描き方を学ぶ絵手本では、竹・梅・菊と並んで蘭がよく取り上げられ、特に表情豊かな細い葉を特徴とする蘭の葉は、長きにわたり運筆の修練のための格好のモチーフとなってきたのです。
熱帯から寒帯までの豊かな自然環境を擁する台湾には、現在470種以上ものラン科植物が生育しています。これらは、台湾の全頭花植物の約10分の1にあたり、それぞれの花や葉の形は極めて多彩です。台湾に何千年もの間居住してきた原住民が、漢民族の移住者の文化的影響を受けるはるか以前から、自然との関わりを通じて、独自のさまざまな文化を発展させてきたなかに、蘭にまつわる習慣や儀式が含まれています。
台湾における本格的な植物相研究は、19世紀初頭に始まりました。19世紀半ば以降には、英国の植物採集者が台湾産植物をキュー植物園の植物学者のもとに送り、次々と新種が同定されました。台湾植物相研究の飛躍的な進展を後押ししたのは、1895(明治28)年から1945(昭和20)年の日本統治時代に、日本人植物学者が台湾全島で実施した植物調査でした。東京大学植物標本室は、この頃に台湾で採集された植物標本を数多く収蔵し、世界的な植物学研究の拠点の一つとして、これまでそれらの標本を植物学研究に役立ててきました。
一方日本国内では、日本最初の本草学書、貝原益軒(1630-1714)による『大和本草』諸品圖(1715年)や、日本における最初の植物図鑑、岩崎灌園『本草圖譜』(1828年自序)に収載された植物のなかに、蘭の図が確認できます。墨一色の木版印刷による蘭の表現は、今日の眼からみて、その科学性と美術性の両側面から注目されます。品種改良が盛んであった江戸の園芸は、「葉芸」(葉の形や斑の変化などを鑑賞する園芸の技法)を生み出し、人々は斑入り植物を珍重しました。江戸後期を代表する草木奇品集として知られる、水野忠暁(1767-1834)による「草木錦葉集」(1829年)では、蘭の葉の複雑な斑入りの現象が木版による白黒の二色で緻密に表現されています。
台湾における洋蘭(熱帯蘭)栽培は、1912(大正元)年、台湾総府林業試験場(現在の農業部林業試験所)に東京帝国大学理科大学附属植物園(小石川植物園)より分譲された10数種が嚆矢とされています。日本統治時代(1895-1945)、台湾に産する胡蝶蘭は、日本統治下の台湾の豊かで美しい自然を象徴する植物として、新たに人気を集め、台湾蘭の栽培や観賞文化の中心となりました。1936(昭和11)年、蘭愛好家でインドネシアにて数多くの熱帯蘭を描いた川澄理三郎(1872-没年不詳)の熱帯蘭写生画展が台北で開催され、台湾における熱帯蘭への関心をさらに高めました。
『台湾蘭花百姿 – 東京展』の概要
今回の『台湾蘭花百姿 – 東京展』は、以下の通り構成されています。
【展示構成】
1:日本人植物学者による台湾ラン科植物調査
2:台湾蘭の栽培と観賞
3:東洋蘭の図譜
4:台湾蘭と自然・芸術・人間
また、この特別展示は、総合研究博物館と台湾の国立歴史博物館が2024年に締結した学術交流協定の成果の一部で、東京会場(インターメディアテク)で開催した後、台北会場(国立歴史博物館)にて東京とは装いを変えた展示が開催予定となっています。台湾会場へも行ってみたいですね。
特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』
会期:2025年2月15日~6月8日
時間:11:00 ~ 18:00(金・土は20:00まで開館)※時間は変更する場合があります
休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日休館)、その他館が定める日
会場:インターメディアテク2階「GREY CUBE(フォーラム)」
主催:東京大学総合研究博物館
入館料:無料
住所:東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE2・3F
アクセス:JR東京駅丸の内南口から徒歩約1分、東京メトロ丸ノ内線東京駅地下道より直結、千代田線二重橋前駅(4番出口)より徒歩約2分
主 催:東京大学総合研究博物館+国立歴史博物館
協 力:東京大学大学院理学系研究科附属植物園、東京大学農学生命科学図書館、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究室、国立台湾大学植物標本館、国立台湾大学図書館、農業部林業試験所植物標本館、国立台湾博物館、国立台湾歴史博物館、国立台湾美術館、国立公共資訊図書館、高雄市立歴史博物館、英国キュー王立植物園
丸の内LOVE WALKERの最新情報を購読しよう