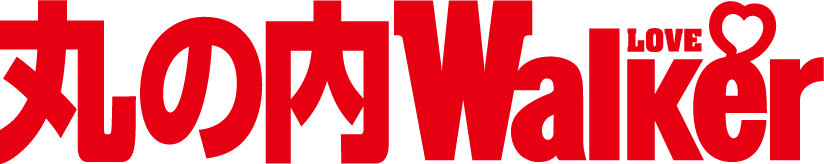つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は長野県長野市の旅の様子をお届けします!
長野市といえば善光寺。伊勢神宮よろしく「一生に一度は善光寺詣り」といわれる善光寺、実は長野駅から歩いて行ける範囲にあるんです。参道を歩いての参拝、なかなかいいものでしたよ。
(歴史編はこちらから)
かなりイケてる長野駅舎
長野駅へ向かう北陸新幹線の車内は、朝早めということもあってビジネスマンが多く見られました。とはいえ夏休みに入ったらしき学生や外国人の姿もけっこう多く、車内はにぎわっていました。
善光寺は一生に一度参るだけじゃもったいない!
実は御朱印集めが趣味の私。せっかく長野市を訪れるなら善光寺は押さえておきたいところです。長野駅から善光寺までのバスも出ていますが、徒歩でも20~30分とのことなので、街並みを楽しみながら歩くことにしました。
善光寺の御本尊、一光三尊阿弥陀如来がこの地に鎮座したのはなんと奈良時代の642年。644年に創建したといわれていて、とても歴史のあるお寺です。歴史の勉強をしたのはかなり昔なのですっかり忘れていましたが、奈良時代に栄えていたのは奈良・京都周辺だけではないんですよね。九州には大宰府、東北には多賀城が置かれていた時代なので、当然日本全国に人が住んでいたわけで、このあたりもたくさんの人が暮らしを営んでいたはずです。
善光寺事務局庶務部長、若麻績英亮さんによると、善光寺の如来さまは日本最古の仏さまともいわれ、日本に仏教を広めるきっかけになったといわれているのだそう。「善光寺如来さまと聖徳太子は手紙のやりとりをしていたそうで、その手紙は法隆寺に納められているんですよ」と教えてもらいました。しょ、聖徳太子ってまさに仏教を広めた人じゃないですか!
少し話が前後しますが、本堂に入って一番最初に出会うのが「びんずるさま」と呼ばれている「びんずる尊者像」です。16人いたお釈迦さまの弟子の一人で、痛みなどの苦を取り除く神通力がとても強かったのだとか。例えばひざが痛い人は、びんずるさまのひざをなでるというように、自分の患部と同じところをなでると神通力にあやかれるといわれています。
若麻績さんは「1713年に安置されて以来、今まで約300年間たくさんの方になでられてきたので、今ではだいぶお顔もすり減ってしまいました」と話してくれました。
ちなみに若麻績さんは「びんずるさまの心臓のあたりを触ると心が落ち着くというか、平常心になれますね」とのことだったので、私も触ってきました。
江戸時代になると、交通網が発達して遠くから参拝しにくる人が増えるようになりました。とはいえ当時は険しい野麦峠を越えなければならなかったため、他の人に依頼して代わりに参拝してもらう「代参」が多かったのだそう。そんなこともあって、次第に「一生に一度は善光寺詣り」と善光寺信仰が広まっていきました。
「性別や身分を問わず、どんな方でも極楽浄土に導くという、今の世の中をより良くするための信仰なんです。私としては、参拝した上でどのように生きていくのかを考えるところなんだと思っています」と若麻績さん。戦などがないという意味で、江戸時代も今の日本と同じように平和だったはず。それでも今の私たちが「より良く生きたい」と思うように、当時の人々もそう思っていたんでしょうね。
参拝したらぜひ体験してほしいのが「お戒壇巡り」。善光寺如来さまの真下にある「極楽の錠前」に触れることで、極楽往生の約束がいただけるとされています。
真っ暗な中、手すりを頼りに歩くことになるのですが、本当に何も見えません!! 一度でも手すりを離したら終わりなので、自然とそろそろとした歩みに。途中でジャラジャラとした何かを触ることができて、何も見えないながらも「これが錠前か!」とちょっと感動しました。が、暗闇すぎてしみじみするほどの心の余裕がなく、私は外に出てから「あの錠前の真上にご本尊の善光寺如来さまがいたのか…」としみじみしました。見えないとはいえ、阿弥陀如来さまの近くまで行けるのは想像以上に感動します。
また、善光寺といえば「善光寺」と書いてある門の印象が強い人も多いのではないでしょうか。あの門は「山門」と呼ばれ、中に入ることができます。
この山門もちょっとおもしろくて、中に四国八十八ヵ所霊場の分身仏が安置されているんです。置かれ始めた時期も理由も分からないそうですが、山門に上ったことで八十八ヵ所の札所を巡ったことにするという風習があったのではないかと考えられています。
特別にあの「善光寺」の文字を間近で見せてもらいました。2畳くらいの大きさがあるとのことで、かなりのサイズ。「善」の字が牛の顔にも見えるといわれているのですが、こうして見ると確かに牛っぽい!
牛といえば「牛に引かれて善光寺詣り」という言葉があります。信心がなかったおばあさんに仏の道を説くため、牛に化身した観音さまを追いかけさせて善光寺へ導き信仰の心を持つようになったことから、「偶然のできごとが良い方に導いてくれる」という意味。「善光寺」の文字にも牛がいますし、本当に観音さまが牛として人々を導いたのかもしれません。
もう1ヵ所、楽しかったところをご紹介。仏教経典を網羅した経本全6,771巻が納められている「経蔵」というお堂です。ここの何が楽しかったかというと、八角の輪蔵を一周押して回すと、中の経本をすべて読んだことになるところ。
下に付いている棒の部分を時計回りに押して回すのですが、これが重い! 最初うんともすんともせずにどうしようかと思っていたのですが、途中で男性が参加(?)してくれたおかげで勢いがついて回すことができました。善光寺詣りができて如来さまとつながれた上に、四国八十八ヵ所を巡って経典も全部読んだことになって、大満足。
最後に御朱印とお守りをいただきます。中央に押された四角い印がどことなく伊勢神宮っぽい雰囲気で、そういえばあちらも「一生に一度はお伊勢詣り」と言われているなと思いました。
お土産もお守りもとても種類が豊富。BEAMSとコラボした雑貨など普段使いできそうなお土産から、さすが善光寺と言いたくなるようなお守りまでたくさん並んでいて、お守りだけいただく予定だった私をかなり悩ませました。
善光寺、参拝する場所が多くて楽しめますよ。私は2時間くらい滞在していたと思います。みなさんも一生に一度はぜひ!
善光寺
住所:長野県長野市長野元善町491-イ
HP:https://www.zenkoji.jp/
アクセス:長野駅から徒歩25分、または「善光寺大門」バス停から徒歩5分
そばを食べるなら地元ファンが多い仲見世通りの食堂で
善光寺の山門から見えた仲見世には、食事処やおみやげ屋さんが並んでいます。長野といえばそばが食べたい、ということで訪れたのが「丸清食堂」。善光寺に向かうために丸清食堂の前を通った時に、立って順番待ちをしている人や表に出ているメニューを眺めている人がいて、気になっていました。
丸清食堂は創業76年の老舗。現在店長を務める松澤孝憲さんで5代目になります。「うちのお店はもともと善光寺の裏側の方にあったんですよ」と、店長のお姉さんの清水さんが教えてくれました。
ちょっと不思議なのが、お店の看板とのれんに「とんかつ」と書かれている点。清水さんにそのことを尋ねると、「元は店名のとおり“食堂”だったんです」という答えが返ってきました。かつて食堂は善光寺本堂の裏手にあり、いろいろなメニューを出していましたが、次第にかつ丼とカレーが人気に。現在の場所に移転した際、せっかく仲見世に移るのだからということでそばを出すことにしたのだそう。仲見世にあるお店だと観光客がメインになるところが多いと思いますが、こちらは昔からの地元のお客さんも多く、かつ丼も相変わらず人気なんだそうです。
それならとんかつも食べないと!ということで、冷たいそばとミニひれかつ丼がセットになった「もりそばセット」を注文。外が暑かったので思わずビールときゅうりのわさび漬けを追加すると、清水さんが「じゃあこれも食べてみて」と、そばを揚げたおつまみを出してくれました。そばのおつまみ、ポリポリとした食感がクセになります。
石臼引きのそばは繊細な風味。更科そばほど白くはありませんが、でも更科っぽいなめらかなのど越しがとても気持ちいい! 夏に食べるそばって最高です。
そしてひれかつ丼! ひれかつは柔らかく厚みがあり、食べ応え抜群。甘いソースとさっぱりしたキャベツがいい仕事をしています。これはおいしい。清水さんによると「3代目、4代目の頃に開発したオリジナルソースを使っている」とのことで、地元にかつ丼ファンが多いのも頷けます。
丸清食堂
住所:長野県長野市長野元善町486
定休日:水曜日(お盆・正月・ゴールデンウィークは無休)
HP:https://marusei-soba.com/
アクセス:「善光寺大門」バス停から徒歩5分
大人になった今だからこそ楽しめる善光寺詣り
長野市といったら善光寺!くらいの気持ちで参拝しましたが、境内は見どころがたくさんで行った甲斐がありました。特にお戒壇巡りはぜひ体験してほしい! 7年に一度ご開帳がありますが、お戒壇巡りならいつでもご本尊を身近に感じることができます(見えませんが)。修学旅行以来行っていないという方も多いと思いますが、大人だからこそ楽しめる場所のような気がします。おみやげ屋さんも充実していますし、仲見世も買い食いができるお店からカフェまでいろいろあるので、あまり寺社仏閣に興味がない方でも楽しく過ごせる場所だと思いますよ。
(歴史編はこちらから)
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう