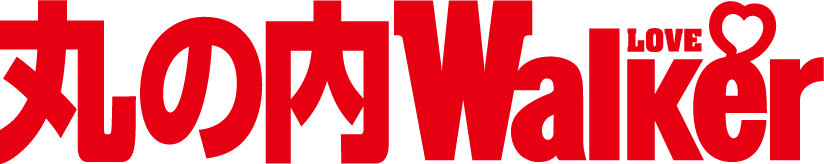東京国立博物館が「べらぼう」の舞台に変身! ドラマで使われたセットから歌麿の貴重な作品まで見どころがありすぎる
2025年04月23日 18時00分更新
江戸のコンテンツ・ビジネスを際限なく革新し続けた
蔦重の世界をじっくり堪能できる
東京国立博物館(東京・上野)は2025年4月22日、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(〜6月15日)を開幕した。
江戸時代の出版業界を革新した蔦屋重三郎(1750年〜1797年、通称:蔦重)は、喜多川歌麿や東洲斎写楽といった浮世絵師を世に送り出し、現代でいうコンテンツビジネスを牽引した人物。
本展では、天明・寛政期(1781年〜1801年)を中心に、蔦重の出版活動と江戸の多様な文化を紹介する。約250点の作品を通じて、彼のビジネス手腕と芸術的価値観を探る。
2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(主演:横浜流星、蔦重役)とも連携し、ドラマのセットを用いた江戸の街の再現展示も実施される(すべてがドラマで使われているものではない)。
戦国LOVEウォーカーは、大河ドラマ応援ということで、2024年12月に刊行したムックでも「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を特集している。そんな縁もあり、4月21日のプレス内覧会にも駆けつけた。
戦国時代も遠い過去になった、天下泰平の江戸期。しかしそこは、出版ビジネスも、江戸城での政治も激しい時代。そんな激しく刺激的な時代の文化をたっぷり見てきたぞ。
本展では、江戸時代の傑出した出版業者である蔦重こと蔦屋重三郎の活動をつぶさにみつめながら、天明・寛政期を中心に江戸の多彩な文化を楽しめる。
蔦重は江戸の遊郭や歌舞伎を背景にしながら、狂歌の隆盛に合わせて、狂歌師や戯作者とも親交を深めた。武家や富裕な町人、人気役者、人気戯作者、人気絵師のネットワークを縦横無尽に広げて、さまざまな分野を結びつけながら、さながらメディアミックスによって、出版業界に新機軸を打ち出していった。
まさに、蔦重はその商才を活かして、コンテンツ・ビジネスを際限なく革新し続けたわけだ。 本展は、蔦屋重三郎を主人公とした2025年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)と連携し、江戸の街の様相とともに、蔦重の出版活動を多面から展示する。
平賀源内も喜多川歌麿も東洲斎写楽も
みんな蔦重と江戸の街をめっちゃ面白く革新した
展示構成は3章構成+附章の4部からなり、蔦重の活動を時系列で追う。
【第1章:吉原再見・洒落本・黄表紙の革新】
蔦重は吉原遊廓で生まれ、幕府公認の遊廓情報誌「吉原細見」の出版からキャリアをスタートした。吉原をプロモーションする出版物や浮世絵を中心に展示、 盟友・平賀源内の貴重なものも展示されている。
●平賀源内
エレキテルは、源内が長崎で壊れたエレキテルを復元したもので、病の治療に用いたり、見世物としたりして話題を集めた。
「物類品隲」は言わば、展覧会の図録。江戸時代、薬品会と称するイベントがたびたび盛況を博していたが、本草学者でもあった平賀源内プロデュースで、宝暦7年(1757年)〜宝暦12年(1762年)に計5回開かれ、大成功をおさめた。この本は、薬品会の出品解説書、展覧会の図録であり、動植物や鉱物などの薬効を解説している。
●礒田湖龍斎筆《雛形若菜初模様》
●一目千本
蔦重が初めて手掛けた出版物。流行の生け花に遊女をなぞらえて紹介する遊女評判記。
●青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)
人気絵師2名による遊女164名の姿絵と、その発句を載せた絵本。
●二美人図
左の豊国は、深川あたりの芸者が描かれている。豊国は東洲斎写楽のライバルともなる絵師。右は歌麿で、蛍を眺める女性たちを描いたもの。肉筆画。

左は歌川豊国《二美人図》(寛政中期、1789年〜1801年)。紙本着色。東京国立博物館蔵。右は喜多川歌麿《蛍狩り美人図》(享和期、1801年〜1804年)。絹本着色。北海道・公益財団法人似鳥文化財団蔵
●吉原の桜と常夜灯
第1章の展示場の中央には桜が並ぶ。吉原大門をくぐった吉原のメインストリート「仲之町」には桜の季節だけ、桜が移植され、夜は常夜灯の明かりに照らされた。この展示室にある常夜灯は大河ドラマ「べらぼう」の撮影のために作られたもので、実際に使用されたセットだ。
●吉原大門
江戸時代の遊郭・吉原への唯一の入場口。この門は大河ドラマ「べらぼう」の撮影で実際に使用されたセットで、歌川豊春、歌川国貞、歌川広重らの浮世絵を参考に作られた。
【第2章:狂歌隆盛ー蔦唐丸、文化人たちとの交流】
天明期(1781年〜1789年)の狂歌ブームに乗じ、蔦重は狂歌師(大田南畝こと蜀山人、石川雅望など)や戯作者(山東京伝、朋誠堂喜三二など)と連携した。黄表紙や洒落本で大衆の心を掴み、出版業界に新風を吹き込んだ。
●狂歌絵本ー歌麿の才能開花
狂歌本は最初、文字だけだったが、蔦重は、ここに絵を描かせ、多色摺や雲母摺、空摺などの技法を使って、豪華な狂歌絵本を作った。

左側は、宿屋飯盛撰・喜多川歌麿画《龢謌夷(わかえびす)》(天明9年、1789年)。横大判錦絵折帖。版元:蔦屋重三郎。東京都江戸東京博物館蔵。さまざまな正月風景を描いた狂歌絵本。正月に獅子舞を披露する太神楽の図。右側は、喜多川歌麿画《歌まくら》(天明9年、1789年)。横大判錦絵折帖。版元:蔦屋重三郎。東京・浦上蒼穹堂蔵。修羅場あり、駆け引きありのさまざまなシチュエーションで、細やかな機微が描かれている
【第3章:浮世絵師発掘ー歌麿、写楽、栄松斎長喜】
寛政の改革で打撃を受けた蔦重は、役者大首絵で再起。無名の東洲斎写楽を起用し、寛政6年(1794)に28枚の大首絵を一挙刊行し、浮世絵界に衝撃を与えた。また、歌麿の美人画や栄松斎長喜の京阪芸妓画も紹介。
●喜多川歌麿
歌麿は美人画の第一人者。蔦重とともに、従来役者絵に用いられた「大首絵」の構図を美人画に取り入れ、人物の表情や仕草にクローズアップした表現で人気を博した。一時期、蔦重のもとに寄寓していたとされる。

右側は、喜多川歌麿筆《青楼仁和嘉女芸者部 大万度 萩江 おいよ 竹次》(天明3年、1783年)。大判錦絵。版元:蔦屋重三郎。東京国立博物館蔵。吉原の芸者たちが仮装して練り歩く吉原俄を題材にした初期作品。左側は、喜多川歌麿筆《風流花之香遊び 上・下 高輪の季夏》(天明3年、1783年ごろ)。大判錦絵。版元:蔦屋重三郎。東京国立博物館蔵。海を望む開放的な座敷での宴席。品川の遊郭を描いた初期の優作
●東洲斎写楽
わずか10か月間で、140点を超える作品を残して忽然と姿を消した絵師。阿波の能役者、斎藤十郎兵衛とされる。役者の欠点まで描き出すリアリズムは人々に衝撃を与えた。蔦重が役者絵独占を目指し、見出したスター。

左側は、東洲斎写楽筆《二代目坂東三津五郎の石井源蔵》(寛政6年、1794年)。大判錦絵。版元:蔦屋重三郎。重要文化財。東京国立博物館蔵。藤川水右衛門の威圧感に押されながらも刀を抜く石井源蔵。右側は、東洲斎写楽筆《三代目坂田半五郎の藤川水右衛門》(寛政6年、1794年)。大判錦絵。版元:蔦屋重三郎。重要文化財。東京国立博物館蔵。父の仇の藤川水右衛門に石川源蔵が斬りかかろうとしている場面
【附章:天明寛政、江戸の街】
大河ドラマのセットを一部に用いて、日本橋近辺の18世紀後半の江戸の街を再現。当時の文化や経済の活気を体感できる。
●耕書堂
●大河ドラマコーナー
学芸企画部長に見どころを聞く
東京国立博物館の松嶋雅人学芸企画部長に見どころを聞いた。
「今回の展覧会は、蔦屋重三郎という江戸後期のコンテンツビジネスのパイオニア、その出版活動を時系列で追いながら、出版物や浮世絵の魅力をお届けする展示でございます」
「全体で258点、浮世絵や版本が並んでまして、4週間ごとに展示替えをして、全部で10回くらいのシフトになります。5月20日から後期に切り替わって、品物が変わるんですけど、例えば同じ絵柄の別版本を展示するなどの工夫をしていますので、前期後期、どちらも楽しんでいただければと思います」
「蔦屋の名前が歴史に登場するのは、吉原遊郭のガイドブック、情報誌みたいな『吉原細見』からです。編集者、リサーチャーとして名前が出て、義理の兄のお店で出版業をスタートさせました。吉原生まれの蔦屋は、そこでしか手に入らない情報を武器に、出版で頭角を現したわけです。吉原細見を大量生産して独占販売したり、浄瑠璃本を扱ったり、手堅い商売で資金を蓄えていくわけです」
「その後、洒落本や黄表紙といった、大人も楽しめる娯楽本に手を広げます。江戸の出版って、古典をベースにしつつ、吉原の流行やトレンドを反映するんです。蔦屋のビジネスモデルの特徴は、人気作家や絵師を囲い込んで、版権を押さえて独占販売すること。こうやって、よそと差をつける革新的な出版物を次々生み出していくんです」
「ちょっと飛ばしますけど、寛政の改革で出版統制が厳しくなると、武士出身の作家が減って、町民出身の新しい才能が出てきます。蔦屋はそういう流れも見逃さず、人気作家とコラボして、狂歌本や狂歌絵本を出版。これは、富裕層が出資して豪華な本を作る形態で、自己承認欲求を満たすような仕組みもあったんですよ。現代でいうSNSで作品をシェアするみたいな感覚に近いかもしれません」
「特に見どころは、第2章の浮世絵。歌麿の『歌まくら』シリーズ、男女の機微を描いた12枚組で、東京国立博物館、創立152年目にして初公開になります。茶屋の二階座敷で、女性の後頭部と男性の顔が重なって、ちらっと見える男性の目……これ、感情の解釈が観る人次第で変わる、深い絵なんです」
「線だけでやわらかさや形を表現する技術は、ピカソのデッサンに匹敵するんじゃないかと、個人的には思うんですけど。これは数十部しか残ってないオンデマンドの逸品で、前期後期で別版本を展示して、同じ場面をご覧いただけます」
「後半は浮世絵のコーナー。歌麿や写楽の作品が中心で、歌麿は遊女や茶屋の看板娘を個性的に描き分けて、リアリズムを追求しました。写楽は役者の役柄を超えて、年齢や個性までリアルに描いちゃう。写楽の絵は流行らなくて1年半で消えちゃうんですけど、蔦屋が彼らを起用したことで、浮世絵に新しい風を吹き込んだんです」
「最後、第4章(附章)では、日本橋あたりをイメージした江戸の街並みを再現。写真撮影もOKなので、ぜひ記念にどうぞ。今回の展覧会は、大河ドラマと連携して、ドラマで映る出版物のオリジナルを展示してるんです。江戸の空気感、200数十年前の東京を、ぜひ感じ取っていただければと思います」
■音声ガイド
ナビゲーターは、横浜流星さん(NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で蔦屋重三郎役を演じる)。横浜流星さんが、蔦屋重三郎の生き様や、喜多川歌麿、東洲斎写楽などの浮世絵師による作品の魅力を解説し、展覧会の見どころを案内する。また、現代のコンテンツプロデューサーである秋元康さんのインタビューも含まれ、アプリ版ではロングバージョンが配信予定。
詳細は公式サイト:https://tsutaju2025.jp/goods#trg3
形式:
会場レンタル版:展覧会会場入口で専用ガイド機をレンタル。
日本語版:1台650円
英語版:1台800円
*耳が不自由な方には、音声ガイドの文字原稿を同料金で貸出。
アプリ版:「いつでもミュージアム・トーク」アプリでダウンロード可能。会期中何度でも聴ける。
価格:800円
*事前ダウンロード推奨で、OSや機種によっては利用できない場合がある
■展覧会グッズ
江戸情緒溢れつつポップなオリジナルグッズが並ぶ。
■開催概要
展覧会名:
特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」
*展示作品、会期、展示期間、開館日、入館方法等については、今後の諸事情により変更する場合があるので、展覧会公式サイトなどで要確認。また、会期中、一部作品の展示替えを実施する。
前期展示:4月22日~5月18日
後期展示:5月20日~6月15日
会期:
2025年4月22日~6月15日
会場:
東京国立博物館 平成館(上野公園)
開館時間:
9時30分~17時00分
*毎週金・土曜日、5月4日(日・祝)、5月5日(月・祝)は20時00分まで開館 (入館は閉館の30分前まで)
休館日:
月曜日、5月7日(水)。ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館
観覧料金:
一般2100円(一般前売1900円)、大学生1300円(大学生前売 1100円)、高校生900円(高校生前売 700円)
*中学生以下、障がい者とその介護者一名は無料。入館の際に障がい者手帳などを提示する。
*混雑時は入場を待つ可能性がある。
*本券で、会期中観覧当日に限り、東博コレクション展(平常展)も観覧できる。
*会期中、一部作品の展示替えを行う。
*東京国立博物館キャンパスメンバーズ会員の学生は、当日券が1100円(200円割引)。正門チケット売場(窓口)にて、キャンパスメンバーズ会員の学生であることを申し出てから、学生証を提示する。
*本展は事前予約不要。
*本展の観覧券を持っている人は、会期中観覧当日に限り「浮世絵現代」(表慶館 4月22日〜6月15日)を無料で観覧できる。
交通:
JR上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分、東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、千代田線根津駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分
展覧会公式サイト:
https://tsutaju2025.jp/
展覧会公式X:
@tohaku_edo2025
展覧会公式Instagram:
@tohaku_edo2025
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう